 たしかフランスの詩人ポール・ヴァレリーだったと思うが、「後ろ向きに未来に入る」という詩句があるそうだ。まさむねさんの「家紋主義宣言」がこの度めでたく発刊となったが、送っていただいた御本を拝読して、まさに上記ヴァレリーの言をまず思い出した。
たしかフランスの詩人ポール・ヴァレリーだったと思うが、「後ろ向きに未来に入る」という詩句があるそうだ。まさむねさんの「家紋主義宣言」がこの度めでたく発刊となったが、送っていただいた御本を拝読して、まさに上記ヴァレリーの言をまず思い出した。
やっぱりぼくら人間はゴーギャンの絵のタイトルじゃないけど「われわれは何者か、どこから来て、どこへ行くのか」を知りたがる生き物だ。そしていま過剰なまでに日本人が未来へ向かっての視線(眼差し)に晒されて痛めつけられているのだと思う。それは日本の将来性や未来のなさへ通じるような喪失感の予感でもあるだろう。グラウンド・ゼロの時代。
だが、未来ばかりを想い描こうとしても、未来からの視点だけでは多分たいしたアイディアは出てこないだろう、それよりもわれわれはどういう性(サガ)の人たちだったのか、何をしてきたのか、その来歴(後ろ向きに)を知ることがいまこそ必要なのかもしれない。
龍馬ブームにしろ、墓マイラー、歴女の興隆、アシュラーのブームにせよ、いわゆる「日本」が冠につく本の出版ラッシュにせよ、未来へ!未来へ!という視線の投げかけに疲れ、むしろ足元へ至る過去の道からもう一度見つめなおそうというある種の先祖がえりとけっして無縁な風潮ではないと思う。
そして今回「家紋主義宣言」を読んで、あらためてわれわれ日本人とは何者だったのかを強く感じさせられる契機ともなった気がする。家紋に託されたさまざまな物語、その紡ぎの数々。そこに何よりもまさむねさんの個人史も投影されている。
そして改めて確認させてもらったことは、家紋にまつわる意外なおおらかさや自由さということ。家紋が持つ広がりとは、かならずしも厳密な物語の公証性に基づくような類によるのではなく、あくまでもそこに自由な個人の思いがいつも許容されるスペースのようなものとして広がっているのだという事実。
それから家紋の種類の多さ、そのアイコン(イコン)としての面白さと秀逸さ。この家紋をめぐる象形性のひとつをとっても、以前ぼくも「デザイン立国・日本の自叙伝」の架空談義として書かせていただいたこととも相通じると思うのだが、日本人のデザイン感覚力(構想力)のDNAはやはりすごい!と思うのだ。そうしたことも本書を読んで気づかされたことだ。
ぼくは家紋主義宣言を読む前に、以下のような勝手な予感メールをまさむねさんに送らせてもらったことがある。それを原文のままここに引用してみる。
「日本人がいま自分のルーツ探しをしようとする時にあるいは{われわれはどこから来たのか}を知ろうとするときに家紋というのは有力なツールのひとつになりえるように思われます。
何でもありの時代だからこそ何も手がかりのない時代でもあるわけでそこに物語性としての家紋の意義があるようにも思われます。おっしゃられるように見えない制度としての抑圧性については注意しないといけないと思いますが。」「みんな物語がすでに死滅したことは了解していてもやっぱり想像力としての任意の物語性は求めているように思います。それとやはり身体性ということの関連でも妙に家紋の象形チックな紋様がマッチするようにも感じます。」
この思いは本書を読んだ後のいまも変わらない。というよりも21世紀を迎えて、あらためてますます家紋の潮流が新しい、と言えるように思うのだ。ぼくもまさむねさんとは古い付き合いで、途中の音信途絶の時期もいれてもうかれこれ20数年になる。
昨年から骨折を機縁に(?)一本気新聞にも合流させてもらってこうして書かせていただいているわけだけど、年齢の近しい同時代人として、このような書物が同世代のひとりの書き手によって出現したことを誇りに思うし、もっと多くの人の目に触れてほしいと思う。
本の帯にもあるようにこの本は21世紀に出版が予定されていたもっとも危険な書物の一冊かもしれない。読まれていない方があったら、ぼくが言うのもなんですが、ぜひ読んでいただきたいと思います。そしてまず自分と自分の家の歴史(先祖の人たちのことも)についてしばし想いを馳せてみてください。そこからはじめてみましょう。
因みにぼくの家紋は「細輪に中柏」の柏紋である。まさむねさん曰く、ぼくの先祖はアート感覚にあふれたおしゃれな方だったのかもしれませんね、とのご診断。それからぼくの家(先祖)の出は姓から推察しても京都あたりだったのでしょう、ということ。ただし、実際のお墓に彫られた家紋は間違っているのだが。この間実家に帰ってそれを確かめてきた。まあ、いずれにしてもこれも家紋にまつわるおおらかな物語のひとつかもしれない。
最後に、まさむねさんの「家紋主義宣言」の一節でぼくがもっとも好きな語句は次のことばだ。
「今ならば、まだ、僕らの「帰り道」はかろうじてそこに在るに違いないのである。」
文字通り、最終章、結びのことば。ひとの帰り道。それはそのままこれから行く道でもある。もう日が暮れて、道は遠くなってきていても(お家がだんだん遠くなる)、まだ帰り道があると信じたい。
まさむねさん、出版おめでとう!
よしむね
 この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。
この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。 いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。
いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。 だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。
だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。 まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。
まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。 誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。
誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。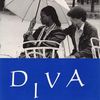 ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。
ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。 しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。
しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。 最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。
最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。 でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?
でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?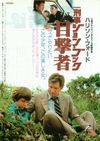 当時この映画が話題になったのは、今もアメリカに現存しているアーミッシュという自給自足の社会(ドイツ系アメリカ人の村社会)が取り上げられていたという物珍しさも多少あったと思う。そこに適度なサスペンスと恋愛ドラマ。今みてもよくできた映画だ。いろんな要素を持っているのでさまざまな切り口の考察が可能だと思われるのだが、ここでは共同体と個人ということに絞りたい。ふたつの共同体が舞台。ひとつは無法もふくめて刑事が所属する社会。もうひとつは上記アーミッシュという共同体。
当時この映画が話題になったのは、今もアメリカに現存しているアーミッシュという自給自足の社会(ドイツ系アメリカ人の村社会)が取り上げられていたという物珍しさも多少あったと思う。そこに適度なサスペンスと恋愛ドラマ。今みてもよくできた映画だ。いろんな要素を持っているのでさまざまな切り口の考察が可能だと思われるのだが、ここでは共同体と個人ということに絞りたい。ふたつの共同体が舞台。ひとつは無法もふくめて刑事が所属する社会。もうひとつは上記アーミッシュという共同体。 この間麻布十番を歩いていたら、ふと暗闇坂の道標が目にとまった。この通りは過去何度も歩いていたのだが、暗闇坂への目線(意識)がまったく失われていたのだった。写真はそのときの通りの方角からみた暗闇坂なのだが、それとともに俄かに思い出したことがあった。ここは昔寺山修司の劇団天井桟敷(兼事務所)があった場所のはずだ。ぼくの記憶が正しければ(もし間違っていたら、どなたかご指摘ください)。
この間麻布十番を歩いていたら、ふと暗闇坂の道標が目にとまった。この通りは過去何度も歩いていたのだが、暗闇坂への目線(意識)がまったく失われていたのだった。写真はそのときの通りの方角からみた暗闇坂なのだが、それとともに俄かに思い出したことがあった。ここは昔寺山修司の劇団天井桟敷(兼事務所)があった場所のはずだ。ぼくの記憶が正しければ(もし間違っていたら、どなたかご指摘ください)。 まさむねさんの「存在の耐えられない軽さ」に続いて80年代に観た映画について書いてみたい。ぼくもその時代の子というか当時は映画青年のはしくれだったということになるだろう。大学時代に映研に入っていたことがあり、多い時でたぶん年間200本くらいの映画を観ていたことがある。しかも80年代の前半はビデオ(VHS)なんてそんなに普及してなかったから、ほとんど映画館に通って観ていた。勤め人になってからもまさむねさんが言っていたのと同じように、80年代当時(90年代も)は年間50本以上は優に観ていたと思う。
まさむねさんの「存在の耐えられない軽さ」に続いて80年代に観た映画について書いてみたい。ぼくもその時代の子というか当時は映画青年のはしくれだったということになるだろう。大学時代に映研に入っていたことがあり、多い時でたぶん年間200本くらいの映画を観ていたことがある。しかも80年代の前半はビデオ(VHS)なんてそんなに普及してなかったから、ほとんど映画館に通って観ていた。勤め人になってからもまさむねさんが言っていたのと同じように、80年代当時(90年代も)は年間50本以上は優に観ていたと思う。 「去年マリエンバートで」のデジタルリメーク版(ニューマスター版)ができたとかいうことで、先月渋谷でリバイバル上映されていたので観に行ってきた。ぼくがこの作品を観たのははっきり覚えていないのだが、たしか劇場で1回、深夜のTV放送で1回観たように記憶している。
「去年マリエンバートで」のデジタルリメーク版(ニューマスター版)ができたとかいうことで、先月渋谷でリバイバル上映されていたので観に行ってきた。ぼくがこの作品を観たのははっきり覚えていないのだが、たしか劇場で1回、深夜のTV放送で1回観たように記憶している。 それに比べると、「去年マリエンバートで」はその仮構ぶりといい、華美さ加減といい、どこか気楽な感じで退屈な映画になったと思えて仕方がない。本当に変わらずに凄いと思うのは、主演女優デルフィーヌ・セイリグの美しさだ。これだけは今も変わらない。
それに比べると、「去年マリエンバートで」はその仮構ぶりといい、華美さ加減といい、どこか気楽な感じで退屈な映画になったと思えて仕方がない。本当に変わらずに凄いと思うのは、主演女優デルフィーヌ・セイリグの美しさだ。これだけは今も変わらない。