かつてNHKで「電子立国 日本の自叙伝」という名物番組があった。それは20世紀の話。こちらは21世紀の架空の談義、ある昼下がりの茶飲み話みたいなもの。テーマはデザイン立国・日本の自叙伝。
A:日本はものづくり、ものづくりって過剰に言い過ぎるね。これこそ戦後の成功体験にもとづく依怙地な理屈に思えるよ。資源のない国だから技術と生産しかないっていう。確かにモノはなくならないから、ものづくりは大事だが、よく言われることだけど、生産という意味ではひとつのプロダクト(産業分野)で企業が1社から2社あればいいよ。何社もあって多すぎるよ。とにかく過剰。みんな横並びになっちゃったし。
B:じゃ、他はどうするの? 食べていけなくなるよ。
A:これから日本はデザイン立国を目指すべき。それこそ小さなもの(半導体素子)から大きなもの(家、自動車、建築)まで、あらゆるもののデザイン・設計の仕事に特化してゆけばいい。日本人のセンスとか昔からのメンタリティー、縮み志向の文化といい、デザイン精神にあふれた民族性だと思うよ。アニメもファッションも、ファニチャーもみんなデザインがベースさ。デザインはアナログに近いし、なかなか真似できないよ。
B:デザインだけでペイするかな。
A:生産での物づくりについては、世界で戦うにはもう規模のメリット(大量生産)とローコストしか将来の道はやっぱりないよ。ここはもう日本の領域じゃない。付加価値品とかいっても無理だね。いずれ必ずコモディティー化してゆく。ここで戦うのは国内1社、2社くらいでいいよ。あとは小ぢんまりとした小規模単位のデザイン集団の会社になればいい。名とか面子とかを捨てて、黒子のデザイン・コンテンツ設計集団でいいじゃないか。できるだけ身軽であることが大事だよ。
B:これからは人口も減少してゆくからねぇ。
A:そうだよ。もう人も増えないんだから、集団や組織自体はだんだん小規模化していって、その連携を心がけでゆけばいいんだ。江戸時代の「連」みたいにね。かりに売上が伸びなくても、人口減以上の売上をキープできれば一人当たりの売上高は逆に増える。それでよしとしないと。そして一個人がより豊かになればいいじゃないか。
B:うまく行くかな。
A:中途半端が一番良くない。中庸は美徳じゃない。ここは思い切りだね。うまく行かなきゃまた修正すればいい。それからデザインとあわせて観光立国を目指すべき。とにかくアジアの人たちにバンバン来てもらおう。客へのもてなしとかサービスは日本人はまだ一流だと思うからね。微妙な心遣いとか絶品だと思うよ。環境面でも清潔だし。一人一人が豊かな気持ちで良い国になれば必ず訪れてくる人は沢山いるよ。
B:デザインと観光ね。けっきょくソフトだね。
A:いや、ぼくはソフトという言い方はあまり好きじゃないな。ちゃんとハード(モノや器、土地)を伴ったソフトサービスだよ。だから両方あるさ。デザイン心あふれるモノとサービス。でも、まあ、ほどほどでいいじゃない。その意味ではやっぱり中庸か。そして坂道を上るイメージよりは、ほんの少し下ってゆくような感じかな。そういう時のほうが人に優しく気遣いできるようにも思えるしね。
よしむね
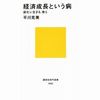 平川克美さんという現役の社長さんが書かれた本で講談社現代新書の一冊。この方はたしかフランス文学者の内田樹さんの小学校時代からのご友人だそう。内田さんとは共著で本を書かれているらしいが、ぼくは初めてこの方の本を読んだ。
平川克美さんという現役の社長さんが書かれた本で講談社現代新書の一冊。この方はたしかフランス文学者の内田樹さんの小学校時代からのご友人だそう。内田さんとは共著で本を書かれているらしいが、ぼくは初めてこの方の本を読んだ。 ちょうど「We ARE THE WORLD」から25年めの今年、ハイチ・バージョンが出た。本当はマイケル・ジャクソンの死もあり25周年記念のようなものを考えていたところ、ハイチ地震があって、ハイチ・バージョンに変わったらしいけど。
ちょうど「We ARE THE WORLD」から25年めの今年、ハイチ・バージョンが出た。本当はマイケル・ジャクソンの死もあり25周年記念のようなものを考えていたところ、ハイチ地震があって、ハイチ・バージョンに変わったらしいけど。 こうした映像をみていてつくづく思うのは、なぜ日本ではこのようなボランタリーな試みがすぐに行われないのだろうかということ。詳しいことは分からないが、所属事務所の違いとかレコード会社の問題、レーベルの問題とかいろいろ障壁が大きいのだろうか。加えてたしかにアメリカやイギリスと違い、ミュージックシーンにおけるインパクトの大きさの違いもあると思うが。もちろんこうしたバンド・エイドによって世界が変わるわけではないとしても。
こうした映像をみていてつくづく思うのは、なぜ日本ではこのようなボランタリーな試みがすぐに行われないのだろうかということ。詳しいことは分からないが、所属事務所の違いとかレコード会社の問題、レーベルの問題とかいろいろ障壁が大きいのだろうか。加えてたしかにアメリカやイギリスと違い、ミュージックシーンにおけるインパクトの大きさの違いもあると思うが。もちろんこうしたバンド・エイドによって世界が変わるわけではないとしても。
 最近、鳩山政権の支持率低下が盛んに喧伝されるようになった。直近の世論調査ではたしか30%を割りこむところまで低下しているらしい。米国のオバマ大統領の陰りも然り。両者ともいわゆる蜜月期間をとうに過ぎて、マスコミによる容赦ない反撃のようなものをふくめて、支持率の下降局面に入ってきているというわけだ。
最近、鳩山政権の支持率低下が盛んに喧伝されるようになった。直近の世論調査ではたしか30%を割りこむところまで低下しているらしい。米国のオバマ大統領の陰りも然り。両者ともいわゆる蜜月期間をとうに過ぎて、マスコミによる容赦ない反撃のようなものをふくめて、支持率の下降局面に入ってきているというわけだ。 民主党の施策に対して、それと対抗し封じ込めるような新しい戦略やビジョンがまったく出てこない。かといって新しい政党として出直してくるだけのポテンシャルがあるとも思えない。せいぜい小泉元首相の生意気な次男坊や、かわいすぎるといわれる女性の市議に出てもらって人気取りの街頭演説を行っているていたらくだ。
民主党の施策に対して、それと対抗し封じ込めるような新しい戦略やビジョンがまったく出てこない。かといって新しい政党として出直してくるだけのポテンシャルがあるとも思えない。せいぜい小泉元首相の生意気な次男坊や、かわいすぎるといわれる女性の市議に出てもらって人気取りの街頭演説を行っているていたらくだ。 今回民主党に変わったことで、あらためて自民党政権時代に日本がどれだけ既得権益で生きてきた人が多かったか、そのしがらみの多さが白日の下に垣間見える機会があっただけでも良かったのではないか、とぼくは思っている。それがなんとなく分かっただけでも民主党に政権が変わった意味がある、と。だから別に民主党の支持率が下がろうが別にいいじゃないか。
今回民主党に変わったことで、あらためて自民党政権時代に日本がどれだけ既得権益で生きてきた人が多かったか、そのしがらみの多さが白日の下に垣間見える機会があっただけでも良かったのではないか、とぼくは思っている。それがなんとなく分かっただけでも民主党に政権が変わった意味がある、と。だから別に民主党の支持率が下がろうが別にいいじゃないか。 だが日本が経済と繁栄の軌道に乗ってからは、ただ惰性操舵のままに行けばよくなり次第に事なかれ主義になり、自らを変革する力を失い、ただただ劣化してもはや斬新な政策を打ち出す能力がほぼ皆無に等しい現在の状態になってしまったということなのかもしれない。でもそれでいいじゃないか。だって戦後60年以上もそうやって政権の座にあり続けたのだから。
だが日本が経済と繁栄の軌道に乗ってからは、ただ惰性操舵のままに行けばよくなり次第に事なかれ主義になり、自らを変革する力を失い、ただただ劣化してもはや斬新な政策を打ち出す能力がほぼ皆無に等しい現在の状態になってしまったということなのかもしれない。でもそれでいいじゃないか。だって戦後60年以上もそうやって政権の座にあり続けたのだから。 これはとても残念な話。ここ20年以上、友人たちとテニスをやってきたのだが、その施設が例の、うわさの厚生年金関連の施設だったため、世田谷区に払い下げになってしまい、実質使えなくなってしまった。そこは料金も比較的安くかつ交通のアクセスをふくめて東京近郊のいろんな所に住んでいる友人にとっても集まりやすい場所だったのだが。
これはとても残念な話。ここ20年以上、友人たちとテニスをやってきたのだが、その施設が例の、うわさの厚生年金関連の施設だったため、世田谷区に払い下げになってしまい、実質使えなくなってしまった。そこは料金も比較的安くかつ交通のアクセスをふくめて東京近郊のいろんな所に住んでいる友人にとっても集まりやすい場所だったのだが。 ずっとずっと昔、「岸辺のアルバム」というTVドラマがあった。若い人はまったく知らないと思うのだけれど。アラ筋はいわゆる新興住宅街(番組では多摩川沿い、田園都市沿線エリア)を舞台に崩壊してゆく家族の物語だった。ドラマのエンディングはたしか多摩川の決壊で、岸辺(川の土手)にたたずむ家族たちのシーンだったように記憶している。これはこれでその後の風潮や時代性(中流階級幻想とその崩壊?)を先取りするような良いドラマ(脚本は山田太一)だったと思う。岸辺ということでたまたま思い出して書いたままで、本題とはまったく関連のない導入になってしまったようです。ご免なさい。(最初から横道にそれてしまいました。)
ずっとずっと昔、「岸辺のアルバム」というTVドラマがあった。若い人はまったく知らないと思うのだけれど。アラ筋はいわゆる新興住宅街(番組では多摩川沿い、田園都市沿線エリア)を舞台に崩壊してゆく家族の物語だった。ドラマのエンディングはたしか多摩川の決壊で、岸辺(川の土手)にたたずむ家族たちのシーンだったように記憶している。これはこれでその後の風潮や時代性(中流階級幻想とその崩壊?)を先取りするような良いドラマ(脚本は山田太一)だったと思う。岸辺ということでたまたま思い出して書いたままで、本題とはまったく関連のない導入になってしまったようです。ご免なさい。(最初から横道にそれてしまいました。) こうした動きが金融をまきこんである面だけ先行加速していったのがそれこそリーマンショック前の一部の趨勢だったようにも思う。そしてリーマンショック以後を見ると、さすがにフロー一辺倒のような動きにも多少見直しが入りつつあるようにも思える。だが一度加速した動きがほんとうに巻き戻されるかどうか。人は昔とった杵柄がなかなか忘れられないものだ。
こうした動きが金融をまきこんである面だけ先行加速していったのがそれこそリーマンショック前の一部の趨勢だったようにも思う。そしてリーマンショック以後を見ると、さすがにフロー一辺倒のような動きにも多少見直しが入りつつあるようにも思える。だが一度加速した動きがほんとうに巻き戻されるかどうか。人は昔とった杵柄がなかなか忘れられないものだ。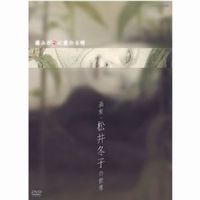
 ・けっきょくここで取り上げられているもののひとつは死ということなのだが、現代の若者は死に惹きつけられているのかもしれない
・けっきょくここで取り上げられているもののひとつは死ということなのだが、現代の若者は死に惹きつけられているのかもしれない ラーメン二郎はWikipediaによると、創業は1968年だそう。ぼくもラーメン二郎の評判は一応知っており、休日に山の手通りを車で走っていると、店の前でよく長蛇の列が作られているのを何度も目にしていたのだけれど、味がこってりタイプ(トンコツベース強し?)と聞いていたので、それが嫌でなんとなく敬遠していたのだが・・・。
ラーメン二郎はWikipediaによると、創業は1968年だそう。ぼくもラーメン二郎の評判は一応知っており、休日に山の手通りを車で走っていると、店の前でよく長蛇の列が作られているのを何度も目にしていたのだけれど、味がこってりタイプ(トンコツベース強し?)と聞いていたので、それが嫌でなんとなく敬遠していたのだが・・・。 一、清く正しく美しく、散歩に読書にニコニコ貯金、週末は釣り、ゴルフ、写経
一、清く正しく美しく、散歩に読書にニコニコ貯金、週末は釣り、ゴルフ、写経 この間の週末、奈良・京都の小旅行の際、京都の吉田神社にも行ってきた。もともと私の姓と同じであり、家紋の話(これについてはまさむねさんが専門家)などからもこの辺り一帯が祖先のルーツ(出)かもしれないという興味もあって訪ねてみた。吉田神社そのものは有名かつ立派な神社なので特にここで紹介めいたことは書くつもりはない。
この間の週末、奈良・京都の小旅行の際、京都の吉田神社にも行ってきた。もともと私の姓と同じであり、家紋の話(これについてはまさむねさんが専門家)などからもこの辺り一帯が祖先のルーツ(出)かもしれないという興味もあって訪ねてみた。吉田神社そのものは有名かつ立派な神社なので特にここで紹介めいたことは書くつもりはない。 それから、関連したことだけれど、日本には何もない空間をいわゆる「やしろ」として崇める慣習があったと言われているようだが、同じように良い空間にはかならずそうした意味のない空間を寿ぐような場所があるということ。ゆとりともいえるだろうし、遊びの空間とも、赤瀬川原平さんならそれこそまさに「トマソン」だとおっしゃるかもしれないような場所。添付写真は吉田神社で見られた「やしろ」のような空間の数々。これについては神聖化している理由はちゃんとあるのかもしれないが。
それから、関連したことだけれど、日本には何もない空間をいわゆる「やしろ」として崇める慣習があったと言われているようだが、同じように良い空間にはかならずそうした意味のない空間を寿ぐような場所があるということ。ゆとりともいえるだろうし、遊びの空間とも、赤瀬川原平さんならそれこそまさに「トマソン」だとおっしゃるかもしれないような場所。添付写真は吉田神社で見られた「やしろ」のような空間の数々。これについては神聖化している理由はちゃんとあるのかもしれないが。 いずれにしても吉田神社には上記のような空間がたしかにあった。それから、君が代で歌われている「さざれ石」の原形(?)を祭っていることを知ることができたのも僥倖だった。
いずれにしても吉田神社には上記のような空間がたしかにあった。それから、君が代で歌われている「さざれ石」の原形(?)を祭っていることを知ることができたのも僥倖だった。