
映画「シングルマン」を見た。バイセクシャルの話なのだが、そうした題材というよりも、描かれている当たり前の個人としての孤独感に共感できるし、ぼくはとても好きな部類に入る映画だ。監督がファッション・デザイナーのトム・フォード(ぼくはこの人の眼鏡のデザインが好きだ)ということもあり、映像がスタイリッシュで抑制が効いていてかつ最小限の美しさにあふれているような感じもいい。どこかノスタルジックな映像表現だ。もちろん映像だけではなく、人物や状況の描写も優れていると思う。
だが、それよりも一番良かったのは1960年代のアメリカという舞台設定だ。ちょうどキューバ危機の前後この当時のアメリカのおそらくミドルクラス以上の生活風景。芝生つきの広い家。モータリゼーション(自動車)の進展期。主人公が運転するアナログ的なインパネをもつ4ドア自動車がまたいいのだ。これはイーストウッドの「グラン・トリノ」の世界にも通じるもの。そして銀行での顧客サービス。すべてにおいてまだ上品で余裕があった時代のアメリカ白人社会が透けてみえるようだ。
総じて中流やや以上の暮らしが中心なのだろうが、それこそあの時代もっとも全世界があこがれていたに違いないアメリカの暮らし。冷蔵庫とTVと自動車と広い庭つきの白亜の家(それは空虚と裏腹だとしても)。そしてリビングの風景、60年代のファッション。女性の髪形の編み上げかたの面白さ。ポップだった時代。とくにジュリアン・ムーアのパーマネント・ウェイブがまたあの時代のポップな感じを想わせていい。ツイッギーみたいな感じか。ビートルズもこの時代の申し子。
いずれにしてもその功罪は別にして、それらはどういう時代であれまず貧しい国が成長を目指す過程でかならず思い描くであろう日常生活としての欲望のかたちにつながっている。そして映画のなかでの自信にみちて明るく紳士的・淑女的にみえる登場人物たち(もちろん登場人物たちの性格のねじれはあるのだが)。いっぽうで個人によってはどこか破滅的になりつつある(主人公が感じている核戦争の危機による世界の終わり)予感もある。
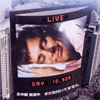
そうした諸々の変化に取り巻かれながらも、まだ健全で強く、退廃的であることが許されていたアメリカの古き良き時代。それは「トゥルーマン・ショー」の管理社会まではまだずっと遠い時代でもあり、登場人物はみんなやたらとタバコを吸っていたりするのだ。
最近読んだ関川夏央さんの「坂の上の雲と日本人」によると、司馬遼太郎さんの見方でもあるのだろうが、日本は日露戦争までの坂に至るまでは健康で明るい国だった(いわゆる偉大な明治だった)が、その達成以降劣化してゆくということになる。
その言い方にならえば世界史的にみればおそらくアメリカの全盛時代は1950年代から60年代前半あたりまで(ケネディ大統領が暗殺される辺りまで)で、それ以降はベトナム戦争への没入とともに劣化していくことになるといえるのかもしれない。そしてもっと広げていえば西欧やアメリカを中心とした先進国が文化的にも成長という意味でもまだ全的に輝いて見えた時代とはおそらく60年代までということになるのではないか。文化史的にみればフーコーとかラカン、バルトとかレヴィ=ストロースなどの一連のいわゆる構造主義者の著作が目白押しだったのが1966年という年だった(文化的にエポックの年)という指摘もあるようだ。
そしてこの辺りを境に日本でも世界でも学生運動が頻発し、その挫折とともにどこか停滞のステージに入っていく。70年代は石油危機が起こり、ローマクラブからは「成長の限界」というレポートが出るDecadeでもあった。先進国での人口増加のカーブ曲線もこの辺りをピークに変局していくともいわれている。ぼくが中学生から大人になってゆくのはこれ以降の時代だ。
没落の予感に怯えつつ、でもまだ日常生活の風景(消費社会)としてはアメリカが頂上の栄華を極めていた時代。だいぶ蛇足が長くなってしまったが、そのように紛れもなくある時代の「ひとつの坂の上」の雰囲気と、どこかそこはかとなく漂っているノスタルジーの感覚がとてもよく描かれていたということだけでも、「シングルマン」を見る価値はあるように思う。そしてそこにひとりの個人史の生と死もオーバーラップされて刻まれているのだ。
よしむね

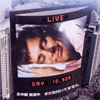
 羽田空港の新ターミナルビル(国際線)に行ってきた。家内が国内線を利用したその帰り、迎えに行ったついでに開設した空港ターミナルビルを見てきた。第一印象としては施設は意外にシンプルでコンパクトという感じ。予想していたよりも施設内のロビーはそんなに広くなくコンパクトというのが一番強い実感。
羽田空港の新ターミナルビル(国際線)に行ってきた。家内が国内線を利用したその帰り、迎えに行ったついでに開設した空港ターミナルビルを見てきた。第一印象としては施設は意外にシンプルでコンパクトという感じ。予想していたよりも施設内のロビーはそんなに広くなくコンパクトというのが一番強い実感。 それとなんといっても便利だと驚いたのは、モノレールの新駅改札口がそのまま空港ターミナルのフロアーと直結していること(添付写真)。以前京急の広告CGだったかで国際線の空港ターミナルに電車が乗り上げているつり革広告?があったと思うのだが(それを見て本当にそうなっていると思っていた人もいるという冗談めいた話を聞いたことがあるけど、)それが冗談ではなくまさにほぼ近い形で実現されていることは驚きだった。駅の改札を出ればすぐそこは国際線のターミナルだ。
それとなんといっても便利だと驚いたのは、モノレールの新駅改札口がそのまま空港ターミナルのフロアーと直結していること(添付写真)。以前京急の広告CGだったかで国際線の空港ターミナルに電車が乗り上げているつり革広告?があったと思うのだが(それを見て本当にそうなっていると思っていた人もいるという冗談めいた話を聞いたことがあるけど、)それが冗談ではなくまさにほぼ近い形で実現されていることは驚きだった。駅の改札を出ればすぐそこは国際線のターミナルだ。 むしろ本物志向でいっそほんとうの短い歌舞伎の演目を上演したり、コスプレのGALたちのファッションショーみたいなものをやったり、ストリートミュージシャンに日本の今を歌ってもらったり、そういうことができるような劇場やスペースをターミナル内に常設しても良かったのではないか。どうせ国力も衰退しているのだし、もっと面白い活力を見せるということで、そうした本物で異国を訪れた外国の方をまずもって圧倒してみるという試みがあっても良かったのではないか、などど勝手な空想を膨らませた次第。
むしろ本物志向でいっそほんとうの短い歌舞伎の演目を上演したり、コスプレのGALたちのファッションショーみたいなものをやったり、ストリートミュージシャンに日本の今を歌ってもらったり、そういうことができるような劇場やスペースをターミナル内に常設しても良かったのではないか。どうせ国力も衰退しているのだし、もっと面白い活力を見せるということで、そうした本物で異国を訪れた外国の方をまずもって圧倒してみるという試みがあっても良かったのではないか、などど勝手な空想を膨らませた次第。 「ブラタモリ」はご存知タモリが東京という町の今昔をどこかワープしながら散歩するというような内容。たとえばこの間あった新宿の探索では、新宿という町が江戸時代からいかに水道(玉川上水)とのかかわりをもって発展してきたかという観点でその足跡をたどりながら散歩してゆく流れになっていた。たとえば四谷の交差点のコーナーの曲がり具合が実は上水の曲がり具合をそのまま反映したものであるという事実や、上水からの分水(枝水)が今は柵の脇の草の生えたただの無意味な土地のように伸びていることなどが明らかにされてゆく。
「ブラタモリ」はご存知タモリが東京という町の今昔をどこかワープしながら散歩するというような内容。たとえばこの間あった新宿の探索では、新宿という町が江戸時代からいかに水道(玉川上水)とのかかわりをもって発展してきたかという観点でその足跡をたどりながら散歩してゆく流れになっていた。たとえば四谷の交差点のコーナーの曲がり具合が実は上水の曲がり具合をそのまま反映したものであるという事実や、上水からの分水(枝水)が今は柵の脇の草の生えたただの無意味な土地のように伸びていることなどが明らかにされてゆく。 それから「世界ふれあい街歩き」のほうはカメラマンの体に装着された水平移動カメラが世界のある都市の路地をまるで縫ったり這ったりするように移動してゆきながら、その間に現地の人とまるで対話しているような日本語のナレーションが入りつつ進んでゆくというコンセプト。これを早朝(朝の出勤時刻)から夕方まで街中を歩き続けるシーンが続いて、そこで偶然に出会った人やモノ、風景を映し出すという流れになっている。
それから「世界ふれあい街歩き」のほうはカメラマンの体に装着された水平移動カメラが世界のある都市の路地をまるで縫ったり這ったりするように移動してゆきながら、その間に現地の人とまるで対話しているような日本語のナレーションが入りつつ進んでゆくというコンセプト。これを早朝(朝の出勤時刻)から夕方まで街中を歩き続けるシーンが続いて、そこで偶然に出会った人やモノ、風景を映し出すという流れになっている。