
映画「シングルマン」を見た。バイセクシャルの話なのだが、そうした題材というよりも、描かれている当たり前の個人としての孤独感に共感できるし、ぼくはとても好きな部類に入る映画だ。監督がファッション・デザイナーのトム・フォード(ぼくはこの人の眼鏡のデザインが好きだ)ということもあり、映像がスタイリッシュで抑制が効いていてかつ最小限の美しさにあふれているような感じもいい。どこかノスタルジックな映像表現だ。もちろん映像だけではなく、人物や状況の描写も優れていると思う。
だが、それよりも一番良かったのは1960年代のアメリカという舞台設定だ。ちょうどキューバ危機の前後この当時のアメリカのおそらくミドルクラス以上の生活風景。芝生つきの広い家。モータリゼーション(自動車)の進展期。主人公が運転するアナログ的なインパネをもつ4ドア自動車がまたいいのだ。これはイーストウッドの「グラン・トリノ」の世界にも通じるもの。そして銀行での顧客サービス。すべてにおいてまだ上品で余裕があった時代のアメリカ白人社会が透けてみえるようだ。
総じて中流やや以上の暮らしが中心なのだろうが、それこそあの時代もっとも全世界があこがれていたに違いないアメリカの暮らし。冷蔵庫とTVと自動車と広い庭つきの白亜の家(それは空虚と裏腹だとしても)。そしてリビングの風景、60年代のファッション。女性の髪形の編み上げかたの面白さ。ポップだった時代。とくにジュリアン・ムーアのパーマネント・ウェイブがまたあの時代のポップな感じを想わせていい。ツイッギーみたいな感じか。ビートルズもこの時代の申し子。
いずれにしてもその功罪は別にして、それらはどういう時代であれまず貧しい国が成長を目指す過程でかならず思い描くであろう日常生活としての欲望のかたちにつながっている。そして映画のなかでの自信にみちて明るく紳士的・淑女的にみえる登場人物たち(もちろん登場人物たちの性格のねじれはあるのだが)。いっぽうで個人によってはどこか破滅的になりつつある(主人公が感じている核戦争の危機による世界の終わり)予感もある。
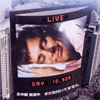
そうした諸々の変化に取り巻かれながらも、まだ健全で強く、退廃的であることが許されていたアメリカの古き良き時代。それは「トゥルーマン・ショー」の管理社会まではまだずっと遠い時代でもあり、登場人物はみんなやたらとタバコを吸っていたりするのだ。
最近読んだ関川夏央さんの「坂の上の雲と日本人」によると、司馬遼太郎さんの見方でもあるのだろうが、日本は日露戦争までの坂に至るまでは健康で明るい国だった(いわゆる偉大な明治だった)が、その達成以降劣化してゆくということになる。
その言い方にならえば世界史的にみればおそらくアメリカの全盛時代は1950年代から60年代前半あたりまで(ケネディ大統領が暗殺される辺りまで)で、それ以降はベトナム戦争への没入とともに劣化していくことになるといえるのかもしれない。そしてもっと広げていえば西欧やアメリカを中心とした先進国が文化的にも成長という意味でもまだ全的に輝いて見えた時代とはおそらく60年代までということになるのではないか。文化史的にみればフーコーとかラカン、バルトとかレヴィ=ストロースなどの一連のいわゆる構造主義者の著作が目白押しだったのが1966年という年だった(文化的にエポックの年)という指摘もあるようだ。
そしてこの辺りを境に日本でも世界でも学生運動が頻発し、その挫折とともにどこか停滞のステージに入っていく。70年代は石油危機が起こり、ローマクラブからは「成長の限界」というレポートが出るDecadeでもあった。先進国での人口増加のカーブ曲線もこの辺りをピークに変局していくともいわれている。ぼくが中学生から大人になってゆくのはこれ以降の時代だ。
没落の予感に怯えつつ、でもまだ日常生活の風景(消費社会)としてはアメリカが頂上の栄華を極めていた時代。だいぶ蛇足が長くなってしまったが、そのように紛れもなくある時代の「ひとつの坂の上」の雰囲気と、どこかそこはかとなく漂っているノスタルジーの感覚がとてもよく描かれていたということだけでも、「シングルマン」を見る価値はあるように思う。そしてそこにひとりの個人史の生と死もオーバーラップされて刻まれているのだ。
よしむね
 まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。
まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。 誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。
誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。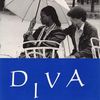 ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。
ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。 しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。
しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。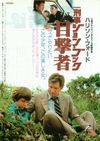 当時この映画が話題になったのは、今もアメリカに現存しているアーミッシュという自給自足の社会(ドイツ系アメリカ人の村社会)が取り上げられていたという物珍しさも多少あったと思う。そこに適度なサスペンスと恋愛ドラマ。今みてもよくできた映画だ。いろんな要素を持っているのでさまざまな切り口の考察が可能だと思われるのだが、ここでは共同体と個人ということに絞りたい。ふたつの共同体が舞台。ひとつは無法もふくめて刑事が所属する社会。もうひとつは上記アーミッシュという共同体。
当時この映画が話題になったのは、今もアメリカに現存しているアーミッシュという自給自足の社会(ドイツ系アメリカ人の村社会)が取り上げられていたという物珍しさも多少あったと思う。そこに適度なサスペンスと恋愛ドラマ。今みてもよくできた映画だ。いろんな要素を持っているのでさまざまな切り口の考察が可能だと思われるのだが、ここでは共同体と個人ということに絞りたい。ふたつの共同体が舞台。ひとつは無法もふくめて刑事が所属する社会。もうひとつは上記アーミッシュという共同体。 まさむねさんの「存在の耐えられない軽さ」に続いて80年代に観た映画について書いてみたい。ぼくもその時代の子というか当時は映画青年のはしくれだったということになるだろう。大学時代に映研に入っていたことがあり、多い時でたぶん年間200本くらいの映画を観ていたことがある。しかも80年代の前半はビデオ(VHS)なんてそんなに普及してなかったから、ほとんど映画館に通って観ていた。勤め人になってからもまさむねさんが言っていたのと同じように、80年代当時(90年代も)は年間50本以上は優に観ていたと思う。
まさむねさんの「存在の耐えられない軽さ」に続いて80年代に観た映画について書いてみたい。ぼくもその時代の子というか当時は映画青年のはしくれだったということになるだろう。大学時代に映研に入っていたことがあり、多い時でたぶん年間200本くらいの映画を観ていたことがある。しかも80年代の前半はビデオ(VHS)なんてそんなに普及してなかったから、ほとんど映画館に通って観ていた。勤め人になってからもまさむねさんが言っていたのと同じように、80年代当時(90年代も)は年間50本以上は優に観ていたと思う。 「去年マリエンバートで」のデジタルリメーク版(ニューマスター版)ができたとかいうことで、先月渋谷でリバイバル上映されていたので観に行ってきた。ぼくがこの作品を観たのははっきり覚えていないのだが、たしか劇場で1回、深夜のTV放送で1回観たように記憶している。
「去年マリエンバートで」のデジタルリメーク版(ニューマスター版)ができたとかいうことで、先月渋谷でリバイバル上映されていたので観に行ってきた。ぼくがこの作品を観たのははっきり覚えていないのだが、たしか劇場で1回、深夜のTV放送で1回観たように記憶している。 それに比べると、「去年マリエンバートで」はその仮構ぶりといい、華美さ加減といい、どこか気楽な感じで退屈な映画になったと思えて仕方がない。本当に変わらずに凄いと思うのは、主演女優デルフィーヌ・セイリグの美しさだ。これだけは今も変わらない。
それに比べると、「去年マリエンバートで」はその仮構ぶりといい、華美さ加減といい、どこか気楽な感じで退屈な映画になったと思えて仕方がない。本当に変わらずに凄いと思うのは、主演女優デルフィーヌ・セイリグの美しさだ。これだけは今も変わらない。 この間、ラジオを「ながら」で聞いていたとき、今年2009年が映画「
この間、ラジオを「ながら」で聞いていたとき、今年2009年が映画「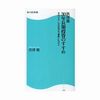 20年ではないが、「
20年ではないが、「 ぼくが最初この映画に感動したのは、これもまたあまりにも有名なラストの古い映画のキスシーンの数珠つながりのシーンだ。洗礼の水でも浴びるようなフィルムの切れはしたちの映像の連鎖。検閲にひっかからないようにフィリップ・ノワレ演じる映写技師アルフレードがそれらのフィルムを切り刻んでいたわけだが、その「記念品(形見)」を主人公が上映してながめるシーン。ここには過ぎた時への回想とともに、トルナトーレ監督自身による古き映画への紛れもないオマージュもあったはずだ。
ぼくが最初この映画に感動したのは、これもまたあまりにも有名なラストの古い映画のキスシーンの数珠つながりのシーンだ。洗礼の水でも浴びるようなフィルムの切れはしたちの映像の連鎖。検閲にひっかからないようにフィリップ・ノワレ演じる映写技師アルフレードがそれらのフィルムを切り刻んでいたわけだが、その「記念品(形見)」を主人公が上映してながめるシーン。ここには過ぎた時への回想とともに、トルナトーレ監督自身による古き映画への紛れもないオマージュもあったはずだ。 そして映画の最後のほうで、アルフレードの死の知らせをうけて故郷へ帰る決心をした主人公はなにかと和解し(過去と現在に連なる時間と?)、その葬式参列の日にかつての知人たちの多くの顔に出会う。そこに見いだされるのは、時が確実に刻みつけた人々の顔の変化であり、それと同じだけ主人公も年を重ねたという事実、そしてそれらがある懐かしさをともなって現れてくるのだ。ちょうどプルーストが「失われた時を求めて」における最終巻の「見出された時」の仮装パーティーで「時」の交差と出会ったかのように?・・・・。
そして映画の最後のほうで、アルフレードの死の知らせをうけて故郷へ帰る決心をした主人公はなにかと和解し(過去と現在に連なる時間と?)、その葬式参列の日にかつての知人たちの多くの顔に出会う。そこに見いだされるのは、時が確実に刻みつけた人々の顔の変化であり、それと同じだけ主人公も年を重ねたという事実、そしてそれらがある懐かしさをともなって現れてくるのだ。ちょうどプルーストが「失われた時を求めて」における最終巻の「見出された時」の仮装パーティーで「時」の交差と出会ったかのように?・・・・。 21世紀を前にしてその最後の10年の手前で公開されたニュー・シネマ・パラダイスは、そう思えば予見的な映画だったのかもしれない。それは華やかな未来よりもどこか追憶の過去にひきよせられ、新しさよりも追憶のさざ波に揺れているような映画だからだが、それこそまさに現代の風景そのものにも思える。現代において新しいものはまだあるのか? あるのは追憶だけなのか? 失われた過去への記憶だけなのか? 果たして、ぼくらはこの老いた日本の再生の果てに、ニュー・パラダイスを見ることができるだろうか?
21世紀を前にしてその最後の10年の手前で公開されたニュー・シネマ・パラダイスは、そう思えば予見的な映画だったのかもしれない。それは華やかな未来よりもどこか追憶の過去にひきよせられ、新しさよりも追憶のさざ波に揺れているような映画だからだが、それこそまさに現代の風景そのものにも思える。現代において新しいものはまだあるのか? あるのは追憶だけなのか? 失われた過去への記憶だけなのか? 果たして、ぼくらはこの老いた日本の再生の果てに、ニュー・パラダイスを見ることができるだろうか?  「サイドウェイズ」は2004年同名のハリウッド映画のリメイク版。監督は外国人のチェリン・グラック。主演陣は日本人の俳優で小日向文世、生瀬勝久、鈴木京香、菊池凛子の4名。まず役者たちの顔ぶれが良い。物語は解説文をそのまま使わせてもらうと、「ワインの産地、カリフォルニアのナパ・バレーを舞台に、さえない40代の男二人のパッとしない人生が少しずつ動き出していく様をていねいに描く」とある。まあたしかにそのように動いてゆく。そこに同世代といってよい二人の女たち(鈴木京香と菊池凛子)が絡む。
「サイドウェイズ」は2004年同名のハリウッド映画のリメイク版。監督は外国人のチェリン・グラック。主演陣は日本人の俳優で小日向文世、生瀬勝久、鈴木京香、菊池凛子の4名。まず役者たちの顔ぶれが良い。物語は解説文をそのまま使わせてもらうと、「ワインの産地、カリフォルニアのナパ・バレーを舞台に、さえない40代の男二人のパッとしない人生が少しずつ動き出していく様をていねいに描く」とある。まあたしかにそのように動いてゆく。そこに同世代といってよい二人の女たち(鈴木京香と菊池凛子)が絡む。 一方の「アンナと過ごした4日間」はこれとは対蹠的にまったく異常さに基づくような内容になっている。監督はポーランドのイエジー・スコリモフスキー。現代世界の特徴のひとつが等質性にあるとすれば、この映画はそのすべてにおいてこれと反対を行くような設定だ。主人公は病院の火葬場で働くまったく冴えない寡黙な独身男。年老いた祖母との二人暮しだが、ほとんど引きこもりのような二人の生活。やがて祖母の死。そして異常なレイプ事件を目撃。主人公自身も過去に異常な暴力事件(?)に遭った過去を持つ。
一方の「アンナと過ごした4日間」はこれとは対蹠的にまったく異常さに基づくような内容になっている。監督はポーランドのイエジー・スコリモフスキー。現代世界の特徴のひとつが等質性にあるとすれば、この映画はそのすべてにおいてこれと反対を行くような設定だ。主人公は病院の火葬場で働くまったく冴えない寡黙な独身男。年老いた祖母との二人暮しだが、ほとんど引きこもりのような二人の生活。やがて祖母の死。そして異常なレイプ事件を目撃。主人公自身も過去に異常な暴力事件(?)に遭った過去を持つ。 雑誌記事などによるとフランスで空前の日本ブームだという。空前というのがどの程度なのかよく分からないが、同じように日本ブームという意味ではちょうど150年くらい前の日本文化への嗜好(いわゆるジャポニズム)がこれに匹敵するのだろうか。今回の一連のブームのなかでは日本を題材にした小説も結構多く書かれているようだ。最近では本国フランスでベストセラーになったといわれている「優雅なハリネズミ」(これに登場するのは映画監督小津安二郎を思わせるような日本人オズが登場しているそうだ。ぼくはまだ読んでいないが。)という小説もあるらしい。ぼくも今年にはいって日本を題材にした一冊である「さりながら」(フィリップ・フォレスト著)を読んだことがある。夏目漱石、小林一茶、山端庸介(写真家)を主人公に設定しながら、コント風仕立ての枠組みを使って単に日本への関心にとどまらずに、自身の遺児への思いと重ね合わせながら哲学的な省察(同時代への考察)を試みている、抑制の効いた佳品だったと記憶している。
雑誌記事などによるとフランスで空前の日本ブームだという。空前というのがどの程度なのかよく分からないが、同じように日本ブームという意味ではちょうど150年くらい前の日本文化への嗜好(いわゆるジャポニズム)がこれに匹敵するのだろうか。今回の一連のブームのなかでは日本を題材にした小説も結構多く書かれているようだ。最近では本国フランスでベストセラーになったといわれている「優雅なハリネズミ」(これに登場するのは映画監督小津安二郎を思わせるような日本人オズが登場しているそうだ。ぼくはまだ読んでいないが。)という小説もあるらしい。ぼくも今年にはいって日本を題材にした一冊である「さりながら」(フィリップ・フォレスト著)を読んだことがある。夏目漱石、小林一茶、山端庸介(写真家)を主人公に設定しながら、コント風仕立ての枠組みを使って単に日本への関心にとどまらずに、自身の遺児への思いと重ね合わせながら哲学的な省察(同時代への考察)を試みている、抑制の効いた佳品だったと記憶している。 今回の日本ブームはアニメやゲーム、コスプレなどの従来のポップカルチャーのみならず、寿司、禅、焼き物、茶、相撲、歌舞伎など広範な事象への関心の広がりも特徴の一つのようだ(それらが紋切り型の理解であれどうあれ、理解のためには多少の紋切り型が必要だと思う。その意味でぼくは紋切り型について好意的に考えている)。
今回の日本ブームはアニメやゲーム、コスプレなどの従来のポップカルチャーのみならず、寿司、禅、焼き物、茶、相撲、歌舞伎など広範な事象への関心の広がりも特徴の一つのようだ(それらが紋切り型の理解であれどうあれ、理解のためには多少の紋切り型が必要だと思う。その意味でぼくは紋切り型について好意的に考えている)。 そうした中で日本人気はまさにアンビバレンスななかで起こっている。だがこうした海外での日本への評価・人気というものがどれだけ正しく日本に伝えられてきたかははなはだ疑わしい。TVによる報道に限っても世界のなかのクール・ジャパンについてわりと一貫して伝えてきたのはNHKくらいで、民放からこの手の継続的な報道ニュースがあったことをぼくはほとんど知らない。それからどうも日本人の傾向として自虐的に自己分析することはあっても、他人に褒められることに素直になれない性向があるのだろうか。自分たちの良いものを海外に評価されて始めて、そんなに凄かったのかと気づかされるようなところが往々にしてあるようだ。建築の例をとっても桂離宮などがその最たる事例だろう。逆にいえば日本人は自分たちに自信がないので、いつも外部評価(海外の目)を通じてしか評価づけることができない性なのだろうか。
そうした中で日本人気はまさにアンビバレンスななかで起こっている。だがこうした海外での日本への評価・人気というものがどれだけ正しく日本に伝えられてきたかははなはだ疑わしい。TVによる報道に限っても世界のなかのクール・ジャパンについてわりと一貫して伝えてきたのはNHKくらいで、民放からこの手の継続的な報道ニュースがあったことをぼくはほとんど知らない。それからどうも日本人の傾向として自虐的に自己分析することはあっても、他人に褒められることに素直になれない性向があるのだろうか。自分たちの良いものを海外に評価されて始めて、そんなに凄かったのかと気づかされるようなところが往々にしてあるようだ。建築の例をとっても桂離宮などがその最たる事例だろう。逆にいえば日本人は自分たちに自信がないので、いつも外部評価(海外の目)を通じてしか評価づけることができない性なのだろうか。 こうしたことのチグハグさもふくめて、依然日本の本質は変わっていないのかもしれない。ただ斜陽のなかでの日本ブームについて考えるとき、ついつい思い出してしまう映画の中のことばがある。その映画というのは鈴木清順監督の「チゴイネルワイゼン」で、もう大分昔に見た映画なのでその言葉をつぶやいたのが主人公の原田芳雄だったかもはっきりとは覚えていないのだが、たしか何か果物を食べるシーンで「なんでも腐りかけが一番おいしい」とつぶやくセリフがあったことを記憶している。
こうしたことのチグハグさもふくめて、依然日本の本質は変わっていないのかもしれない。ただ斜陽のなかでの日本ブームについて考えるとき、ついつい思い出してしまう映画の中のことばがある。その映画というのは鈴木清順監督の「チゴイネルワイゼン」で、もう大分昔に見た映画なのでその言葉をつぶやいたのが主人公の原田芳雄だったかもはっきりとは覚えていないのだが、たしか何か果物を食べるシーンで「なんでも腐りかけが一番おいしい」とつぶやくセリフがあったことを記憶している。 先週の日曜日に、彼が亡くなる直前までロンドン公演向けのリハーサルに打ち込んでいたときの収録ビデオを編集した映画「This Is It」を観た。この映画を見る限り、彼がその直後に死ぬ人とはとても思えないし(とても死期の近い病人のようには見えなかった)、死の直後に言われていたような公演のリハをほとんど行っていなかったという真らしきデマが嘘だったこともよく分かる。リハーサルの様子を観るかぎり、かなり完成形に近づいていたと思うし、公演への思いも本気だったと理解できるのだ。だとすれば、死因はやはり担当主治医の処方ミスということになるのだろうか。それは分からないが、ここではMJの死因について語ることが目的ではない。それはたぶん永遠の謎かもしれない。
先週の日曜日に、彼が亡くなる直前までロンドン公演向けのリハーサルに打ち込んでいたときの収録ビデオを編集した映画「This Is It」を観た。この映画を見る限り、彼がその直後に死ぬ人とはとても思えないし(とても死期の近い病人のようには見えなかった)、死の直後に言われていたような公演のリハをほとんど行っていなかったという真らしきデマが嘘だったこともよく分かる。リハーサルの様子を観るかぎり、かなり完成形に近づいていたと思うし、公演への思いも本気だったと理解できるのだ。だとすれば、死因はやはり担当主治医の処方ミスということになるのだろうか。それは分からないが、ここではMJの死因について語ることが目的ではない。それはたぶん永遠の謎かもしれない。 今回「This Is It」を観て、改めてMJの晩年の容貌について思うのだが、今更ながらなんと年齢不詳であることかということ! とても50歳の人には見えないよね。確かに芸能人やエンターティナーを職業としている人たちが年齢不詳、アンチ・エイジングで、いわゆる普通の人の年域を超えて若く見えるのは当然だとしても、彼の場合は単にそれだけではなく筋金入りで、元々その根っこの思想としても年を取ることを拒んでいたように思えるのだ。どこか中性的な感じ、なにか少年合唱団の面影をひきずり(ジャクソン5)、合唱団を卒業した後も去勢したように声変わりせずに高音域の声を残したまま、華奢で未成熟な肢体のイメージを醸し、白でも黒でもない人種の枠を超えて、少年、児童、玩具、遊園地が大好きで・・・・・等々。スクリーンの彼はますます人間離れしていて、なにか手足の長い宇宙人のように見えたものだ。MJはその後半生において宇宙からの使者、伝道師ETのようなものになったのかもしれない。
今回「This Is It」を観て、改めてMJの晩年の容貌について思うのだが、今更ながらなんと年齢不詳であることかということ! とても50歳の人には見えないよね。確かに芸能人やエンターティナーを職業としている人たちが年齢不詳、アンチ・エイジングで、いわゆる普通の人の年域を超えて若く見えるのは当然だとしても、彼の場合は単にそれだけではなく筋金入りで、元々その根っこの思想としても年を取ることを拒んでいたように思えるのだ。どこか中性的な感じ、なにか少年合唱団の面影をひきずり(ジャクソン5)、合唱団を卒業した後も去勢したように声変わりせずに高音域の声を残したまま、華奢で未成熟な肢体のイメージを醸し、白でも黒でもない人種の枠を超えて、少年、児童、玩具、遊園地が大好きで・・・・・等々。スクリーンの彼はますます人間離れしていて、なにか手足の長い宇宙人のように見えたものだ。MJはその後半生において宇宙からの使者、伝道師ETのようなものになったのかもしれない。 そういうなかでMJの音楽ももともと深まることはなく、表層を表層のまま奏でていった。その後半に至って、ヒーリング(癒し)、地球環境へのメッセージや愛、WE ARE THE WORLDのボランタリーなどの色彩を強めて移動してゆくかのように見えても、それらは深さによったものではないし、なにか年輪の智慧によって生まれたものでもないし、どこまでも単に彼の嗜好、オタクの一環としてくらいの意味しかないだろうと思う、本当のところは。時代が下降してゆくなかにあっては音楽的には僕はむしろマドンナの方が戦略的にしたたかな感じがする。先ごろWOWOWで見たブエノスアイレスでの2008年のマドンナのツアーはよかった。ギター片手に歌うマドンナがいい。草原のなかの兵士みたいで、ジャンヌ・ダルクのようでもあり、フィジカルで、シンプルで、身体的で、・・・・、等々。
そういうなかでMJの音楽ももともと深まることはなく、表層を表層のまま奏でていった。その後半に至って、ヒーリング(癒し)、地球環境へのメッセージや愛、WE ARE THE WORLDのボランタリーなどの色彩を強めて移動してゆくかのように見えても、それらは深さによったものではないし、なにか年輪の智慧によって生まれたものでもないし、どこまでも単に彼の嗜好、オタクの一環としてくらいの意味しかないだろうと思う、本当のところは。時代が下降してゆくなかにあっては音楽的には僕はむしろマドンナの方が戦略的にしたたかな感じがする。先ごろWOWOWで見たブエノスアイレスでの2008年のマドンナのツアーはよかった。ギター片手に歌うマドンナがいい。草原のなかの兵士みたいで、ジャンヌ・ダルクのようでもあり、フィジカルで、シンプルで、身体的で、・・・・、等々。