 この間、ラジオを「ながら」で聞いていたとき、今年2009年が映画「ニュー・シネマ・パラダイス」(ジュゼッペ・トルナトーレ監督)が公開されてからちょうど20年めだということを改めて知った。これは別に大事件でもなんでもないのだが、公開年である1989年というその区切りの年号といい、ぼくにとってはなにか極めて感慨深いものがあった。もちろん当時ぼくはリアルタイムでこの映画を観た。
この間、ラジオを「ながら」で聞いていたとき、今年2009年が映画「ニュー・シネマ・パラダイス」(ジュゼッペ・トルナトーレ監督)が公開されてからちょうど20年めだということを改めて知った。これは別に大事件でもなんでもないのだが、公開年である1989年というその区切りの年号といい、ぼくにとってはなにか極めて感慨深いものがあった。もちろん当時ぼくはリアルタイムでこの映画を観た。
20年といえば成人に代表されるように人が生まれていっぱしの大人になる年数だし、経済用語でいえばキチンの波(40ヶ月)、ジュグラーの波(10年)と来てクズネッツの波(20年)を迎えるわけで、世の中の建築需要などが大きく動く年単位に相当すると言われる。
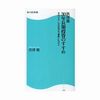 20年ではないが、「澁澤流30年長期投資のすすめ」(澁澤健著、角川SSC新書)などに見られるように長期の運用哲学が花開くことをおっしゃる方もいる。因みにこの方は明治時代の日本経済(資本主義)の礎をつくった渋沢栄一さんの5代目ご子孫だ。つまり20年という単位はなにかが大きく変わってもおかしくない単位の一つであるということ。それだけの年数を自分もすでに生きてしまったわけで、それに対する感慨がなかったといえば嘘になる。
20年ではないが、「澁澤流30年長期投資のすすめ」(澁澤健著、角川SSC新書)などに見られるように長期の運用哲学が花開くことをおっしゃる方もいる。因みにこの方は明治時代の日本経済(資本主義)の礎をつくった渋沢栄一さんの5代目ご子孫だ。つまり20年という単位はなにかが大きく変わってもおかしくない単位の一つであるということ。それだけの年数を自分もすでに生きてしまったわけで、それに対する感慨がなかったといえば嘘になる。
そして1989年という記念すべき年。この年は世界史的にはベルリンの壁崩壊があり、日本がバブル崩壊する直前の年(言わずと知れた大納会のときに付けた日経平均38,915円が歴史的ピークで、年明け以降はこれが急降下してゆくことになる)で、いわば国内海外をふくめた世の中全般が大きく変動してゆく前年にあたっている。
ニュー・シネマ・パラダイスはわざわざ説明するまでもないくらい人口に膾炙している映画で、映画史上では名作中の名作と呼ばれる類の作品。何がしかのランキング投票を行えば必ずベスト10位入りすることは間違いないだろう。あまりにも有名なエンニオ・モリコーネのサウンドトラック(旋律)もどこかで必ず聴いているはずだ。
 ぼくが最初この映画に感動したのは、これもまたあまりにも有名なラストの古い映画のキスシーンの数珠つながりのシーンだ。洗礼の水でも浴びるようなフィルムの切れはしたちの映像の連鎖。検閲にひっかからないようにフィリップ・ノワレ演じる映写技師アルフレードがそれらのフィルムを切り刻んでいたわけだが、その「記念品(形見)」を主人公が上映してながめるシーン。ここには過ぎた時への回想とともに、トルナトーレ監督自身による古き映画への紛れもないオマージュもあったはずだ。
ぼくが最初この映画に感動したのは、これもまたあまりにも有名なラストの古い映画のキスシーンの数珠つながりのシーンだ。洗礼の水でも浴びるようなフィルムの切れはしたちの映像の連鎖。検閲にひっかからないようにフィリップ・ノワレ演じる映写技師アルフレードがそれらのフィルムを切り刻んでいたわけだが、その「記念品(形見)」を主人公が上映してながめるシーン。ここには過ぎた時への回想とともに、トルナトーレ監督自身による古き映画への紛れもないオマージュもあったはずだ。
映画は生き物であり、おそらくその時々によって何に感動するのか、その印象も確実に変わってゆく。ぼくにとってのニュー・シネマ・パラダイスもその意味では変化し続ける作品なのかもしれないが、今もあらためて惹かれている部分があるとしたら、それはたぶんこの映画がノスタルジーに貫かれた追想の視点で描かれていることだ。主人公の幼年時代への、町をとりまく環境への、高校時代の恋人への、その別れへの、親しい友人への、なによりも大好きだった映画館への、そうした失われたものたちへの、追想のオマージュ。
 そして映画の最後のほうで、アルフレードの死の知らせをうけて故郷へ帰る決心をした主人公はなにかと和解し(過去と現在に連なる時間と?)、その葬式参列の日にかつての知人たちの多くの顔に出会う。そこに見いだされるのは、時が確実に刻みつけた人々の顔の変化であり、それと同じだけ主人公も年を重ねたという事実、そしてそれらがある懐かしさをともなって現れてくるのだ。ちょうどプルーストが「失われた時を求めて」における最終巻の「見出された時」の仮装パーティーで「時」の交差と出会ったかのように?・・・・。
そして映画の最後のほうで、アルフレードの死の知らせをうけて故郷へ帰る決心をした主人公はなにかと和解し(過去と現在に連なる時間と?)、その葬式参列の日にかつての知人たちの多くの顔に出会う。そこに見いだされるのは、時が確実に刻みつけた人々の顔の変化であり、それと同じだけ主人公も年を重ねたという事実、そしてそれらがある懐かしさをともなって現れてくるのだ。ちょうどプルーストが「失われた時を求めて」における最終巻の「見出された時」の仮装パーティーで「時」の交差と出会ったかのように?・・・・。
1989年のバブル崩壊のあとの、日本の20年。失われた10年とも20年とも言われる、その長いだらだら坂の低迷。この間の最初の10年でみても、単に経済情勢の激しい変化だけではなく、オウム事件や阪神大震災に代表される大きな社会的な事件や天変地異があった。次の10年でみても不景気なのに異常なくらいのラッシュとなった都市の大規模再開発(六本木、汐留、丸の内)など、とても変化の激しいDecadeだったと言える。そのあまりにも振幅が大きいために誰も正確に語れないような時代。そして今、ぼくたちはニュー・シネマ・パラダイスの主人公と同じように、その日本の周辺のあちこちに、それこそ制度疲労のためかすっかり「老いた」日本の多くの顔たちとその残像に出会っている。
 21世紀を前にしてその最後の10年の手前で公開されたニュー・シネマ・パラダイスは、そう思えば予見的な映画だったのかもしれない。それは華やかな未来よりもどこか追憶の過去にひきよせられ、新しさよりも追憶のさざ波に揺れているような映画だからだが、それこそまさに現代の風景そのものにも思える。現代において新しいものはまだあるのか? あるのは追憶だけなのか? 失われた過去への記憶だけなのか? 果たして、ぼくらはこの老いた日本の再生の果てに、ニュー・パラダイスを見ることができるだろうか?
21世紀を前にしてその最後の10年の手前で公開されたニュー・シネマ・パラダイスは、そう思えば予見的な映画だったのかもしれない。それは華やかな未来よりもどこか追憶の過去にひきよせられ、新しさよりも追憶のさざ波に揺れているような映画だからだが、それこそまさに現代の風景そのものにも思える。現代において新しいものはまだあるのか? あるのは追憶だけなのか? 失われた過去への記憶だけなのか? 果たして、ぼくらはこの老いた日本の再生の果てに、ニュー・パラダイスを見ることができるだろうか?
よしむね
関連エントリー
2009.12.18・・・ぼくらは両極の映画の佳品「サイドウェイズ」と「アンナと過ごした4日間」の間で揺れ動くのだ
2009.12.16・・・「世界カワイイ革命」と日本ブームについて思う
2009.12.09・・・箱根のリゾートSPAでつくづく時間という買い物について想ったこと
2009.12.04・・・「なんでも腐りかけがおいしい」という斜陽のなかでの日本ブーム
2009.11.27・・・たしかにガラパゴス化した国で皆が子泣き爺になっているようだ
2009.11.17・・・大江戸温泉の無国籍化でブレードランナーのことなどを思いながらわしも考えた
2009.11.05・・・MJは後半生において宇宙からの使者、伝道師ETのようなものになったのではないか
 「サイドウェイズ」は2004年同名のハリウッド映画のリメイク版。監督は外国人のチェリン・グラック。主演陣は日本人の俳優で小日向文世、生瀬勝久、鈴木京香、菊池凛子の4名。まず役者たちの顔ぶれが良い。物語は解説文をそのまま使わせてもらうと、「ワインの産地、カリフォルニアのナパ・バレーを舞台に、さえない40代の男二人のパッとしない人生が少しずつ動き出していく様をていねいに描く」とある。まあたしかにそのように動いてゆく。そこに同世代といってよい二人の女たち(鈴木京香と菊池凛子)が絡む。
「サイドウェイズ」は2004年同名のハリウッド映画のリメイク版。監督は外国人のチェリン・グラック。主演陣は日本人の俳優で小日向文世、生瀬勝久、鈴木京香、菊池凛子の4名。まず役者たちの顔ぶれが良い。物語は解説文をそのまま使わせてもらうと、「ワインの産地、カリフォルニアのナパ・バレーを舞台に、さえない40代の男二人のパッとしない人生が少しずつ動き出していく様をていねいに描く」とある。まあたしかにそのように動いてゆく。そこに同世代といってよい二人の女たち(鈴木京香と菊池凛子)が絡む。 一方の「アンナと過ごした4日間」はこれとは対蹠的にまったく異常さに基づくような内容になっている。監督はポーランドのイエジー・スコリモフスキー。現代世界の特徴のひとつが等質性にあるとすれば、この映画はそのすべてにおいてこれと反対を行くような設定だ。主人公は病院の火葬場で働くまったく冴えない寡黙な独身男。年老いた祖母との二人暮しだが、ほとんど引きこもりのような二人の生活。やがて祖母の死。そして異常なレイプ事件を目撃。主人公自身も過去に異常な暴力事件(?)に遭った過去を持つ。
一方の「アンナと過ごした4日間」はこれとは対蹠的にまったく異常さに基づくような内容になっている。監督はポーランドのイエジー・スコリモフスキー。現代世界の特徴のひとつが等質性にあるとすれば、この映画はそのすべてにおいてこれと反対を行くような設定だ。主人公は病院の火葬場で働くまったく冴えない寡黙な独身男。年老いた祖母との二人暮しだが、ほとんど引きこもりのような二人の生活。やがて祖母の死。そして異常なレイプ事件を目撃。主人公自身も過去に異常な暴力事件(?)に遭った過去を持つ。 櫻井孝昌さんの「
櫻井孝昌さんの「 一例を挙げるなら、韓国の企業で三星電子だったと思うが、世界のある市場に製品を売る前に、ある人材を送り込んで一年間まったく自由に過ごさせることで現地に溶け込ませ、その国の文化に始まり何から何まですべてを吸収させて、その現地にあった市場戦略(販売戦略)を考えさせるという研修員プランがあるという。ここまで時間をかけて相手の国のことを研究することを日本企業(=人)はやっているだろうか。そこまで相手のことを見ようとしているとは思えない。
一例を挙げるなら、韓国の企業で三星電子だったと思うが、世界のある市場に製品を売る前に、ある人材を送り込んで一年間まったく自由に過ごさせることで現地に溶け込ませ、その国の文化に始まり何から何まですべてを吸収させて、その現地にあった市場戦略(販売戦略)を考えさせるという研修員プランがあるという。ここまで時間をかけて相手の国のことを研究することを日本企業(=人)はやっているだろうか。そこまで相手のことを見ようとしているとは思えない。 戦後、焼け野原だけが残ったといわれる(もちろん戦後生まれのぼくはその焼け野原を知らない)。バブル崩壊後現在(=いま)に連綿と続く原風景も多くの日本人にとってどこか焼け野原に近いイメージを抱かせるものなのかもしれない。頼るもののない、荒れた土地。瓦礫の街。そうしたなかで、世界中の女の子だけが能動的な生き方として「カワイくなりたい。カワイく生きたい」と願いそれを実践している。人はそれを安易にロリータファッションとのみ定義づけ括ろうとして安心しようとしたりするのかもしれないが。でもこの女の子たちの感性パワーは今を生きることをめぐる結構ほんものの呼び声や価値観に近いなにかなのかもしれないとぼくは思う。
戦後、焼け野原だけが残ったといわれる(もちろん戦後生まれのぼくはその焼け野原を知らない)。バブル崩壊後現在(=いま)に連綿と続く原風景も多くの日本人にとってどこか焼け野原に近いイメージを抱かせるものなのかもしれない。頼るもののない、荒れた土地。瓦礫の街。そうしたなかで、世界中の女の子だけが能動的な生き方として「カワイくなりたい。カワイく生きたい」と願いそれを実践している。人はそれを安易にロリータファッションとのみ定義づけ括ろうとして安心しようとしたりするのかもしれないが。でもこの女の子たちの感性パワーは今を生きることをめぐる結構ほんものの呼び声や価値観に近いなにかなのかもしれないとぼくは思う。 先々週末、箱根の某リゾートホテルに家内と一緒に宿泊に出かけた。ぼくの目的はリハビリを兼ねて温泉に浸かること、家内は以前から行ってみたいホテルだったらしいが、結果としてはアロマトリートメントを施術してもらい大いにリラクシングできてご満悦だったようである。因みに彼女自身も自宅でアロマを施術しているアロマセラピストである。ぼくにとっては大江戸温泉通いの延長としての温泉療養の意味合いもあった。そこは強羅温泉のエリアなので温泉の質も格段によかった。
先々週末、箱根の某リゾートホテルに家内と一緒に宿泊に出かけた。ぼくの目的はリハビリを兼ねて温泉に浸かること、家内は以前から行ってみたいホテルだったらしいが、結果としてはアロマトリートメントを施術してもらい大いにリラクシングできてご満悦だったようである。因みに彼女自身も自宅でアロマを施術しているアロマセラピストである。ぼくにとっては大江戸温泉通いの延長としての温泉療養の意味合いもあった。そこは強羅温泉のエリアなので温泉の質も格段によかった。 それから、吹き抜けのリビングフロアーの天井から長い筒のような煙突が下がっていて、その下に薪がくべられた暖炉があり、その爆ぜる音を聞きながらゆったりできることもとてもよかった。ふつう暖炉といえば部屋の隅のほうにあるものだろうが、そこではちょうどフロアーの真ん中に位置するように暖炉が設計されており、寛ぎにきた人たちが取り囲むようにしてその暖炉の火を眺めることになるのだ。グラスを一杯傾けながら、いつまでも飽きることなくその火を眺めながら談笑している泊り客のすがたも絶えなかった。こうした何でもないような設計にみえて、客本位への気配りといい、寛ぎを演出するその意匠の心づくしといい、やはり上質であったといえるだろう。
それから、吹き抜けのリビングフロアーの天井から長い筒のような煙突が下がっていて、その下に薪がくべられた暖炉があり、その爆ぜる音を聞きながらゆったりできることもとてもよかった。ふつう暖炉といえば部屋の隅のほうにあるものだろうが、そこではちょうどフロアーの真ん中に位置するように暖炉が設計されており、寛ぎにきた人たちが取り囲むようにしてその暖炉の火を眺めることになるのだ。グラスを一杯傾けながら、いつまでも飽きることなくその火を眺めながら談笑している泊り客のすがたも絶えなかった。こうした何でもないような設計にみえて、客本位への気配りといい、寛ぎを演出するその意匠の心づくしといい、やはり上質であったといえるだろう。 まさむねさんが{「ここはウソで固めた世界でありんす」とは僕らの台詞だ}のなかで語っているように、「世界に対する違和感、それは現代人に特有の感覚なのだろうか。それは、本当の自分はどこか別の場所に居るべきであり、今、ここに存在するのはウソの自分だという感覚」だけがたしかなものなのかもしれない。だとするなら、そうした不確かさのなかでヒトはより確からしいなにかにスガルしかない。それが唯一根っこのような時間というものなのだろうか。
まさむねさんが{「ここはウソで固めた世界でありんす」とは僕らの台詞だ}のなかで語っているように、「世界に対する違和感、それは現代人に特有の感覚なのだろうか。それは、本当の自分はどこか別の場所に居るべきであり、今、ここに存在するのはウソの自分だという感覚」だけがたしかなものなのかもしれない。だとするなら、そうした不確かさのなかでヒトはより確からしいなにかにスガルしかない。それが唯一根っこのような時間というものなのだろうか。 雑誌記事などによるとフランスで空前の日本ブームだという。空前というのがどの程度なのかよく分からないが、同じように日本ブームという意味ではちょうど150年くらい前の日本文化への嗜好(いわゆるジャポニズム)がこれに匹敵するのだろうか。今回の一連のブームのなかでは日本を題材にした小説も結構多く書かれているようだ。最近では本国フランスでベストセラーになったといわれている「優雅なハリネズミ」(これに登場するのは映画監督小津安二郎を思わせるような日本人オズが登場しているそうだ。ぼくはまだ読んでいないが。)という小説もあるらしい。ぼくも今年にはいって日本を題材にした一冊である「さりながら」(フィリップ・フォレスト著)を読んだことがある。夏目漱石、小林一茶、山端庸介(写真家)を主人公に設定しながら、コント風仕立ての枠組みを使って単に日本への関心にとどまらずに、自身の遺児への思いと重ね合わせながら哲学的な省察(同時代への考察)を試みている、抑制の効いた佳品だったと記憶している。
雑誌記事などによるとフランスで空前の日本ブームだという。空前というのがどの程度なのかよく分からないが、同じように日本ブームという意味ではちょうど150年くらい前の日本文化への嗜好(いわゆるジャポニズム)がこれに匹敵するのだろうか。今回の一連のブームのなかでは日本を題材にした小説も結構多く書かれているようだ。最近では本国フランスでベストセラーになったといわれている「優雅なハリネズミ」(これに登場するのは映画監督小津安二郎を思わせるような日本人オズが登場しているそうだ。ぼくはまだ読んでいないが。)という小説もあるらしい。ぼくも今年にはいって日本を題材にした一冊である「さりながら」(フィリップ・フォレスト著)を読んだことがある。夏目漱石、小林一茶、山端庸介(写真家)を主人公に設定しながら、コント風仕立ての枠組みを使って単に日本への関心にとどまらずに、自身の遺児への思いと重ね合わせながら哲学的な省察(同時代への考察)を試みている、抑制の効いた佳品だったと記憶している。 今回の日本ブームはアニメやゲーム、コスプレなどの従来のポップカルチャーのみならず、寿司、禅、焼き物、茶、相撲、歌舞伎など広範な事象への関心の広がりも特徴の一つのようだ(それらが紋切り型の理解であれどうあれ、理解のためには多少の紋切り型が必要だと思う。その意味でぼくは紋切り型について好意的に考えている)。
今回の日本ブームはアニメやゲーム、コスプレなどの従来のポップカルチャーのみならず、寿司、禅、焼き物、茶、相撲、歌舞伎など広範な事象への関心の広がりも特徴の一つのようだ(それらが紋切り型の理解であれどうあれ、理解のためには多少の紋切り型が必要だと思う。その意味でぼくは紋切り型について好意的に考えている)。 そうした中で日本人気はまさにアンビバレンスななかで起こっている。だがこうした海外での日本への評価・人気というものがどれだけ正しく日本に伝えられてきたかははなはだ疑わしい。TVによる報道に限っても世界のなかのクール・ジャパンについてわりと一貫して伝えてきたのはNHKくらいで、民放からこの手の継続的な報道ニュースがあったことをぼくはほとんど知らない。それからどうも日本人の傾向として自虐的に自己分析することはあっても、他人に褒められることに素直になれない性向があるのだろうか。自分たちの良いものを海外に評価されて始めて、そんなに凄かったのかと気づかされるようなところが往々にしてあるようだ。建築の例をとっても桂離宮などがその最たる事例だろう。逆にいえば日本人は自分たちに自信がないので、いつも外部評価(海外の目)を通じてしか評価づけることができない性なのだろうか。
そうした中で日本人気はまさにアンビバレンスななかで起こっている。だがこうした海外での日本への評価・人気というものがどれだけ正しく日本に伝えられてきたかははなはだ疑わしい。TVによる報道に限っても世界のなかのクール・ジャパンについてわりと一貫して伝えてきたのはNHKくらいで、民放からこの手の継続的な報道ニュースがあったことをぼくはほとんど知らない。それからどうも日本人の傾向として自虐的に自己分析することはあっても、他人に褒められることに素直になれない性向があるのだろうか。自分たちの良いものを海外に評価されて始めて、そんなに凄かったのかと気づかされるようなところが往々にしてあるようだ。建築の例をとっても桂離宮などがその最たる事例だろう。逆にいえば日本人は自分たちに自信がないので、いつも外部評価(海外の目)を通じてしか評価づけることができない性なのだろうか。 こうしたことのチグハグさもふくめて、依然日本の本質は変わっていないのかもしれない。ただ斜陽のなかでの日本ブームについて考えるとき、ついつい思い出してしまう映画の中のことばがある。その映画というのは鈴木清順監督の「チゴイネルワイゼン」で、もう大分昔に見た映画なのでその言葉をつぶやいたのが主人公の原田芳雄だったかもはっきりとは覚えていないのだが、たしか何か果物を食べるシーンで「なんでも腐りかけが一番おいしい」とつぶやくセリフがあったことを記憶している。
こうしたことのチグハグさもふくめて、依然日本の本質は変わっていないのかもしれない。ただ斜陽のなかでの日本ブームについて考えるとき、ついつい思い出してしまう映画の中のことばがある。その映画というのは鈴木清順監督の「チゴイネルワイゼン」で、もう大分昔に見た映画なのでその言葉をつぶやいたのが主人公の原田芳雄だったかもはっきりとは覚えていないのだが、たしか何か果物を食べるシーンで「なんでも腐りかけが一番おいしい」とつぶやくセリフがあったことを記憶している。