最近たまたま読んだ三冊について、以下にその感想を書きます。いずれも「これから」を考える上でのヒントのひとつになるような本かな、と。その意味で三者三様、いずれもマイナーではありますが、ひとりひとりの傾斜角での視点に基づく、「三斜・三様」の本たちだと思います。あえてここで強引に内容を共通化して言ってみると、従来の「持てるもの」の時代が終わりを迎え、これからはいかに持たないで生きてゆくか、その工夫が鍵になる、ということでしょうか。
「オーガニック革命」(集英社新書、 高城剛)」
 高城さんの主張は一貫している。まずここで言うオーガニックとは、単に有機農業などへの食品嗜好を意味するのではなく、もっと広く「個人の意識のあり方や態度から発信される行動様式」と定義。そして市場万能主義と金融グローバリゼーションが崩れたいわゆるリーマンショック以後を見据えて、効率化モデル・アメリカ的価値観の終わりの後に来るものとして、オーガニックのムーブメントを位置づけている。それを自身が住んでいたロンドンの先駆事例に基づきながら紹介している。
高城さんの主張は一貫している。まずここで言うオーガニックとは、単に有機農業などへの食品嗜好を意味するのではなく、もっと広く「個人の意識のあり方や態度から発信される行動様式」と定義。そして市場万能主義と金融グローバリゼーションが崩れたいわゆるリーマンショック以後を見据えて、効率化モデル・アメリカ的価値観の終わりの後に来るものとして、オーガニックのムーブメントを位置づけている。それを自身が住んでいたロンドンの先駆事例に基づきながら紹介している。
「次」に向けて、ロンドンが、世界がもう変わり始めている、と。そして、このオーガニックには「行き過ぎた資本主義へのアンチテーゼがある」のだ、と。以下、面白そうな論点。
・これからは、働く場所(第一の土地)、住む家(第二の土地)以外の第三の土地をいかに発見するか、である
・できるだけモノを持たないのが21世紀的発想になる
・都市システムを解体することが、21世紀的な行為になるのではないか、等々
またこれは高城さんが以前から書いていることとも符合していると思われるが、「フラット化する世界」(トーマス・フリードマン著)に留まらず、これからはますます世界がリキッド化(液状化)に向かうとして、その中で自らより強く「ハイパー・ノマド(遊牧民」として生きてゆくことを宣言してもいる。高城さんの視点は、先の著書「サバイバル時代の海外旅行術」(光文社新書)にも代表されるように、変化が激しく見通しにくいこの時代を漂流してゆきつついかにサバイブしてゆくかに主眼があるともいえるだろう。
「2011年新聞・テレビ消滅」(文春新書、佐々木俊尚)」
 タイトルからはややショッキングに思えるかもしれないが、佐々木さんの主張も決して大げさなものではなく、ある必然をもって新聞とテレビという既存メディアがこれから確実に衰退に向かうことを描写してゆく。その基調にあるのは、従来前提とされていたマスメディアが明確に終焉を迎えつつある、というある意味でオーソドックスな時代認識だ。
タイトルからはややショッキングに思えるかもしれないが、佐々木さんの主張も決して大げさなものではなく、ある必然をもって新聞とテレビという既存メディアがこれから確実に衰退に向かうことを描写してゆく。その基調にあるのは、従来前提とされていたマスメディアが明確に終焉を迎えつつある、というある意味でオーソドックスな時代認識だ。
そして、メディアの流れ(流通)を、コンテンツ・コンテナ・コンベヤという三層モデルで考えた場合、従来のメディアは垂直統合でこの三層を押さえていたのだが、ネットビジネスの登場等でそのモデルが完全に崩れつつあり、次の時代の覇者は、コンテナなどのプラットホームを握るものにこそ優位権があるという考え方。
そのような近未来的なプラットホーム争いのなかで、キンドルのアマゾンやユーチューブ、グーグル、アップル、リクルートなどの新興企業の登場と戦略が併行して語られてゆくのだが、上記の考え方もふくめてベースとなるものは古典的な見方にそったものだ。
これはしばしば言われたことだが、過去の歴史において最終的に石油の利権を制したのは、石油の採掘権を握った者たちではなく、その石油を輸送する手段(その当時は鉄道)を握ったロックフェラーたちだったという事実。つまりいくら石油が取れても、運ぶことができなければ石油もただの水以下だということ。
大事なのは昔も今も運ぶ手段網(流通経路の根幹となるネットワーク)にあるのだ、ということ。佐々木さんの考えもある意味でそのような考え方を忠実に踏襲しているといえるだろう。そして2011年に行われる完全地デジ化と情報通信法の施行が、日本の新聞社とテレビ局に対して従来の権益モデルをつき崩す決定的なトリガー(引き金)になると見ているのだ。
「未来のための江戸学」(小学館101新書、 田中優子)」
 著名な江戸学者によって、時事風の主題をまじえながら、江戸時代からこの今を考えるということ、現代が江戸の優れていた点とどんな風に交差することが可能かを未来の視点から考えようとしている、と言ったらよいだろうか。
著名な江戸学者によって、時事風の主題をまじえながら、江戸時代からこの今を考えるということ、現代が江戸の優れていた点とどんな風に交差することが可能かを未来の視点から考えようとしている、と言ったらよいだろうか。
ぼくは日本の歴史に明るくなく大した知識など持っているとは言えないのだが、このような著書を読むと、過去の歴史というものを今の視点で括ってしまってなんとなく分かった気になっていることが往々にしてありはしないか、反省させられるような気がする。本当の歴史とは今ぼくらが聞いて知っていたものとはおよそまったく異なるかたちだったのではないかというようなことだ。
以下に、田中さんのフィルターを通した指摘の幾つかを示してみる。江戸時代とはどんな時代だったのか。
・江戸時代の職人たちは、100年や200年ももつ道具や建築物や紙や布を作ることを誇りにしていた
・江戸時代の商人倫理は過剰な利ざやを稼がないことが、信用を得ることだった
・江戸時代の森林伐採の禁止は、環境保全と経済成長を両立させようなどというむしのいい発想ではなく、むしろ「すたり」(無駄)をなくすことによって、健全なサイクルを作り、誰もが貧困状態にならないよう世の中を経営するという考え方に基づいていた
・江戸時代には、「始末」という考え方があり、これは始まりと終わりをきちんとして循環が滞らないようにすることだった
・江戸時代の「経済」という言葉は、国土を経営し、物産を開発し、都内を富豊にし、万民を済救するという意味であった
・安藤広重の「名所江戸百景」によると、江戸という都市が単に活気に満ちた騒がしいところなのではなく、静かでゆったりして、実にのびのびとした空間であったことがありありとわかる
・縄文時代後期から始まって江戸時代中期に完成した水の管理システムは、本来は至るところ急流になっている日本の川を制御して、降った雨が大地のすみずみまで滲みこんで潤しながら、むしろゆっくり流れるようにすることだった
これなどは正にダム建設中心で推移してきた日本の治水システムを見直そうとしている昨今の民主党の施策のずっと先を行っていたようなものとも言えるだろう。また江戸のゆったり感というのも、当時今のような高い建物などがなく、いろんな場所から富士山を見ることができたことを想うと、江戸が水の都市と呼ばれ、かつ視界がひろびろとしていたことが当たり前のようにまざまざと想像できるように思える。さらによく言われる鎖国というものが実は後で作られた言葉に過ぎず、鎖国によって国を閉ざしていたわけではなく、今でいうグローバル化のなかで選択された施策であったことなども田中さんの論点によって明らかにされてゆく。そして「分」をわきまえ、配慮と節度で対応していた江戸時代の人たちの心構えのようなもの、人との関係としての「框」の構造の意味、等々。
別に江戸時代の昔に返ればよいということではないし、古の昔が良かったというわけではない。ただ未だに成長神話に頼らずには生きていけないような、一本調子の基調のみを求めたがる現在の風潮に対して、江戸時代が持っていた「循環(めぐること)」の価値観に基づく考え方には、どこか一筋縄では行かない奥行きの深さを感じずにはいられないし、今を生きるヒントの一つとなり得る示唆に満ちているようにも思えるのだ。
いずれにしても、戦略ということを含めて、何を持ち、何を持たないか、その取捨がこれからとても大事になるように思える、そういうことを示唆してくれた三冊だった。
よしむね
 著者の佐々木俊尚氏は過去に「電子書籍の衝撃」(ディスカヴァー携書)や「グーグル」(文春新書)などでも時代の先端を読み解く作業をされてきたが、本書「キュレーションの時代」(ちくま新書)ではそうした一連の流れをうけてこれからの未来社会へ向けたより突っ込んだご自身の考えを披瀝しているようにも思う。一個一個の時代の先端の読み解きも面白いが、ここでは筋立てて細かには紹介しない。ぜひご一読いただければ。
著者の佐々木俊尚氏は過去に「電子書籍の衝撃」(ディスカヴァー携書)や「グーグル」(文春新書)などでも時代の先端を読み解く作業をされてきたが、本書「キュレーションの時代」(ちくま新書)ではそうした一連の流れをうけてこれからの未来社会へ向けたより突っ込んだご自身の考えを披瀝しているようにも思う。一個一個の時代の先端の読み解きも面白いが、ここでは筋立てて細かには紹介しない。ぜひご一読いただければ。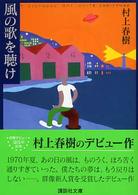 その時代とは特に80年代前半からバブル期の全盛前夜辺りまでとなる。「ノルウェイの森」が出版されたのは1987年で、「風の歌を聴け」が1979年に群像に掲載されたので、この間ほぼ10年近く、ぼくはずっと村上春樹の小説をリアルタイムで読んでいた。
その時代とは特に80年代前半からバブル期の全盛前夜辺りまでとなる。「ノルウェイの森」が出版されたのは1987年で、「風の歌を聴け」が1979年に群像に掲載されたので、この間ほぼ10年近く、ぼくはずっと村上春樹の小説をリアルタイムで読んでいた。 けれど、そのことによって僕にとっては村上さんの小説がリアルなものではなくなったのだ。なによりも物語になりきれないその不全さを愛していたのだから、たぶん。「羊をめぐる冒険」も「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も然りだった。
けれど、そのことによって僕にとっては村上さんの小説がリアルなものではなくなったのだ。なによりも物語になりきれないその不全さを愛していたのだから、たぶん。「羊をめぐる冒険」も「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も然りだった。 最後に、先のコメントで、ぼくは村上さんの小説には本当の意味で他者性がないかもしれないとも書いた。同じキャラクターの分身の物語ではないか、とも。じゃ、ぼくが感じる他者性のある小説とは何か。それはたとえば島尾敏雄さんが書いた「死の棘」という小説だ。ずっと昔に読んだのでもう細かいあらすじはすっかり忘れてしまっているけど、要は浮気をした主人公のおかげで気が変になってしまった(なりかかった)奥さんと、それにとことん付きあい付き添ってゆくしかない男の話。しまいには主人公の男も気が変になりかかるような、ふたりがふたりで病んでゆくような、どちらが快癒してゆくか分からないような、そんな決して切り分けることのできない現実のなかで生き延びてゆく日々を書き続けたもの。その不分明さ。そういうものこそ実は本当の他者性ではないかと最近のぼくは思っている。
最後に、先のコメントで、ぼくは村上さんの小説には本当の意味で他者性がないかもしれないとも書いた。同じキャラクターの分身の物語ではないか、とも。じゃ、ぼくが感じる他者性のある小説とは何か。それはたとえば島尾敏雄さんが書いた「死の棘」という小説だ。ずっと昔に読んだのでもう細かいあらすじはすっかり忘れてしまっているけど、要は浮気をした主人公のおかげで気が変になってしまった(なりかかった)奥さんと、それにとことん付きあい付き添ってゆくしかない男の話。しまいには主人公の男も気が変になりかかるような、ふたりがふたりで病んでゆくような、どちらが快癒してゆくか分からないような、そんな決して切り分けることのできない現実のなかで生き延びてゆく日々を書き続けたもの。その不分明さ。そういうものこそ実は本当の他者性ではないかと最近のぼくは思っている。
 だが、はたしてそうなのだろうか。それよりも論調以前の対応として、上記のような金融に翻弄された結果として当たり前の辛く厳しい生活の実態や事実をまず継続的に報道することからすべては始まるのではないか。そうした事実の提供を受けてそのあとどう考えるかは各自の自由だ。
だが、はたしてそうなのだろうか。それよりも論調以前の対応として、上記のような金融に翻弄された結果として当たり前の辛く厳しい生活の実態や事実をまず継続的に報道することからすべては始まるのではないか。そうした事実の提供を受けてそのあとどう考えるかは各自の自由だ。
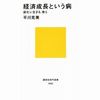 平川克美さんという現役の社長さんが書かれた本で講談社現代新書の一冊。この方はたしかフランス文学者の内田樹さんの小学校時代からのご友人だそう。内田さんとは共著で本を書かれているらしいが、ぼくは初めてこの方の本を読んだ。
平川克美さんという現役の社長さんが書かれた本で講談社現代新書の一冊。この方はたしかフランス文学者の内田樹さんの小学校時代からのご友人だそう。内田さんとは共著で本を書かれているらしいが、ぼくは初めてこの方の本を読んだ。 高城さんの主張は一貫している。まずここで言うオーガニックとは、単に有機農業などへの食品嗜好を意味するのではなく、もっと広く「個人の意識のあり方や態度から発信される行動様式」と定義。そして市場万能主義と金融グローバリゼーションが崩れたいわゆるリーマンショック以後を見据えて、効率化モデル・アメリカ的価値観の終わりの後に来るものとして、オーガニックのムーブメントを位置づけている。それを自身が住んでいたロンドンの先駆事例に基づきながら紹介している。
高城さんの主張は一貫している。まずここで言うオーガニックとは、単に有機農業などへの食品嗜好を意味するのではなく、もっと広く「個人の意識のあり方や態度から発信される行動様式」と定義。そして市場万能主義と金融グローバリゼーションが崩れたいわゆるリーマンショック以後を見据えて、効率化モデル・アメリカ的価値観の終わりの後に来るものとして、オーガニックのムーブメントを位置づけている。それを自身が住んでいたロンドンの先駆事例に基づきながら紹介している。 タイトルからはややショッキングに思えるかもしれないが、佐々木さんの主張も決して大げさなものではなく、ある必然をもって新聞とテレビという既存メディアがこれから確実に衰退に向かうことを描写してゆく。その基調にあるのは、従来前提とされていたマスメディアが明確に終焉を迎えつつある、というある意味でオーソドックスな時代認識だ。
タイトルからはややショッキングに思えるかもしれないが、佐々木さんの主張も決して大げさなものではなく、ある必然をもって新聞とテレビという既存メディアがこれから確実に衰退に向かうことを描写してゆく。その基調にあるのは、従来前提とされていたマスメディアが明確に終焉を迎えつつある、というある意味でオーソドックスな時代認識だ。 著名な江戸学者によって、時事風の主題をまじえながら、江戸時代からこの今を考えるということ、現代が江戸の優れていた点とどんな風に交差することが可能かを未来の視点から考えようとしている、と言ったらよいだろうか。
著名な江戸学者によって、時事風の主題をまじえながら、江戸時代からこの今を考えるということ、現代が江戸の優れていた点とどんな風に交差することが可能かを未来の視点から考えようとしている、と言ったらよいだろうか。 櫻井孝昌さんの「
櫻井孝昌さんの「 一例を挙げるなら、韓国の企業で三星電子だったと思うが、世界のある市場に製品を売る前に、ある人材を送り込んで一年間まったく自由に過ごさせることで現地に溶け込ませ、その国の文化に始まり何から何まですべてを吸収させて、その現地にあった市場戦略(販売戦略)を考えさせるという研修員プランがあるという。ここまで時間をかけて相手の国のことを研究することを日本企業(=人)はやっているだろうか。そこまで相手のことを見ようとしているとは思えない。
一例を挙げるなら、韓国の企業で三星電子だったと思うが、世界のある市場に製品を売る前に、ある人材を送り込んで一年間まったく自由に過ごさせることで現地に溶け込ませ、その国の文化に始まり何から何まですべてを吸収させて、その現地にあった市場戦略(販売戦略)を考えさせるという研修員プランがあるという。ここまで時間をかけて相手の国のことを研究することを日本企業(=人)はやっているだろうか。そこまで相手のことを見ようとしているとは思えない。 戦後、焼け野原だけが残ったといわれる(もちろん戦後生まれのぼくはその焼け野原を知らない)。バブル崩壊後現在(=いま)に連綿と続く原風景も多くの日本人にとってどこか焼け野原に近いイメージを抱かせるものなのかもしれない。頼るもののない、荒れた土地。瓦礫の街。そうしたなかで、世界中の女の子だけが能動的な生き方として「カワイくなりたい。カワイく生きたい」と願いそれを実践している。人はそれを安易にロリータファッションとのみ定義づけ括ろうとして安心しようとしたりするのかもしれないが。でもこの女の子たちの感性パワーは今を生きることをめぐる結構ほんものの呼び声や価値観に近いなにかなのかもしれないとぼくは思う。
戦後、焼け野原だけが残ったといわれる(もちろん戦後生まれのぼくはその焼け野原を知らない)。バブル崩壊後現在(=いま)に連綿と続く原風景も多くの日本人にとってどこか焼け野原に近いイメージを抱かせるものなのかもしれない。頼るもののない、荒れた土地。瓦礫の街。そうしたなかで、世界中の女の子だけが能動的な生き方として「カワイくなりたい。カワイく生きたい」と願いそれを実践している。人はそれを安易にロリータファッションとのみ定義づけ括ろうとして安心しようとしたりするのかもしれないが。でもこの女の子たちの感性パワーは今を生きることをめぐる結構ほんものの呼び声や価値観に近いなにかなのかもしれないとぼくは思う。