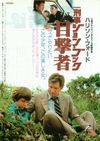 当時この映画が話題になったのは、今もアメリカに現存しているアーミッシュという自給自足の社会(ドイツ系アメリカ人の村社会)が取り上げられていたという物珍しさも多少あったと思う。そこに適度なサスペンスと恋愛ドラマ。今みてもよくできた映画だ。いろんな要素を持っているのでさまざまな切り口の考察が可能だと思われるのだが、ここでは共同体と個人ということに絞りたい。ふたつの共同体が舞台。ひとつは無法もふくめて刑事が所属する社会。もうひとつは上記アーミッシュという共同体。
当時この映画が話題になったのは、今もアメリカに現存しているアーミッシュという自給自足の社会(ドイツ系アメリカ人の村社会)が取り上げられていたという物珍しさも多少あったと思う。そこに適度なサスペンスと恋愛ドラマ。今みてもよくできた映画だ。いろんな要素を持っているのでさまざまな切り口の考察が可能だと思われるのだが、ここでは共同体と個人ということに絞りたい。ふたつの共同体が舞台。ひとつは無法もふくめて刑事が所属する社会。もうひとつは上記アーミッシュという共同体。
そして刑事ジョン・ブック(ハリソン・フォード)とレイチェル(ケリー・マクギリス)というそれぞれの共同体に属していたふたりが共同体の間で惹かれあい揺れ動いてゆく。その共同体をめぐっては何度か「掟」というセリフが出てくる。掟を破った者は共同体を去らなければならないし、共同体の外へ放逐されなければならない。映画の中でジョン・ブックがレイチェルにむかって「君を抱いたら、ふたりとも出てゆかなければならなくなる」と呟くシーンがある。だがふたりはギリギリのところで引き返し、それぞれが以前属していた共同体にもどってゆくところでこの映画は終わる。
ふたりが目の表情だけで語り合うシーンや、ジョン・ブックが村を去ろうとする日にレイチェルの長男と一緒に黙って土手に座っている映像とか、村の皆で納屋だったか新居だったかを造るシーン(そこにジョン・ブックも参加している。ここでのモーリス・ジャールの音楽がまた良い)などなど、忘れがたいシーンはたくさんある。だがとにかく共同体にとってまれ人である者はそこに入るための掟を受け入れないかぎりやがて出てゆかなければならないのだ。
ジョン・ブックは結局去ってゆくのである。映画のいちばん最後で彼はオンボロ車をふたたび運転しながら一本道を引き返してゆく。「まれびと(稀人)」として村にやってきてまた去ってゆくのだ。この映画が公開された1985年という年は今から振り返ってみるといろんな意味でその後を暗示しているような年だったと思う。
プラザ合意をへて、時代はその後の英米による金融の自由化へまっしぐらに進んでゆく転換点に当たっていたと思われるからだ。ちょうどジョン・ブックの車が自給自足のアーミッシュという共同体から離れて行ったように、時代の切っ先はある意味で質素倹約の友愛社会から金融至上主義の競争社会に向かい始めてゆこうとしていたのだ。この映画のラストをそんな風に勝手に読み解くこともできるかもしれない。
そして25年が過ぎていくつかの金融・経済危機をへて、時代はふたたび単なるお金ではない、なにかオーガニックなものへ回帰してゆこうとしているように見える。ジョン・ブックの乗った車は、かつての一本道を映画のラストとは逆向きにオーガニックな風景と村々のほうへもう一度引き返そうとしているのかもしれない。
ぼくがこの映画を観たのはほとんど公開時のリアルタイムで、新宿か渋谷の映画館だったと思う。誰と観たのかは覚えていない。当時はジョン・ブックの車の先にこれからどんな時代の風が吹きつけてくることになるのかなど、もちろんなにも予見できなかったのだけど。
よしむね
 この間麻布十番を歩いていたら、ふと暗闇坂の道標が目にとまった。この通りは過去何度も歩いていたのだが、暗闇坂への目線(意識)がまったく失われていたのだった。写真はそのときの通りの方角からみた暗闇坂なのだが、それとともに俄かに思い出したことがあった。ここは昔寺山修司の劇団天井桟敷(兼事務所)があった場所のはずだ。ぼくの記憶が正しければ(もし間違っていたら、どなたかご指摘ください)。
この間麻布十番を歩いていたら、ふと暗闇坂の道標が目にとまった。この通りは過去何度も歩いていたのだが、暗闇坂への目線(意識)がまったく失われていたのだった。写真はそのときの通りの方角からみた暗闇坂なのだが、それとともに俄かに思い出したことがあった。ここは昔寺山修司の劇団天井桟敷(兼事務所)があった場所のはずだ。ぼくの記憶が正しければ(もし間違っていたら、どなたかご指摘ください)。 まさむねさんの「存在の耐えられない軽さ」に続いて80年代に観た映画について書いてみたい。ぼくもその時代の子というか当時は映画青年のはしくれだったということになるだろう。大学時代に映研に入っていたことがあり、多い時でたぶん年間200本くらいの映画を観ていたことがある。しかも80年代の前半はビデオ(VHS)なんてそんなに普及してなかったから、ほとんど映画館に通って観ていた。勤め人になってからもまさむねさんが言っていたのと同じように、80年代当時(90年代も)は年間50本以上は優に観ていたと思う。
まさむねさんの「存在の耐えられない軽さ」に続いて80年代に観た映画について書いてみたい。ぼくもその時代の子というか当時は映画青年のはしくれだったということになるだろう。大学時代に映研に入っていたことがあり、多い時でたぶん年間200本くらいの映画を観ていたことがある。しかも80年代の前半はビデオ(VHS)なんてそんなに普及してなかったから、ほとんど映画館に通って観ていた。勤め人になってからもまさむねさんが言っていたのと同じように、80年代当時(90年代も)は年間50本以上は優に観ていたと思う。 「去年マリエンバートで」のデジタルリメーク版(ニューマスター版)ができたとかいうことで、先月渋谷でリバイバル上映されていたので観に行ってきた。ぼくがこの作品を観たのははっきり覚えていないのだが、たしか劇場で1回、深夜のTV放送で1回観たように記憶している。
「去年マリエンバートで」のデジタルリメーク版(ニューマスター版)ができたとかいうことで、先月渋谷でリバイバル上映されていたので観に行ってきた。ぼくがこの作品を観たのははっきり覚えていないのだが、たしか劇場で1回、深夜のTV放送で1回観たように記憶している。 それに比べると、「去年マリエンバートで」はその仮構ぶりといい、華美さ加減といい、どこか気楽な感じで退屈な映画になったと思えて仕方がない。本当に変わらずに凄いと思うのは、主演女優デルフィーヌ・セイリグの美しさだ。これだけは今も変わらない。
それに比べると、「去年マリエンバートで」はその仮構ぶりといい、華美さ加減といい、どこか気楽な感じで退屈な映画になったと思えて仕方がない。本当に変わらずに凄いと思うのは、主演女優デルフィーヌ・セイリグの美しさだ。これだけは今も変わらない。 プリサーブド・フラワーをご存知だろうか。ご存知のかたも多いはず。元々は生花だが、手入れ・水やりなしでも最低2年くらいもつフラワー・アレンジメントの一種。プリサーブドに限らないが、最近男性のあいだでもフラワー・アレンジメントや自分のために花を買う習慣が増えているという。これも古くはわが国平安朝に由来する雅につながるものなのか、最近の草食系男子のムーブメントにも現れていることなのか。
プリサーブド・フラワーをご存知だろうか。ご存知のかたも多いはず。元々は生花だが、手入れ・水やりなしでも最低2年くらいもつフラワー・アレンジメントの一種。プリサーブドに限らないが、最近男性のあいだでもフラワー・アレンジメントや自分のために花を買う習慣が増えているという。これも古くはわが国平安朝に由来する雅につながるものなのか、最近の草食系男子のムーブメントにも現れていることなのか。 日本の金融資産がまだ1,400兆円くらいあるとよく言われる。ついこの間も日経新聞に記事が出ていたね。だがこれはもう数字の嘘・まやかしであり、はっきり言って毎度毎度のこういう提示の仕方はやめたほうがいいと思う。いったい誰がどういう意図があってこんな公表をやっているのだろうか。
日本の金融資産がまだ1,400兆円くらいあるとよく言われる。ついこの間も日経新聞に記事が出ていたね。だがこれはもう数字の嘘・まやかしであり、はっきり言って毎度毎度のこういう提示の仕方はやめたほうがいいと思う。いったい誰がどういう意図があってこんな公表をやっているのだろうか。 でも、そろそろそんな思考停止はやめて、ニッチもサッチもいかないことから始めていくことを覚悟して考えないといけないのじゃないだろうか。そうしないと運用をどうしてゆくかみたいな基本的な肝心なことがいつまでも議論されず等閑にされて、ただただ放置されてゆきかねないように思うのだが。結局はいずれ損の落とし前が必要になるのだから。さしあたっては国として大量に買い込んでいる米国債とかどうするのだろう? 自分で買い支えている日本国債しかり。その他諸々、有象無象、奇奇怪怪。
でも、そろそろそんな思考停止はやめて、ニッチもサッチもいかないことから始めていくことを覚悟して考えないといけないのじゃないだろうか。そうしないと運用をどうしてゆくかみたいな基本的な肝心なことがいつまでも議論されず等閑にされて、ただただ放置されてゆきかねないように思うのだが。結局はいずれ損の落とし前が必要になるのだから。さしあたっては国として大量に買い込んでいる米国債とかどうするのだろう? 自分で買い支えている日本国債しかり。その他諸々、有象無象、奇奇怪怪。