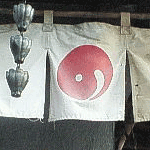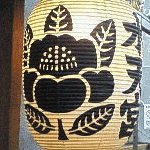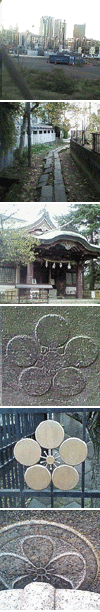都内、及び近郊の様々な墓所を回って有名人の家紋の撮影をするのが、ここ数年の楽しみとなっています。
そうした墓所の中でも、有名人、偉人比率が最も高いエリアが、知る人ぞ知る青山霊園1種ロ8号1~14側です。
本日は、そこに眠る人々の家紋一覧を作ってみました。
超大物の吉田茂元首相の墓が移転してしまったのは残念ではありますが、それでも壮観さは健在です。
青山霊園の近くにオフィスのある方々、お昼休みなどに立ち寄られてはいかがでしょうか。

|
松田正久。1847年5月25日 – 1914年3月4日、政治家。 肥前国小城郡牛津に小城藩士横尾只七の次男として生まれた。陸軍省に入省。欧州留学後に佐賀にて自由民権運動に参加し自由党に入党。『東洋自由新聞』を創刊。大蔵大臣、文部大臣、法務大臣などを歴任。三つ目結い紋。 |

|

|
林董。1850年4月11日 – 1913年7月20日、外交官、政治家。 下総国佐倉藩の蘭医・佐藤泰然の子として生まれ、幕府御典医・林洞海の養子となる。香川・兵庫の県知事、ロシア・イギリスの駐在公使、外務大臣、逓信大臣などを務めた。ロンドンで日英同盟に調印。源氏車紋。 |

|

|
松室致。1852年1月22日 – 1931年2月16日、政治家、教育者。 小倉藩藩士の長男。読みは、まつむろいたす。桂内閣で司法大臣となり司法界の粛清を行う。後に貴族院議員、枢密顧問官を歴任。治安維持法への死刑・無期懲役追加に反対した。法政大学の学長を長く務めた。丸に桔梗紋。 |

|

|
頭山満。1855年5月27日 – 1944年10月5日、国家主義者。 福岡県出身。玄洋社の総帥。右翼の巨頭・黒幕的存在。孫文、蒋介石、ラス・ビハリ・ボースら日本に亡命した革命運動家らに援助を行う。アジア主義の立場で活動した。日韓併合の際、奔走するも植民地化の状態には幻滅した。五三桐紋。 |

|

|
犬養毅。1855年6月4日- 1932年5月15日、政治家。 備中国賀陽郡庭瀬村で大庄屋・郡奉行を務めた犬飼源左衛門の次男。若槻禮次郎内閣が崩壊したため反対党(立憲改進党)の総裁として第29代内閣総理大臣に就任する。五・一五事件で凶弾に倒れる。嘴合わせ三つ雁金。 |

|

|
珍田捨巳。1857年1月19日 – 1929年1月16日、外交官、侍従長。 弘前藩士珍田有孚の長男として弘前で生まれる。皇太子(のちの昭和天皇)の訪欧に際して訪欧供奉長となる。日露戦争後の講和条約締結交渉で小村寿太郎を補佐する。裕仁親王が即位3か月後に侍従長に就任。抱き稲紋。 |

|

|
島村速雄。1858年10月26日 – 1923年1月8日、海軍軍人。 高知県出身。土佐藩の郷士・島村左五平と妻・鹿子の間に生まれる。第四艦隊司令官、海軍兵学校校長、海軍大学校校長、海軍教育本部長、海軍大将を歴任。「天性的に度量のある人物」といわれた。丸に変り三つ蔓蔦紋。 |

|

|
加藤高明。1860年1月25日 – 1926年1月28日、外交官、政治家。 尾張藩の下級藩士・服部重文、久子の次男として出生。正二位 大勲位 伯爵。第24代内閣総理大臣となり、首相在任中に治安維持法、普通選挙法を成立させ日ソ基本条約を締結。ソ連と国交を樹立させる。六つ唐団扇紋。 |

|

|
八代六郎。1860年1月25日 – 1930年6月30日、海軍軍人。 愛知県犬山市出身。地主、松山庄七の三男。水戸藩浪士・八代逸平の養子となる。日露戦争勃発までの5年間、最前線を歴任。最終階級は海軍大将。NHKドラマ『坂の上の雲』では片岡鶴太郎が演じている。折敷に三の字紋。 |

|

|
牧野伸顕。1861年11月24日 – 1949年1月25日、政治家。 大久保利通の二男として生れたが、生後間もなく利通の義理の従兄弟にあたる牧野吉之丞の養子となる。茨城県知事、文部大臣、農商務大臣、外務大臣を歴任。第一次世界大戦後のパリ講和会議に次席全権大使として参加。丸に三つ蔦柏紋。 |

|

|
加藤友三郎。1861年4月1日 – 1923年8月24日、軍人、政治家。 広島市大手町出身。広島藩士・加藤七郎兵衛の三男。最終階級は元帥海軍大将。ワシントン会議には日本首席全権委員として出席。第21代内閣総理大臣時代にはシベリア撤兵・軍縮の実施などの重要な課題を遂行。蛇の目紋。 |

|

|
本野一郎。1862年3月23日 – 1918年9月17日、外交官、政治家。 肥前国佐賀生まれ。父は読売新聞創業者の本野盛亨。弟に化学者・早稲田大学教授の本野英吉郎がいる。外務省に入りフランス公使、ロシア公使、ベルギー公使を歴任。寺内内閣で外務大臣となる。丸に蔦紋。 |

|

|
伊集院彦吉。1864年7月22日 – 1924年4月26日、外務大臣。 薩摩藩出身。妻の芳子は大久保利通の長女。釜山領事、仁川領事、イタリア特命全権大使、パリ講和会議全権委員、外務省情報部部長、関東長官を経て、第2次山本内閣外務大臣となる。勲一等旭日桐花大綬章受章。丸に三方剣花菱紋。 |

|

|
岸清一。1867年8月3日 – 1933年10月29日、IOC委員。 松江雑賀町に松江藩の下級武士岸伴平の次男として生まれる。法曹界の重鎮であり特に民事訴訟法の権威であった。国際オリンピック委員会委員に就任し死ぬまで務めた。東京都渋谷区の岸記念体育会館にその名を残す。五三桐紋。 |

|

|
清水澄。1868年9月27日 – 1947年9月25日、憲法、行政法学者。 石川県金沢市出身。宮内省及び東宮御学問所御用掛となり、大正天皇、昭和天皇に憲法学を進講した。最後の枢密院議長として新憲法の審議に尽力したが日本国憲法が施行された直後に入水自殺をした。折入り角に右一つ丁子紋。 |

|

|
白川義則。1869年1月24日 – 1932年5月26日、陸軍軍人。 松山藩士白川親応の三男として出生。上海派遣軍司令官、関東軍司令官、陸軍大臣、軍事参議官等を歴任。上海での天長節祝賀会で爆弾に遭って重傷を負いそれが元で死去する。最終階級は陸軍大将。丸に軸付柏巴紋。 |

|

|
井上準之助。1869年5月6日 – 1932年2月9日、政治家、財政家。 大分県日田市大鶴町に造り酒屋を営む家に出生。第9、11代日本銀行総裁。第二次山本、浜口、第二次若槻内閣の蔵相。浜口内閣で行った金輸出解禁や緊縮財政は世界恐慌のため深刻な不況を招き血盟団事件で暗殺される。九枚笹紋。 |

|

|
浜口雄幸。1870年5月1日 – 1931年8月26日、政治家。 高知県長岡郡に林業を営む水口家に生まれる。大蔵大臣、内務大臣などを歴任した後、第27代内閣総理大臣となる。在任中に金解禁や緊縮政策を断行し、ロンドン海軍軍縮条約を結ぶ。その風貌から「ライオン宰相」と呼ばれた。丸に上付き二つ引両紋。 |

|

|
政尾藤吉。1871年12月8日 – 1921年8月11日、外交官、政治家。 愛媛県大洲出身。藩の御用商人の長男として生まれる。外務省からシャムに派遣され、のちに同国の法律顧問として刑法・民法・商法を起草する。タイ国王より信頼を受け白象第三勲章、王冠大綬章を受ける。丸に隅立て四つ目結い紋。 |

|

|
三土忠造。1871年8月11日 – 1948年4月1日、政治家。 香川県大内郡水主村出身。読みは、みつちちゅうぞう。宮脇姓であったが、三土家に養子入りしたために三土姓を名乗った。文部大臣・大蔵大臣・逓信大臣・鉄道大臣・枢密顧問官・内務大臣を歴任した戦前政界の重鎮。丸に土佐柏紋。 |

|

|
伏見宮博恭王。1875年10月16日 – 1946年8月16日、海軍軍人。 伏見宮貞愛親王王子。議定官、軍令部総長、元帥海軍大将。日露戦争では連合艦隊旗艦三笠分隊長として黄海海戦に参加。艦長や艦隊司令長官を務めるなど皇族出身の軍人の中では実戦経験が豊富。伏見宮裏菊紋。 |

|

|
植原悦二郎。1877年5月15日 – 1962年12月2日、政治家。 長野県南安曇郡明盛村出身。国民主権論を大胆に主張するなど急進的な大正デモクラットとして言論活動を展開した。戦後、日本自由党の結成に参画し第1次吉田内閣の国務大臣として入閣する。改造後は内務大臣。蔦紋。 |

|

|
森恪。1882年2月28日 – 1932年12月11日、政治家。 大阪府大阪市西区江戸掘出身。読みは、もりかく。本名はもりつとむ。日露戦争ではバルチック艦隊の航跡を打電して日本海海戦の勝利に民間から貢献したという。政治家としては軍部と提携し日本の中国侵出に役割を果たす。丸に片喰紋。 |

|

|
丸山鶴吉。1883年9月27日 – 1956年6月3日、官僚。 丸山茂助の四男として広島県沼隈郡松永村に出生。警視庁特高課長、保安課長、静岡県内務部長、宮城県知事、朝鮮総督府警務局長、大政翼賛会事務総長、武蔵野美術学校校長、警視総監を歴任。丸に横木瓜紋。 |

|

|
高須四郎。1884年10月27日 – 1944年9月2日、海軍軍人。 茨城県桜川村出身。知英派で当時の欧米事情に詳しく、五・一五事件の後に、政党政治の崩壊を嘆き日独伊三国軍事同盟や日米開戦に反対。山本五十六や米内光政等、海軍左派勢力からも強く信頼されていた。最終階級は海軍大将。丸に違い鷹の羽紋。 |

|

|
大麻唯男。1889年7月7日 – 1957年2月20日、政治家。 熊本県玉名市出身。東條内閣の国務大臣として初入閣を果たし「東條の茶坊主」と呼ばれた。政党政治家として戦前から戦後にかけて政友本党、立憲民政党、改進党、日本民主党、自由民主党等を渡り歩く。六つ丁子車紋。 |

|

|
山口多聞。1892年8月17日 – 1942年6月6日、海軍軍人。 東京市小石川区に旧松江藩士の山口宗義の子として出生。軽巡洋艦「五十鈴」や戦艦「伊勢」の艦長を歴任。太平洋戦争では真珠湾攻撃に参加。ミッドウェー海戦で戦死。太平洋戦争期の日本海軍を代表する提督。最終階級は海軍中将。檜扇紋。 |

|
まさむね
 羽田空港の新ターミナルビル(国際線)に行ってきた。家内が国内線を利用したその帰り、迎えに行ったついでに開設した空港ターミナルビルを見てきた。第一印象としては施設は意外にシンプルでコンパクトという感じ。予想していたよりも施設内のロビーはそんなに広くなくコンパクトというのが一番強い実感。
羽田空港の新ターミナルビル(国際線)に行ってきた。家内が国内線を利用したその帰り、迎えに行ったついでに開設した空港ターミナルビルを見てきた。第一印象としては施設は意外にシンプルでコンパクトという感じ。予想していたよりも施設内のロビーはそんなに広くなくコンパクトというのが一番強い実感。 それとなんといっても便利だと驚いたのは、モノレールの新駅改札口がそのまま空港ターミナルのフロアーと直結していること(添付写真)。以前京急の広告CGだったかで国際線の空港ターミナルに電車が乗り上げているつり革広告?があったと思うのだが(それを見て本当にそうなっていると思っていた人もいるという冗談めいた話を聞いたことがあるけど、)それが冗談ではなくまさにほぼ近い形で実現されていることは驚きだった。駅の改札を出ればすぐそこは国際線のターミナルだ。
それとなんといっても便利だと驚いたのは、モノレールの新駅改札口がそのまま空港ターミナルのフロアーと直結していること(添付写真)。以前京急の広告CGだったかで国際線の空港ターミナルに電車が乗り上げているつり革広告?があったと思うのだが(それを見て本当にそうなっていると思っていた人もいるという冗談めいた話を聞いたことがあるけど、)それが冗談ではなくまさにほぼ近い形で実現されていることは驚きだった。駅の改札を出ればすぐそこは国際線のターミナルだ。 むしろ本物志向でいっそほんとうの短い歌舞伎の演目を上演したり、コスプレのGALたちのファッションショーみたいなものをやったり、ストリートミュージシャンに日本の今を歌ってもらったり、そういうことができるような劇場やスペースをターミナル内に常設しても良かったのではないか。どうせ国力も衰退しているのだし、もっと面白い活力を見せるということで、そうした本物で異国を訪れた外国の方をまずもって圧倒してみるという試みがあっても良かったのではないか、などど勝手な空想を膨らませた次第。
むしろ本物志向でいっそほんとうの短い歌舞伎の演目を上演したり、コスプレのGALたちのファッションショーみたいなものをやったり、ストリートミュージシャンに日本の今を歌ってもらったり、そういうことができるような劇場やスペースをターミナル内に常設しても良かったのではないか。どうせ国力も衰退しているのだし、もっと面白い活力を見せるということで、そうした本物で異国を訪れた外国の方をまずもって圧倒してみるという試みがあっても良かったのではないか、などど勝手な空想を膨らませた次第。 この間の週末、奈良・京都の小旅行の際、京都の吉田神社にも行ってきた。もともと私の姓と同じであり、家紋の話(これについてはまさむねさんが専門家)などからもこの辺り一帯が祖先のルーツ(出)かもしれないという興味もあって訪ねてみた。吉田神社そのものは有名かつ立派な神社なので特にここで紹介めいたことは書くつもりはない。
この間の週末、奈良・京都の小旅行の際、京都の吉田神社にも行ってきた。もともと私の姓と同じであり、家紋の話(これについてはまさむねさんが専門家)などからもこの辺り一帯が祖先のルーツ(出)かもしれないという興味もあって訪ねてみた。吉田神社そのものは有名かつ立派な神社なので特にここで紹介めいたことは書くつもりはない。 それから、関連したことだけれど、日本には何もない空間をいわゆる「やしろ」として崇める慣習があったと言われているようだが、同じように良い空間にはかならずそうした意味のない空間を寿ぐような場所があるということ。ゆとりともいえるだろうし、遊びの空間とも、赤瀬川原平さんならそれこそまさに「トマソン」だとおっしゃるかもしれないような場所。添付写真は吉田神社で見られた「やしろ」のような空間の数々。これについては神聖化している理由はちゃんとあるのかもしれないが。
それから、関連したことだけれど、日本には何もない空間をいわゆる「やしろ」として崇める慣習があったと言われているようだが、同じように良い空間にはかならずそうした意味のない空間を寿ぐような場所があるということ。ゆとりともいえるだろうし、遊びの空間とも、赤瀬川原平さんならそれこそまさに「トマソン」だとおっしゃるかもしれないような場所。添付写真は吉田神社で見られた「やしろ」のような空間の数々。これについては神聖化している理由はちゃんとあるのかもしれないが。 いずれにしても吉田神社には上記のような空間がたしかにあった。それから、君が代で歌われている「さざれ石」の原形(?)を祭っていることを知ることができたのも僥倖だった。
いずれにしても吉田神社には上記のような空間がたしかにあった。それから、君が代で歌われている「さざれ石」の原形(?)を祭っていることを知ることができたのも僥倖だった。 4)それから法隆寺の大宝蔵院でみた百済観音像は圧巻だった。ぼくは仏像にはまったく詳しくないのだが、百済観音像には感動した。通常の仏像はどこか威厳がありいかめしさやふくよかさに起因したある種の近寄りがたさがあると思う(どこか天上的で威圧的な)のだが、百済観音像はそれらの仏像とはおよそ対極的な所作を持っているように見えた。まるでジャコメッティの線的な人物彫刻のようでもあり、イコン画から抜け出してきた聖人のようでもあり、それこそグレコの描く聖人像にも似ており、とにかく全体的にきわめて細い躯体から、少しも威圧的でない、やわらかさが滲みでている感じだった。しかも天上的だがすこしも近寄りがたい感じではなく、どこまでも優しいのだ。百済というくらいだから、どこか大陸系・朝鮮の人たちに似た顔立ちのようでもあり、半目開きの物静かな面差しといい、正直こんな仏像を目にしたのは初めてのような気がした。見ていない方がおられたら、ぜひ一度ご覧になってみてください。
4)それから法隆寺の大宝蔵院でみた百済観音像は圧巻だった。ぼくは仏像にはまったく詳しくないのだが、百済観音像には感動した。通常の仏像はどこか威厳がありいかめしさやふくよかさに起因したある種の近寄りがたさがあると思う(どこか天上的で威圧的な)のだが、百済観音像はそれらの仏像とはおよそ対極的な所作を持っているように見えた。まるでジャコメッティの線的な人物彫刻のようでもあり、イコン画から抜け出してきた聖人のようでもあり、それこそグレコの描く聖人像にも似ており、とにかく全体的にきわめて細い躯体から、少しも威圧的でない、やわらかさが滲みでている感じだった。しかも天上的だがすこしも近寄りがたい感じではなく、どこまでも優しいのだ。百済というくらいだから、どこか大陸系・朝鮮の人たちに似た顔立ちのようでもあり、半目開きの物静かな面差しといい、正直こんな仏像を目にしたのは初めてのような気がした。見ていない方がおられたら、ぜひ一度ご覧になってみてください。 さて旅にはいつも終わりはなく、どこで終わるともいえず、いつ終わったとも言えないのだが、最後は法隆寺の外郭の土塀あたりを散策しつつ、傾きかけた午後の日ざしのなかで、なんとなく懐かしいような小道(奈良も京都もやはり路地がいい)をふらつきながら、添付写真のような土塀のなかに、きっと透明人間になって消えていって誰でもないひととして紛れていって終わるのだろうな。皆さん、そこでゆっくり昼寝でもしましょうね、そして良い夢をみましょう。
さて旅にはいつも終わりはなく、どこで終わるともいえず、いつ終わったとも言えないのだが、最後は法隆寺の外郭の土塀あたりを散策しつつ、傾きかけた午後の日ざしのなかで、なんとなく懐かしいような小道(奈良も京都もやはり路地がいい)をふらつきながら、添付写真のような土塀のなかに、きっと透明人間になって消えていって誰でもないひととして紛れていって終わるのだろうな。皆さん、そこでゆっくり昼寝でもしましょうね、そして良い夢をみましょう。