 この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。
この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。
電子書籍とは異なる、従来からある紙の本の可能性についてはいずれ別の機会にあらためて書いてみたいと思っているけど、ここではいわゆる3DやiPADによって代表されるある種の万能感の感覚のようなものについてぼくなりにいま思うところを書いておきたい。
3Dにせよ、iPhone やiPADにせよ、極端にいえばぼくらはその登場によって以前よりも何でもできるような気になりつつあるように思える。つまりぼくらの身体を引き延ばした形での万能感のようなもの。しょせん端末等の力を借りてなのだが、自分の見る能力がとても高くなり、読む能力や、探し出して調べる能力がとても高くなりつつあるような錯覚。良い意味では世界共通としてのイマジネーション力に変化を及ぼす可能性もあるかもしれない。
でも、これはひとつの予感だけれど、ぼくらはある種の万能感が高まるような感じになればなるほど、その一方でますます自分のなかの無能さや無能力さ加減を体感することに飢えるようになるのではないか。
 いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。
いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。
それは高校の地学だったかで習ったアイソスタシーの原理のようなものでもあるかもしれない。海のうえに浮かんでいる氷山は海面から出ている氷の量が多いだけ海面下の氷塊もまた比例して多くなっているという。だから世をあげての万能感が高まれば高まるほど海面下の無能感も高まる・・・。
やっぱり身体のセンシビリティーこそがますます大事になるように思える。理屈ではうまく言えないけど、いわば自分の無力さを肌実感できるような能力こそがとても大事になると思えるのだ。まさむねさんも以前恋々風塵の映画評のなかで述べていたけど、以下の文章にはぼくもまったく同感だ。
「おそらく、センシティブ(感度が高い)というのは自然に対して、こうした悠久の流れ、すなわち山の霊を感じ取れることだと思う。けっしてアップル社の新製品に飛びつく器用さではない」
 だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。
だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。
けっきょく読む、聞く、書く、走る、歩く人間の素の能力なんて2000年まえとたいして変わっていないかもしれないのだから。
よしむね
 まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。
まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。
もう細かいことやあらすじについては触れない。ただあのラストで、お爺さんと主人公が言葉を交わす(実はあまり交わさない)シーン。山の気に包まれたなかで、お爺さんは失恋した主人公に対して仔細はなにも尋ねず、ただ今年はさつまいもが不作だとか良くできたとか、そんな話をするだけだ。お爺さんは多分分かっているのだけど、なにも言わない。
 誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。
誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。
こんなシーンに出会えたことのなんという至福! 映画を観るとはまさにこういう瞬間に出会うことだと思わせてくれた、そういう作品。
人を好きになることはときに悲しい。ぼくももうあの少年少女たちからは遠く離れたところに来ているけど、今もときどきこの映画のいくつかのシーンを思い出す。切ないことや思いっきり楽しかったこと、ワルをしたり、そんなこんな誰にでもあったに違いない小さな出来事の数々。今も恋々風塵は走馬灯のようにそれらを浮かべて回っているのだと思う。
よしむね
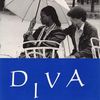 ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。
ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。
今回あらためてビデオで見なおしてみたのだが、ストーリ自体には少しも古い感じがしない。出てくるパリの風景や女性の服装や髪型にはさすがに80年代のものを感じる部分もある(メディアとしての録音テープ等もそうである)が、奇妙な味わいといい、スタイリッシュな映像や、妙な可笑しさといい、誤解を恐れずにいえば3Dという話題性があるにせよ画一的な作品であるアバターなんかよりもよほど飽きない。サスペンスフルで奇妙でスタイリッシュで恋愛的でと、なんでもある。主人公とディーバが連れ立ってデートする雨のなかの寡黙なシーンなんかとても良い。けっして平板ではない。こうした映画をみると、80年代の映画ってやっぱり面白かったなと思う。
 しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。
しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。
当時この映画をみて、東京でもまったく違和感のない、共振する時代感覚のようなシンパシーを感じたのを覚えている。それから余談だけど、ぼくはこの映画ではじめてカタラーニのオペラ「ワリー」を知って、なんて素晴らしい曲なんだと思ったものだった。今ではサラ・ブライトンなんかがさんざん歌っているので、とても有名になってしまったと思うけど。
いろんな意味で2010年になって時代はふたたびディーバに追いついたのかもしれない。
よしむね
 最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。
最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。
たしかに実体経済レベルでは一時の最悪期(去年の春前後)を過ぎつつあることは事実かもしれない。ぼくが身を置いているハイテク関連業界でもかなり忙しい状況になっている。自動車業界、半導体や電子部品業界、精密機器業界、工作機械業界然りだろう。いわゆる実体経済といわれる部分については製造業という観点からみればかなり忙しくなってきていると思う。それもまるでジェット・コースターのようにダウンしたと思ったら急にアップし始めて、猫も杓子もという感じだ。ここに来て急にみんな一斉に、という感じかもしれない。
でも、果たして、と思ってしまう。これが実体というものだろうか? ある意味で実需に根ざしていると思われる実体経済がこんな風に急激に萎んだり膨らんだりするものだろうか。結局実体経済もきわめて虚の経済(レバレッジの効いたバブルチックな経済)に似てきているということなのだろうか。これがグローバルの正体なのかもしれない。悪くなるときはみんな一斉に悪くなり、良くなるときも一斉に良くなるように映って見え、世界での自動車やパソコンや携帯電話や液晶TVの売れ行きにすぐに左右され、みたいな・・・・。
結局グローバル化が進んだことで、経済というものがますます薄っぺらになり、何処も彼処も似たようなトレンドを受けざるを得なくなったということ。その意味で経済そのものに厚みがなく、奥行きや深みがなくなったのだろう。リーマンショック以後、ほんとうは従来の虚の経済から脱却しようという(それを考える)良い機会だったのかもしれないのだけど、やっぱりみんなは喉元すぎれば熱さを忘れるで、バブルチックなものが恋しいのである。というよりも裏返せば今の経済原理そのものがなにかのバブルなしには成立しにくくなっているということでもあるのだろう。麻薬なしでいられない患者たちが増えているのだ。
 でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?
でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?
今騒がれているギリシャに端を発したヨーロッパの経済危機にしても、誰かにババを引かせようとしているゲーム漬けの人たちの策略としか思えない。ギリシャだけが極端に悪いわけではない。借金漬けという意味では実体はアメリカも英国も似たようなものだ、もっと悪いだろう。だいいちユーロよりも米ドルが安全なわけがないじゃないか。
でも、まあこれくらいにしておこう。世の中が変わるときはたぶん一直線ではなく、蛇行しながら変化してゆくのだ。これは以前まさむねさんが小沢一郎について書いていた記事(1月28日)でも述べていたことと同じだけれど、ぼくもまったく同感だ。
人間はホモ・エコノミクスでもあるとおもうけど、でもやっぱり「パンのみに生くるにあらず」もほんとうだ。お金なしでは生きられないが、いかにお金や経済の起伏と上手に別れていけるかも考えていきたい、そう思う。
よしむね
Just another WordPress site
 この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。
この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。 いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。
いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。 だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。
だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。 まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。
まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。 誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。
誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。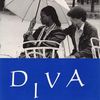 ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。
ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。 しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。
しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。 最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。
最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。 でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?
でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?