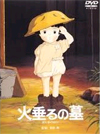 人それぞれにその人に固有の年中行事がきっとあるだろうと思う。ぼくの場合、一年の終わりにはかならず観たいビデオがあって、たとえばそれは「ゴダールの映画史」になっている。多少の例外はあるけど、大体かならず年末になるとそのビデオ作品を引っ張り出してきて観て来た。あるいは夏になると一回は山下達郎の歌を聞きたくなるといったようなことだ。それは自分にとってのある種の儀式のようなもので、それをしないとどこか落ち着かないといったようなところがある。
人それぞれにその人に固有の年中行事がきっとあるだろうと思う。ぼくの場合、一年の終わりにはかならず観たいビデオがあって、たとえばそれは「ゴダールの映画史」になっている。多少の例外はあるけど、大体かならず年末になるとそのビデオ作品を引っ張り出してきて観て来た。あるいは夏になると一回は山下達郎の歌を聞きたくなるといったようなことだ。それは自分にとってのある種の儀式のようなもので、それをしないとどこか落ち着かないといったようなところがある。
それはさておき、標題のアニメ「火垂るの墓」である。あえて夏アニメと限定すべきアニメでないことは重々承知しているが、特に蛍が出てくる季節性からそう言ったまで。ぼくの夏アニメと銘打った特版のこれが最後となります。
原作は野坂昭如氏の同名小説で、あまりにも有名な有名すぎるアニメといってもいいだろう。1988年、スタジオジブリの制作で監督は高畑勲さん。アニメ版以外にもテレビドラマ版、実写映画版もあるらしいが、いずれもぼくは観ていない。このアニメについては以前あるラジオ番組の女性パーソナリティーの方が自分にとってとにかくアニメの中でのベストであり、何度見てもかならず号泣してしまうと言っていたのを聞いたことがある。
かようにもおそらく多くの人たちがある場面ではきっと涙するだろうし、たとえば包帯姿の母親が出てくるシーンがあるのだが、そのリアルな描写の持つ衝撃度の深さや、物語がおのずから負ってしまっているような言い様のない切なさのようなものをふくめて、作者の意図がどうあれおそらく多くの方が静かに戦争への否を歌っているアニメの代表として取り上げていることにも異論は少ないだろうと思う。
 夏になるとTVでも何度か放映されていたように記憶しているが、じつはぼくはちゃんと観てこなかった。今回あらためてビデオを借りてきて観なおした。その悲惨さや戦争の酷さや醜さとか、そういう視点での評価はたくさんなされて来ていると思うので、ここではそういう観点ではあまり触れるつもりはない。むしろ今回の3.11以後との絡みで気になったことを中心に少し書いてみたい。
夏になるとTVでも何度か放映されていたように記憶しているが、じつはぼくはちゃんと観てこなかった。今回あらためてビデオを借りてきて観なおした。その悲惨さや戦争の酷さや醜さとか、そういう視点での評価はたくさんなされて来ていると思うので、ここではそういう観点ではあまり触れるつもりはない。むしろ今回の3.11以後との絡みで気になったことを中心に少し書いてみたい。
ひとつ目は、本作品にも出てくる戦中戦後の焼け跡の景色が、あらためてまさについ先ごろの3.11後の被災地の風景と重なることだ。戦後生まれが多くを占めるにいたった現在、ぼくらの大方にとってどれだけ戦後の焼け跡の光景がリアルに感じ取られていたのか、多くの敗戦体験や言説が語られてはきたが、その実は極めてあいまいになっていたようにも思うのだ。それがこのたびの津波の後の根こそぎの無の光景は、まさにぼくたちに焼け跡の何もない光景がどういうものだったのかをまさにリアルに突き出してきた(だからみんな言葉を失った)のだと思う。
第二の、あるいは第三の、敗戦と形容される所以でもあろう。では今回、ぼくらは何に負けたのか? 自分たちの過信や驕りにか? 戦後築きあげてきたと思ってきた日本という堅固なシステム(幻想)のその実のいい加減さに負けたのか? いまそれに答え得る回答をぼくは持っていない。
だが、そこから更にいえば上記の焼け跡にないものがたぶん3.11以後にひとつあると思うのだ。それは放射能汚染後の避難区域の世界だ。たしかに原爆直後の広島や長崎の光景はある。だが、それらは原子爆弾投下というある意味で可視の爆発(閃光)後の焼け跡だった。
今回は原発事故という可視の出来事はあったが、どちらかというとむしろ放射能汚染事故という不可視の領域に近いようなアクシデントに起因していたように思われるのだ。つまり何が起きているのかいまだによく分からないという意味でも。それによってもたらされた避難区域の世界は地震等の被害はあるにせよ、家も道路もそれまでの日常となんら変わりないようでありながら、いわばそこに住む人だけがいなくなった(強制移住させられた)世界だ。見えない放射能が示す異常値によってだけ、かろうじて生命にとって危ないことが指摘されるような世界。
その収束がいったいいつになるのか、いまだまったく見通しが立っていないなかで、ぼくら日本人が長い責め苦を見守らなければならないというだけでも戦後まったく初めての経験。同じような焼け跡後の焦土のようにみえても、ぼくには「火垂るの墓」の焦土(主人公の清太が動き回る世界)のほうがまだ人間的だし将来に希望を託すことができたように思う。それは東京が空襲にあった後の焼け野原も同様だろう。人々には生活の大変さが依然残っていたとしても復興への希望もまたあったはずだから。だが、放射能汚染の避難区域で人はほんとうに希望を託すことができるのだろうか? ぼくはいま何も答えることはできない。
 ふたつめは、主人公の清太と妹の節子が母を失って、その最後にはふたりだけの生活(盗みも入れた自給自足)に入ってゆき、やがて節子が衰弱死してゆくことになるのだが、そこにいたるある種の違和感のようなものについてである。親戚のお世話になりながら、やがて居心地が悪くなり(邪険さもあり)、家出して二人だけの王国のような世界で自活してゆくのだが、次第に衰弱に見舞われてゆくシチュエーションのなかでそこに救いの手をさし伸ばす大人がひとりも現れてこなかったのはなぜなのだろうか?
ふたつめは、主人公の清太と妹の節子が母を失って、その最後にはふたりだけの生活(盗みも入れた自給自足)に入ってゆき、やがて節子が衰弱死してゆくことになるのだが、そこにいたるある種の違和感のようなものについてである。親戚のお世話になりながら、やがて居心地が悪くなり(邪険さもあり)、家出して二人だけの王国のような世界で自活してゆくのだが、次第に衰弱に見舞われてゆくシチュエーションのなかでそこに救いの手をさし伸ばす大人がひとりも現れてこなかったのはなぜなのだろうか?
戦中戦後とはいってもまだまだ前近代的な意識?(家とか大家族主義とか郷土意識とか云々)も色濃く残っていたはずであり、もう少し鷹揚な大人たちが登場してきてもよかったように思うのだが。たとえ他人の子供であっても一緒に育ててくれる大人たちがひとりくらい出てきてもよいようにも思う(黒澤明監督の「羅生門」の最後で志村喬演じる男がたしかそうしたように?)が、描かれるのはどこまでも無関心で利己的な大人たちの姿のほうが中心になっている。
 主人公の清太はそうした利己的な大人たちの世界を嫌って、ある意味純真無垢な自分たちだけの王国を樹立して生きることを選んだようにも思えるのだが、それは原作でもそうなのか、あるいはアニメがそこを強調しているのか、その辺は原作を読んでいないぼくにはよく分からないところだ。
主人公の清太はそうした利己的な大人たちの世界を嫌って、ある意味純真無垢な自分たちだけの王国を樹立して生きることを選んだようにも思えるのだが、それは原作でもそうなのか、あるいはアニメがそこを強調しているのか、その辺は原作を読んでいないぼくにはよく分からないところだ。
だが、なぜ清太がそこまでかたくなに大人たちの世界に背をむけなければならなかったのか今ひとつ理解できないとも言える。本当に妹を助けたかったら、まずもって大人たちの世界に戻らなければならないことはある段階から明白となっていたはずなのに、どこまでもふたりだけの自活の王国に拘りとどまり続けた理由とは? たとえばあの親戚の家に絶対に戻ることはできなかったのだろうか?節子を最後に診察するお医者さんも冷たい(無関心な)キャラクターの設定になっている。
こうした一連の流れは本アニメの意図とも絡んでいるのかもしれないが、この辺については本作品をご覧になった皆さんのご意見をいろいろうかがってみたいところです。利己的・保身的な大人社会に対して、純粋無垢な子どもの世界をより対置してみたかったというのが、いまとりあえず感じられる作品(作者)の意図のように思えますが、ここはよく分からないところです。
 そして三つめは、作品のいちばん最後でほとんど目立たないように挿入されているラストの一枚の絵のような映像のこと。そこに坐っているのが主人公の分身なのか、まったくの赤の他人なのか、じつは誰でもよいのだが、ひとりの男が、高層のビル群とそれが作り出す幻影のような街の灯を見下ろす丘の斜面に坐っていて、その傍でさかんに蛍が舞い、蛍のひかりが浮遊しているのだ。
そして三つめは、作品のいちばん最後でほとんど目立たないように挿入されているラストの一枚の絵のような映像のこと。そこに坐っているのが主人公の分身なのか、まったくの赤の他人なのか、じつは誰でもよいのだが、ひとりの男が、高層のビル群とそれが作り出す幻影のような街の灯を見下ろす丘の斜面に坐っていて、その傍でさかんに蛍が舞い、蛍のひかりが浮遊しているのだ。
その蛍の火だけはまわりの状況がどう変わろうと、それが焦土から高層ビル群へ戦後という大いなる影が歩んで移り変わってきたとしても(3.11以後も)、いまもどこかの草露に濡れて繋がっているただひとつのものかもしれない、とでも言うように。どんなに頑丈そうにみえてもビルはいつか壊れるが、蛍の火だけは弱弱しくも真実小さな火であり、もしかしたらだからこそこの地上を浮遊してやまず生き延びてきたのかもしれない。
おそらくすべての変遷と虚構を見届けながら、そのかたわらで、毎夏の夜、蛍の火が舞ってきたのだ。それはそのまますぐれてメメント・モリ(死を想え、死を忘れるな)という鎮魂の声にも通じているかのようだ。「火垂るの墓」はまさにその地点でこそ終わる作品であり、ながく余韻を紡ぎ出してやまないように思える。
よしむね




 まず第一弾は「雲のむこう、約束の場所」(新海誠監督、2004年)。評判は聞いていたが、実は観たのは今回が初めてで自宅でDVDを観た。いわゆるセカイ系の定義をぼくはよく知らないのだが、登場人物たち(藤沢浩紀、白川拓也、沢渡佐由理の三人が主要人物)がみんな孤独感を生きていて、いきなり世界の異相(ユニオンの塔というものが出てくる、これはいろんなものの暗喩か。併行世界とも呼ばれ、政治の亀裂や戦いの暗喩でもあり、不可侵のなにかのようでもあり、なにかの夢の形象のようでもあり、おそらくさまざまな意味を包含しているのだろう)と直結しているようなストーリー構成は、広義には本アニメもセカイ系と呼ばれる部類に入るのかもしれない。
まず第一弾は「雲のむこう、約束の場所」(新海誠監督、2004年)。評判は聞いていたが、実は観たのは今回が初めてで自宅でDVDを観た。いわゆるセカイ系の定義をぼくはよく知らないのだが、登場人物たち(藤沢浩紀、白川拓也、沢渡佐由理の三人が主要人物)がみんな孤独感を生きていて、いきなり世界の異相(ユニオンの塔というものが出てくる、これはいろんなものの暗喩か。併行世界とも呼ばれ、政治の亀裂や戦いの暗喩でもあり、不可侵のなにかのようでもあり、なにかの夢の形象のようでもあり、おそらくさまざまな意味を包含しているのだろう)と直結しているようなストーリー構成は、広義には本アニメもセカイ系と呼ばれる部類に入るのかもしれない。



 ただ何度も繰り返すがストーリーにはさして興味がない。全体に流れる孤独感のトーン、夏のはかなさ、短い夏の煌きのなかで、もしかしたら誰にでもありえた、行き場のないような、結晶した時のような、ひと夏のたゆたい、その体験の翳のリアリティーにこそ、このアニメが依って立つすべてがあるようにも思うのだ。それからあのユニオンの塔の存在が、最近の原発事故以後を思うとき、また違った意味で妙にリアルでもあるように感じられた。なにはともあれ夏の青空と雲にささえられたような一片の作品!
ただ何度も繰り返すがストーリーにはさして興味がない。全体に流れる孤独感のトーン、夏のはかなさ、短い夏の煌きのなかで、もしかしたら誰にでもありえた、行き場のないような、結晶した時のような、ひと夏のたゆたい、その体験の翳のリアリティーにこそ、このアニメが依って立つすべてがあるようにも思うのだ。それからあのユニオンの塔の存在が、最近の原発事故以後を思うとき、また違った意味で妙にリアルでもあるように感じられた。なにはともあれ夏の青空と雲にささえられたような一片の作品!
