9月に埼玉東南部の高校の演劇部が集う演劇祭に行った。
そこでいくつか見た演目のうちのひとつに強いインパクトを受けた。
だがきっと今後どこかで上演・発表されることはないだろう。それはちょっと惜しいので、ここでぜひ紹介したい。春日部女子高校演劇部の『ひまわり』という作品だ。脚本も演出も演劇部自身よるという。
舞台は高校の教室。出演者は女子ばかりだから、女子高という設定か。
大きく2つの部分からなる。
前半はいじめの場面。登場人物は5人で、仮にA、B、C、D、Eとする。
被害者Aが加害者C、D、Eからいじめられている。
BはAの友人で、Aがいじめられている境遇に心を痛めている。
A=被害者
B=Aの友人。後に被害者
C=加害者(首謀者)
D=加害者
E=加害者
やがてAはいじめを苦にして、登校しなくなる。
すると、加害者CDEは次にBを標的にする。
いじめは構造であり要素は入れ替え可能だという説の通りに事態は進行する。
Bは加害者グループからの陰湿ないじめに耐えかねて(カッターナイフをつきつけて「死んでくれる?」と脅すおぞましい場面もある)、転校を決意する。
だが、Bが逃げおおせたとして、そのあとに残されたAにはどんな苦難が待ち受けているだろうか。
BはAに対して負い目を感じて、途方にくれる。
ここで唐突にストーリーは後半に移る。
移るきっかけは、
「はいカーット!」
という声。
舞台が明るくなり、みんなががやがやと集まってくる。
おお! 今までのお話は演劇部員たちによる稽古の場面だったのだ。
つまりいじめはすべてお芝居であり、架空の世界のできごとだった。
我々は陰湿な暴力から解放された。
一転して、笑いのある明るい世界が現われる。
でも明るいのは表面だけだった。ここにもいじめはあったからだ。
いじめ構造は説話次元をも超えて存続しつづけるからだ。
ただし世界が変わったら構造内の構成要素がシャッフルしてしまった。いじめ被害者と加害者が逆転したのだ。
劇中劇内でいじめられて登校拒否したAはここからは加害者。そして加害者の中心人物だったCは被害者であることが明らかになる。まるで芝居内容への復讐であるかのようだ。さっきまであんなに憎憎しい悪の塊にしか見えなかったCは、ここからは弱くてナイーブな少女にしか見えない。
またいじめに加担していたD、Eはここでは傍観者(という名の加害者)だ。
そして劇中劇でAをかばってその後被害者に転じたBはいじめ構造から逃れているらしい。
Bは演劇部の部長である。部を統率する役割を担っているにも関わらず、部内を蝕むいじめの存在に気づいていない。
部長がいるときは明るく活気のある演劇部だが、部長が姿を消すととたんに暴力が顔を出す。
A=加害者
B=演劇部部長
C=被害者
D=傍観者
E=傍観者
AがCを執拗に追い詰める。
「最近ものがなくなるのよね。あんたが犯人としか思えないのよね」
傍観者たちも、そういえば自分たちのものもなくなった、と同調する。
身に覚えのない罪を着せられて、傷つくC。
Cはなぜか部長に苦難の状況を打ち明けない。たしかにいじめ被害を受ける子供がなかなか親に打ち明けられないという実態を我々は知っている。
Aが机に放置されたCの服をカッターで切り裂くシーンが痛い。
だが、とうとう部長は暴力の証拠を発見し、部内にいじめがあることを認識する。
部長はきびしく加害者Aを追及し、結局Aは反省して謝罪する。被害者は許す。部に平和が戻る。
だが劇はまだ終わらない。
部員がみんな去った部室で、ひとり残った部長がどこからか袋をひっぱり出す。
袋を逆さにすると、床に物が散らばる。傘や文房具やいろいろな小物。
「最近ものがなくなる」と彼女らが言っていた、あのものたちだ。
部長が犯人であり、いじめの元凶だったのだ。
「面白かったな!」と部長。激しく笑う。
だが、まだまだ劇は終わらない。
舞台に現れたDとE。
「あいつら面白すぎだ。あはははあは」
Cが立っている。
「悲劇のヒロインぶるの楽しかったのになあ。あんなやつ好きじゃないっての。あははははは」
Aが携帯電話で話している。
「もしもし、今部活終わった、ほんと今日はむかついた。あははははは」
全員、身をよじって激しく笑う。
そして、いっせいに独り言をいう、「あ~あ。みんな……」
舞台、暗くなる。
全員が叫ぶ、「死んじゃえばいいのに!」
幕。
破壊的な結末だ。観客はあっけにとられた。なんと加害者も被害者もみんなワルだったのか。
叫びの内容を見れば憎悪を読み取るしかないのだが、唱和の響きからはなんだかすがすがしさを感じる。したたかさ、力強さを感じる。この力強さはいじめ解決のヒントにつながるのか?
もちろん構造からは逃げられない。内部にとどまることしかできない。せめて一斉に叫んで孤立した共闘で、構造への抵抗を示そう、ということか。
TBSラジオ「ニュース探求番組Dig」で7月に「”いじめ”を構造から考える」という話題が放送された。たいへんに刺激的な内容だった。
内藤朝雄さんという学者が、明晰でラディカルな議論を展開していた。
TBSラジオの方針変更によって現在Podcastを聞き返すことができないのだが、議論の内容は自身のブログに掲載されている。「内藤朝雄HP -いじめと現代社会BLOG-」の「2010-08-27 いじめの直し方」というエントリー。
内藤さんによると、学校という制度こそいじめの原因であることは、狭いスペースに長時間監禁すると暴力的な異常行動を起こすラットなどの動物実験からも明らかだという。学校を解体しない限り、いじめはなくならないのだ。
じつに
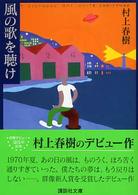 その時代とは特に80年代前半からバブル期の全盛前夜辺りまでとなる。「ノルウェイの森」が出版されたのは1987年で、「風の歌を聴け」が1979年に群像に掲載されたので、この間ほぼ10年近く、ぼくはずっと村上春樹の小説をリアルタイムで読んでいた。
その時代とは特に80年代前半からバブル期の全盛前夜辺りまでとなる。「ノルウェイの森」が出版されたのは1987年で、「風の歌を聴け」が1979年に群像に掲載されたので、この間ほぼ10年近く、ぼくはずっと村上春樹の小説をリアルタイムで読んでいた。 けれど、そのことによって僕にとっては村上さんの小説がリアルなものではなくなったのだ。なによりも物語になりきれないその不全さを愛していたのだから、たぶん。「羊をめぐる冒険」も「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も然りだった。
けれど、そのことによって僕にとっては村上さんの小説がリアルなものではなくなったのだ。なによりも物語になりきれないその不全さを愛していたのだから、たぶん。「羊をめぐる冒険」も「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も然りだった。 最後に、先のコメントで、ぼくは村上さんの小説には本当の意味で他者性がないかもしれないとも書いた。同じキャラクターの分身の物語ではないか、とも。じゃ、ぼくが感じる他者性のある小説とは何か。それはたとえば島尾敏雄さんが書いた「死の棘」という小説だ。ずっと昔に読んだのでもう細かいあらすじはすっかり忘れてしまっているけど、要は浮気をした主人公のおかげで気が変になってしまった(なりかかった)奥さんと、それにとことん付きあい付き添ってゆくしかない男の話。しまいには主人公の男も気が変になりかかるような、ふたりがふたりで病んでゆくような、どちらが快癒してゆくか分からないような、そんな決して切り分けることのできない現実のなかで生き延びてゆく日々を書き続けたもの。その不分明さ。そういうものこそ実は本当の他者性ではないかと最近のぼくは思っている。
最後に、先のコメントで、ぼくは村上さんの小説には本当の意味で他者性がないかもしれないとも書いた。同じキャラクターの分身の物語ではないか、とも。じゃ、ぼくが感じる他者性のある小説とは何か。それはたとえば島尾敏雄さんが書いた「死の棘」という小説だ。ずっと昔に読んだのでもう細かいあらすじはすっかり忘れてしまっているけど、要は浮気をした主人公のおかげで気が変になってしまった(なりかかった)奥さんと、それにとことん付きあい付き添ってゆくしかない男の話。しまいには主人公の男も気が変になりかかるような、ふたりがふたりで病んでゆくような、どちらが快癒してゆくか分からないような、そんな決して切り分けることのできない現実のなかで生き延びてゆく日々を書き続けたもの。その不分明さ。そういうものこそ実は本当の他者性ではないかと最近のぼくは思っている。
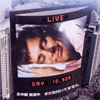
 羽田空港の新ターミナルビル(国際線)に行ってきた。家内が国内線を利用したその帰り、迎えに行ったついでに開設した空港ターミナルビルを見てきた。第一印象としては施設は意外にシンプルでコンパクトという感じ。予想していたよりも施設内のロビーはそんなに広くなくコンパクトというのが一番強い実感。
羽田空港の新ターミナルビル(国際線)に行ってきた。家内が国内線を利用したその帰り、迎えに行ったついでに開設した空港ターミナルビルを見てきた。第一印象としては施設は意外にシンプルでコンパクトという感じ。予想していたよりも施設内のロビーはそんなに広くなくコンパクトというのが一番強い実感。 それとなんといっても便利だと驚いたのは、モノレールの新駅改札口がそのまま空港ターミナルのフロアーと直結していること(添付写真)。以前京急の広告CGだったかで国際線の空港ターミナルに電車が乗り上げているつり革広告?があったと思うのだが(それを見て本当にそうなっていると思っていた人もいるという冗談めいた話を聞いたことがあるけど、)それが冗談ではなくまさにほぼ近い形で実現されていることは驚きだった。駅の改札を出ればすぐそこは国際線のターミナルだ。
それとなんといっても便利だと驚いたのは、モノレールの新駅改札口がそのまま空港ターミナルのフロアーと直結していること(添付写真)。以前京急の広告CGだったかで国際線の空港ターミナルに電車が乗り上げているつり革広告?があったと思うのだが(それを見て本当にそうなっていると思っていた人もいるという冗談めいた話を聞いたことがあるけど、)それが冗談ではなくまさにほぼ近い形で実現されていることは驚きだった。駅の改札を出ればすぐそこは国際線のターミナルだ。 むしろ本物志向でいっそほんとうの短い歌舞伎の演目を上演したり、コスプレのGALたちのファッションショーみたいなものをやったり、ストリートミュージシャンに日本の今を歌ってもらったり、そういうことができるような劇場やスペースをターミナル内に常設しても良かったのではないか。どうせ国力も衰退しているのだし、もっと面白い活力を見せるということで、そうした本物で異国を訪れた外国の方をまずもって圧倒してみるという試みがあっても良かったのではないか、などど勝手な空想を膨らませた次第。
むしろ本物志向でいっそほんとうの短い歌舞伎の演目を上演したり、コスプレのGALたちのファッションショーみたいなものをやったり、ストリートミュージシャンに日本の今を歌ってもらったり、そういうことができるような劇場やスペースをターミナル内に常設しても良かったのではないか。どうせ国力も衰退しているのだし、もっと面白い活力を見せるということで、そうした本物で異国を訪れた外国の方をまずもって圧倒してみるという試みがあっても良かったのではないか、などど勝手な空想を膨らませた次第。 「ブラタモリ」はご存知タモリが東京という町の今昔をどこかワープしながら散歩するというような内容。たとえばこの間あった新宿の探索では、新宿という町が江戸時代からいかに水道(玉川上水)とのかかわりをもって発展してきたかという観点でその足跡をたどりながら散歩してゆく流れになっていた。たとえば四谷の交差点のコーナーの曲がり具合が実は上水の曲がり具合をそのまま反映したものであるという事実や、上水からの分水(枝水)が今は柵の脇の草の生えたただの無意味な土地のように伸びていることなどが明らかにされてゆく。
「ブラタモリ」はご存知タモリが東京という町の今昔をどこかワープしながら散歩するというような内容。たとえばこの間あった新宿の探索では、新宿という町が江戸時代からいかに水道(玉川上水)とのかかわりをもって発展してきたかという観点でその足跡をたどりながら散歩してゆく流れになっていた。たとえば四谷の交差点のコーナーの曲がり具合が実は上水の曲がり具合をそのまま反映したものであるという事実や、上水からの分水(枝水)が今は柵の脇の草の生えたただの無意味な土地のように伸びていることなどが明らかにされてゆく。 それから「世界ふれあい街歩き」のほうはカメラマンの体に装着された水平移動カメラが世界のある都市の路地をまるで縫ったり這ったりするように移動してゆきながら、その間に現地の人とまるで対話しているような日本語のナレーションが入りつつ進んでゆくというコンセプト。これを早朝(朝の出勤時刻)から夕方まで街中を歩き続けるシーンが続いて、そこで偶然に出会った人やモノ、風景を映し出すという流れになっている。
それから「世界ふれあい街歩き」のほうはカメラマンの体に装着された水平移動カメラが世界のある都市の路地をまるで縫ったり這ったりするように移動してゆきながら、その間に現地の人とまるで対話しているような日本語のナレーションが入りつつ進んでゆくというコンセプト。これを早朝(朝の出勤時刻)から夕方まで街中を歩き続けるシーンが続いて、そこで偶然に出会った人やモノ、風景を映し出すという流れになっている。