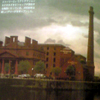最近とても良い2つの映画を見た。映画のタイトルは「サイドウェイズ」と「アンナと過ごした4日間」。どちらも地味な映画なのだが佳品と呼ぶにふさわしい作品だと思う。ここでは映画の解説を書くことが目的ではないのでとにかく作品を見ていただくしかないのだが、以下に少し紹介文めいたサワリを書いてみたい。
 「サイドウェイズ」は2004年同名のハリウッド映画のリメイク版。監督は外国人のチェリン・グラック。主演陣は日本人の俳優で小日向文世、生瀬勝久、鈴木京香、菊池凛子の4名。まず役者たちの顔ぶれが良い。物語は解説文をそのまま使わせてもらうと、「ワインの産地、カリフォルニアのナパ・バレーを舞台に、さえない40代の男二人のパッとしない人生が少しずつ動き出していく様をていねいに描く」とある。まあたしかにそのように動いてゆく。そこに同世代といってよい二人の女たち(鈴木京香と菊池凛子)が絡む。
「サイドウェイズ」は2004年同名のハリウッド映画のリメイク版。監督は外国人のチェリン・グラック。主演陣は日本人の俳優で小日向文世、生瀬勝久、鈴木京香、菊池凛子の4名。まず役者たちの顔ぶれが良い。物語は解説文をそのまま使わせてもらうと、「ワインの産地、カリフォルニアのナパ・バレーを舞台に、さえない40代の男二人のパッとしない人生が少しずつ動き出していく様をていねいに描く」とある。まあたしかにそのように動いてゆく。そこに同世代といってよい二人の女たち(鈴木京香と菊池凛子)が絡む。
よくある再会と新たな旅立ちのストーリー。しかもみんな中年であり、どこかにほろ苦いテイストをひきずって旅立つことになるのだ。それが陽光明るいカリフォルニアを舞台にして静かに淡々とシニカルにそしてやわらかくある意味では決して気負わずに主人公たちが動いていく。大それた事件が起きるわけではない日常の連鎖の延長の中で、主人公たちは悩み、諦め、観念してゆく。まあそんな物語だが、そういう気負わなさが良い。
結局はなにも解決しないし、勿論多少のドラマ風の味付けはあるのだがすっきりかっこよく終わるようには行かない。売れないシナリオライターとしての主人公の設定や留学や渡航の経験などが題材に扱われていても、特別な人物設定ではないし、舞台となるアメリカも心象風景としてみれば現代日本の延長とそれほど劇的に変わる土地として捉えられているわけではない。人も土地もある意味で非常に等質(均質)であり、リアルなのだといえる。
 一方の「アンナと過ごした4日間」はこれとは対蹠的にまったく異常さに基づくような内容になっている。監督はポーランドのイエジー・スコリモフスキー。現代世界の特徴のひとつが等質性にあるとすれば、この映画はそのすべてにおいてこれと反対を行くような設定だ。主人公は病院の火葬場で働くまったく冴えない寡黙な独身男。年老いた祖母との二人暮しだが、ほとんど引きこもりのような二人の生活。やがて祖母の死。そして異常なレイプ事件を目撃。主人公自身も過去に異常な暴力事件(?)に遭った過去を持つ。
一方の「アンナと過ごした4日間」はこれとは対蹠的にまったく異常さに基づくような内容になっている。監督はポーランドのイエジー・スコリモフスキー。現代世界の特徴のひとつが等質性にあるとすれば、この映画はそのすべてにおいてこれと反対を行くような設定だ。主人公は病院の火葬場で働くまったく冴えない寡黙な独身男。年老いた祖母との二人暮しだが、ほとんど引きこもりのような二人の生活。やがて祖母の死。そして異常なレイプ事件を目撃。主人公自身も過去に異常な暴力事件(?)に遭った過去を持つ。
それから目撃したレイプ事件の相手の女性(看護婦)への恋。覗き見。それが嵩じての、ストーカーに近い偏執的な行動。ある一夜の物語、その続き。そして愛の告白。絶対的な愛といえるほどの、なにかへの、・・・・等々。
たぶんこんな風にいくらこの映画のことを書いても、この映画の良さはおそらく伝わらないだろうと思う。だいいち映画そのものが本当はことばでくくられることを拒んでいるし、優れた映画ほど映像や音や役者の身振り・演技のすべてをふくめて、言葉で要約することができないものを持っているからだ。ただぼくがこの映画で強く感じるのは、主人公が持つ愚直さと一途さとほとんど狂気に近いような純粋さが持つ、肯定性のようなものだ。あるいはもし別の言葉でいうなら、やはり希望ということ。それでもぼくは君を愛している、と。
ここで扱われている世界はいずれも重く苦しい。何一つ等質ではなく、貧困をふくめて凹凸ばかりのある生活。主人公もおよそ世間の等質性から外れたアウトロー(脱落者?)だ。だが、それでも人は希望を持つことができるし、そうする権利があると、この映画は底のほうで語ろうとしているかのようだ。
いま、ぼくらを取り巻く世界は、ほとんど等質といってよい世界だ。インターネット、携帯電話、パソコン、高層ビル、電気街、ビジネス街。家とオフィスの往復、通勤電車。人が等質に利用し、まずもって等質に生きることが前提の社会だ。多かれ少なかれ先進国の大都市ではほとんど当たり前となった光景とそれらが累々と積み重なった生活。だが何かのきっかけでその等質のすきまから、ふと等質でないものが顔をのぞかせる。それが秋葉原での集団殺人事件につながったりするのかもしれないが。
いずれにしても大事なのは、何が等質で何が異常かを見極めることではないだろう。まずもって好むと好まざるとにかかわらずぼくらは等質の足場に身をおいているのだ(そのことに観念しながらも)。だが、けっして等質でないものへの目配りも忘れることなく、いわばそうしたものと自由に往復できる視線を持っておくことが必要なのだと思う。ちょうど「サイドウェイズ」と「アンナと過ごした4日間」の間で揺れ動き続けること。それこそが必要なのだと。
よしむね
 櫻井孝昌さんの「
櫻井孝昌さんの「 一例を挙げるなら、韓国の企業で三星電子だったと思うが、世界のある市場に製品を売る前に、ある人材を送り込んで一年間まったく自由に過ごさせることで現地に溶け込ませ、その国の文化に始まり何から何まですべてを吸収させて、その現地にあった市場戦略(販売戦略)を考えさせるという研修員プランがあるという。ここまで時間をかけて相手の国のことを研究することを日本企業(=人)はやっているだろうか。そこまで相手のことを見ようとしているとは思えない。
一例を挙げるなら、韓国の企業で三星電子だったと思うが、世界のある市場に製品を売る前に、ある人材を送り込んで一年間まったく自由に過ごさせることで現地に溶け込ませ、その国の文化に始まり何から何まですべてを吸収させて、その現地にあった市場戦略(販売戦略)を考えさせるという研修員プランがあるという。ここまで時間をかけて相手の国のことを研究することを日本企業(=人)はやっているだろうか。そこまで相手のことを見ようとしているとは思えない。 戦後、焼け野原だけが残ったといわれる(もちろん戦後生まれのぼくはその焼け野原を知らない)。バブル崩壊後現在(=いま)に連綿と続く原風景も多くの日本人にとってどこか焼け野原に近いイメージを抱かせるものなのかもしれない。頼るもののない、荒れた土地。瓦礫の街。そうしたなかで、世界中の女の子だけが能動的な生き方として「カワイくなりたい。カワイく生きたい」と願いそれを実践している。人はそれを安易にロリータファッションとのみ定義づけ括ろうとして安心しようとしたりするのかもしれないが。でもこの女の子たちの感性パワーは今を生きることをめぐる結構ほんものの呼び声や価値観に近いなにかなのかもしれないとぼくは思う。
戦後、焼け野原だけが残ったといわれる(もちろん戦後生まれのぼくはその焼け野原を知らない)。バブル崩壊後現在(=いま)に連綿と続く原風景も多くの日本人にとってどこか焼け野原に近いイメージを抱かせるものなのかもしれない。頼るもののない、荒れた土地。瓦礫の街。そうしたなかで、世界中の女の子だけが能動的な生き方として「カワイくなりたい。カワイく生きたい」と願いそれを実践している。人はそれを安易にロリータファッションとのみ定義づけ括ろうとして安心しようとしたりするのかもしれないが。でもこの女の子たちの感性パワーは今を生きることをめぐる結構ほんものの呼び声や価値観に近いなにかなのかもしれないとぼくは思う。 先々週末、箱根の某リゾートホテルに家内と一緒に宿泊に出かけた。ぼくの目的はリハビリを兼ねて温泉に浸かること、家内は以前から行ってみたいホテルだったらしいが、結果としてはアロマトリートメントを施術してもらい大いにリラクシングできてご満悦だったようである。因みに彼女自身も自宅でアロマを施術しているアロマセラピストである。ぼくにとっては大江戸温泉通いの延長としての温泉療養の意味合いもあった。そこは強羅温泉のエリアなので温泉の質も格段によかった。
先々週末、箱根の某リゾートホテルに家内と一緒に宿泊に出かけた。ぼくの目的はリハビリを兼ねて温泉に浸かること、家内は以前から行ってみたいホテルだったらしいが、結果としてはアロマトリートメントを施術してもらい大いにリラクシングできてご満悦だったようである。因みに彼女自身も自宅でアロマを施術しているアロマセラピストである。ぼくにとっては大江戸温泉通いの延長としての温泉療養の意味合いもあった。そこは強羅温泉のエリアなので温泉の質も格段によかった。 それから、吹き抜けのリビングフロアーの天井から長い筒のような煙突が下がっていて、その下に薪がくべられた暖炉があり、その爆ぜる音を聞きながらゆったりできることもとてもよかった。ふつう暖炉といえば部屋の隅のほうにあるものだろうが、そこではちょうどフロアーの真ん中に位置するように暖炉が設計されており、寛ぎにきた人たちが取り囲むようにしてその暖炉の火を眺めることになるのだ。グラスを一杯傾けながら、いつまでも飽きることなくその火を眺めながら談笑している泊り客のすがたも絶えなかった。こうした何でもないような設計にみえて、客本位への気配りといい、寛ぎを演出するその意匠の心づくしといい、やはり上質であったといえるだろう。
それから、吹き抜けのリビングフロアーの天井から長い筒のような煙突が下がっていて、その下に薪がくべられた暖炉があり、その爆ぜる音を聞きながらゆったりできることもとてもよかった。ふつう暖炉といえば部屋の隅のほうにあるものだろうが、そこではちょうどフロアーの真ん中に位置するように暖炉が設計されており、寛ぎにきた人たちが取り囲むようにしてその暖炉の火を眺めることになるのだ。グラスを一杯傾けながら、いつまでも飽きることなくその火を眺めながら談笑している泊り客のすがたも絶えなかった。こうした何でもないような設計にみえて、客本位への気配りといい、寛ぎを演出するその意匠の心づくしといい、やはり上質であったといえるだろう。 まさむねさんが{「ここはウソで固めた世界でありんす」とは僕らの台詞だ}のなかで語っているように、「世界に対する違和感、それは現代人に特有の感覚なのだろうか。それは、本当の自分はどこか別の場所に居るべきであり、今、ここに存在するのはウソの自分だという感覚」だけがたしかなものなのかもしれない。だとするなら、そうした不確かさのなかでヒトはより確からしいなにかにスガルしかない。それが唯一根っこのような時間というものなのだろうか。
まさむねさんが{「ここはウソで固めた世界でありんす」とは僕らの台詞だ}のなかで語っているように、「世界に対する違和感、それは現代人に特有の感覚なのだろうか。それは、本当の自分はどこか別の場所に居るべきであり、今、ここに存在するのはウソの自分だという感覚」だけがたしかなものなのかもしれない。だとするなら、そうした不確かさのなかでヒトはより確からしいなにかにスガルしかない。それが唯一根っこのような時間というものなのだろうか。 雑誌記事などによるとフランスで空前の日本ブームだという。空前というのがどの程度なのかよく分からないが、同じように日本ブームという意味ではちょうど150年くらい前の日本文化への嗜好(いわゆるジャポニズム)がこれに匹敵するのだろうか。今回の一連のブームのなかでは日本を題材にした小説も結構多く書かれているようだ。最近では本国フランスでベストセラーになったといわれている「優雅なハリネズミ」(これに登場するのは映画監督小津安二郎を思わせるような日本人オズが登場しているそうだ。ぼくはまだ読んでいないが。)という小説もあるらしい。ぼくも今年にはいって日本を題材にした一冊である「さりながら」(フィリップ・フォレスト著)を読んだことがある。夏目漱石、小林一茶、山端庸介(写真家)を主人公に設定しながら、コント風仕立ての枠組みを使って単に日本への関心にとどまらずに、自身の遺児への思いと重ね合わせながら哲学的な省察(同時代への考察)を試みている、抑制の効いた佳品だったと記憶している。
雑誌記事などによるとフランスで空前の日本ブームだという。空前というのがどの程度なのかよく分からないが、同じように日本ブームという意味ではちょうど150年くらい前の日本文化への嗜好(いわゆるジャポニズム)がこれに匹敵するのだろうか。今回の一連のブームのなかでは日本を題材にした小説も結構多く書かれているようだ。最近では本国フランスでベストセラーになったといわれている「優雅なハリネズミ」(これに登場するのは映画監督小津安二郎を思わせるような日本人オズが登場しているそうだ。ぼくはまだ読んでいないが。)という小説もあるらしい。ぼくも今年にはいって日本を題材にした一冊である「さりながら」(フィリップ・フォレスト著)を読んだことがある。夏目漱石、小林一茶、山端庸介(写真家)を主人公に設定しながら、コント風仕立ての枠組みを使って単に日本への関心にとどまらずに、自身の遺児への思いと重ね合わせながら哲学的な省察(同時代への考察)を試みている、抑制の効いた佳品だったと記憶している。 今回の日本ブームはアニメやゲーム、コスプレなどの従来のポップカルチャーのみならず、寿司、禅、焼き物、茶、相撲、歌舞伎など広範な事象への関心の広がりも特徴の一つのようだ(それらが紋切り型の理解であれどうあれ、理解のためには多少の紋切り型が必要だと思う。その意味でぼくは紋切り型について好意的に考えている)。
今回の日本ブームはアニメやゲーム、コスプレなどの従来のポップカルチャーのみならず、寿司、禅、焼き物、茶、相撲、歌舞伎など広範な事象への関心の広がりも特徴の一つのようだ(それらが紋切り型の理解であれどうあれ、理解のためには多少の紋切り型が必要だと思う。その意味でぼくは紋切り型について好意的に考えている)。 そうした中で日本人気はまさにアンビバレンスななかで起こっている。だがこうした海外での日本への評価・人気というものがどれだけ正しく日本に伝えられてきたかははなはだ疑わしい。TVによる報道に限っても世界のなかのクール・ジャパンについてわりと一貫して伝えてきたのはNHKくらいで、民放からこの手の継続的な報道ニュースがあったことをぼくはほとんど知らない。それからどうも日本人の傾向として自虐的に自己分析することはあっても、他人に褒められることに素直になれない性向があるのだろうか。自分たちの良いものを海外に評価されて始めて、そんなに凄かったのかと気づかされるようなところが往々にしてあるようだ。建築の例をとっても桂離宮などがその最たる事例だろう。逆にいえば日本人は自分たちに自信がないので、いつも外部評価(海外の目)を通じてしか評価づけることができない性なのだろうか。
そうした中で日本人気はまさにアンビバレンスななかで起こっている。だがこうした海外での日本への評価・人気というものがどれだけ正しく日本に伝えられてきたかははなはだ疑わしい。TVによる報道に限っても世界のなかのクール・ジャパンについてわりと一貫して伝えてきたのはNHKくらいで、民放からこの手の継続的な報道ニュースがあったことをぼくはほとんど知らない。それからどうも日本人の傾向として自虐的に自己分析することはあっても、他人に褒められることに素直になれない性向があるのだろうか。自分たちの良いものを海外に評価されて始めて、そんなに凄かったのかと気づかされるようなところが往々にしてあるようだ。建築の例をとっても桂離宮などがその最たる事例だろう。逆にいえば日本人は自分たちに自信がないので、いつも外部評価(海外の目)を通じてしか評価づけることができない性なのだろうか。 こうしたことのチグハグさもふくめて、依然日本の本質は変わっていないのかもしれない。ただ斜陽のなかでの日本ブームについて考えるとき、ついつい思い出してしまう映画の中のことばがある。その映画というのは鈴木清順監督の「チゴイネルワイゼン」で、もう大分昔に見た映画なのでその言葉をつぶやいたのが主人公の原田芳雄だったかもはっきりとは覚えていないのだが、たしか何か果物を食べるシーンで「なんでも腐りかけが一番おいしい」とつぶやくセリフがあったことを記憶している。
こうしたことのチグハグさもふくめて、依然日本の本質は変わっていないのかもしれない。ただ斜陽のなかでの日本ブームについて考えるとき、ついつい思い出してしまう映画の中のことばがある。その映画というのは鈴木清順監督の「チゴイネルワイゼン」で、もう大分昔に見た映画なのでその言葉をつぶやいたのが主人公の原田芳雄だったかもはっきりとは覚えていないのだが、たしか何か果物を食べるシーンで「なんでも腐りかけが一番おいしい」とつぶやくセリフがあったことを記憶している。 昨今の報道のサマを見ていると、国民の側も報道する側も、税金を取られるほうも取るほうも皆が皆でまとまって、国全体がもう病的なまでにお金の取り合いのことを考えるしかないような袋小路に追い詰められているようにみえてならない。清貧の思想が良いとは思わないが、どこかに、凛として、節度あり、いわゆる自分の分をわきまえ、ほどほどを知る、という引き算の姿勢があってもいいような気がするし(この主題についてはいつかまとまってまさむねさんと一緒に考察してみたいところだ)、一方もっと大きな視点で、つねにどこかに全体最適から考えていくような発想が抜け落ちていると、必ず瑣末な論議の積み重ねで、どこにも出口のない堂々巡りに落ちてゆくことになりかねないとも思えるからだ。
昨今の報道のサマを見ていると、国民の側も報道する側も、税金を取られるほうも取るほうも皆が皆でまとまって、国全体がもう病的なまでにお金の取り合いのことを考えるしかないような袋小路に追い詰められているようにみえてならない。清貧の思想が良いとは思わないが、どこかに、凛として、節度あり、いわゆる自分の分をわきまえ、ほどほどを知る、という引き算の姿勢があってもいいような気がするし(この主題についてはいつかまとまってまさむねさんと一緒に考察してみたいところだ)、一方もっと大きな視点で、つねにどこかに全体最適から考えていくような発想が抜け落ちていると、必ず瑣末な論議の積み重ねで、どこにも出口のない堂々巡りに落ちてゆくことになりかねないとも思えるからだ。 科学技術の事業仕分けに遭遇して、大学の総長たちが集まって危機感の表明会見を行おうと、ノーベル賞の学者先生があつまって反対意見を述べようと、そこに欠けているのは、ではあなたたちは大学教育をどう考えているのか、どうありたいのですか、技術立国というなら、あなた方はそのあるべき姿についてどうデザインしているのか、まずそれを大上段に愚直に常日頃から発信してほしいということだ。その一環で予算削減について批判的に述べるのならそれはそれでいい。だが、ぼくらの目に映るのは、まずもって「これ以上削られたらもう大変なんだ、大変なんだ、競争できなくなるんだ」という大合唱の光景のようにしかみえない。これで生活している研究者たちの暮らしをなんとか支えてほしいという願いが透けてみえるようで悲しい。科学する心の大切さを漫然と話されても心には響かないのだ。
科学技術の事業仕分けに遭遇して、大学の総長たちが集まって危機感の表明会見を行おうと、ノーベル賞の学者先生があつまって反対意見を述べようと、そこに欠けているのは、ではあなたたちは大学教育をどう考えているのか、どうありたいのですか、技術立国というなら、あなた方はそのあるべき姿についてどうデザインしているのか、まずそれを大上段に愚直に常日頃から発信してほしいということだ。その一環で予算削減について批判的に述べるのならそれはそれでいい。だが、ぼくらの目に映るのは、まずもって「これ以上削られたらもう大変なんだ、大変なんだ、競争できなくなるんだ」という大合唱の光景のようにしかみえない。これで生活している研究者たちの暮らしをなんとか支えてほしいという願いが透けてみえるようで悲しい。科学する心の大切さを漫然と話されても心には響かないのだ。 そもそもの何の疑いもないかのように、日本を技術立国と呼ぶこと自体があやしいものだとぼくは思っている。技術立国と呼んでいるその根拠について話せる人がどれだけいるのだろうか、なにをもって技術立国と定義しているのか。ハイテクの先端である半導体や液晶ディスプレイ産業を例にとるなら、製造業としての日本はもう上位の座を韓国、台湾のメーカーに奪われており競争力を失って久しい。携帯電話然り、PC産業然りである。かろうじてその川上に位置する部品産業はまだ競争優位を保っているようだが、需要の盛衰という意味では完全に新興国であるBRICs頼みの構図となっている。
そもそもの何の疑いもないかのように、日本を技術立国と呼ぶこと自体があやしいものだとぼくは思っている。技術立国と呼んでいるその根拠について話せる人がどれだけいるのだろうか、なにをもって技術立国と定義しているのか。ハイテクの先端である半導体や液晶ディスプレイ産業を例にとるなら、製造業としての日本はもう上位の座を韓国、台湾のメーカーに奪われており競争力を失って久しい。携帯電話然り、PC産業然りである。かろうじてその川上に位置する部品産業はまだ競争優位を保っているようだが、需要の盛衰という意味では完全に新興国であるBRICs頼みの構図となっている。 最近、骨折快癒後の腰痛リハビリを兼ねて大江戸温泉に通っている。大江戸温泉が果たして本当の温泉なのか、なぜ大江戸温泉通いなのかにはとくに深い意味はない。比較的家から近いという利便性と手ごろさというのが選んだ理由の一番だ。それに湯による癒しは確かに腰痛には良いようだ。因みに僕の住まいは大田区だが、京浜地区にも近いエリアでいわゆる城南地区ということになる。
最近、骨折快癒後の腰痛リハビリを兼ねて大江戸温泉に通っている。大江戸温泉が果たして本当の温泉なのか、なぜ大江戸温泉通いなのかにはとくに深い意味はない。比較的家から近いという利便性と手ごろさというのが選んだ理由の一番だ。それに湯による癒しは確かに腰痛には良いようだ。因みに僕の住まいは大田区だが、京浜地区にも近いエリアでいわゆる城南地区ということになる。 また無国籍化というと、ぼくも大好きなかつてのSF映画「ブレードランナー」(原作はフリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢をみるか?」)で描かれている未来都市のなかの屋台風景に通じるようなアジア的な混沌、猥雑なエネルギーみたいなものを想像したくなるが、お台場に代表されるのはそのような混沌とはおよそ対極にあるものだろう。むしろ無機的で人工的でそれがかもし出すどこか醒めた感じの匂いや距離感といったほうがより正確だろう。今では上海のガイタン地区に代表されるような中国沿岸部の成長性のほうが余程未来に通じる湾岸のイメージに近いであろうし、悲しいかなその意味で日本は国力の衰退をたどる以外に道はないともいえるかもしれないけど・・・・。
また無国籍化というと、ぼくも大好きなかつてのSF映画「ブレードランナー」(原作はフリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢をみるか?」)で描かれている未来都市のなかの屋台風景に通じるようなアジア的な混沌、猥雑なエネルギーみたいなものを想像したくなるが、お台場に代表されるのはそのような混沌とはおよそ対極にあるものだろう。むしろ無機的で人工的でそれがかもし出すどこか醒めた感じの匂いや距離感といったほうがより正確だろう。今では上海のガイタン地区に代表されるような中国沿岸部の成長性のほうが余程未来に通じる湾岸のイメージに近いであろうし、悲しいかなその意味で日本は国力の衰退をたどる以外に道はないともいえるかもしれないけど・・・・。 先週の日曜日に、彼が亡くなる直前までロンドン公演向けのリハーサルに打ち込んでいたときの収録ビデオを編集した映画「This Is It」を観た。この映画を見る限り、彼がその直後に死ぬ人とはとても思えないし(とても死期の近い病人のようには見えなかった)、死の直後に言われていたような公演のリハをほとんど行っていなかったという真らしきデマが嘘だったこともよく分かる。リハーサルの様子を観るかぎり、かなり完成形に近づいていたと思うし、公演への思いも本気だったと理解できるのだ。だとすれば、死因はやはり担当主治医の処方ミスということになるのだろうか。それは分からないが、ここではMJの死因について語ることが目的ではない。それはたぶん永遠の謎かもしれない。
先週の日曜日に、彼が亡くなる直前までロンドン公演向けのリハーサルに打ち込んでいたときの収録ビデオを編集した映画「This Is It」を観た。この映画を見る限り、彼がその直後に死ぬ人とはとても思えないし(とても死期の近い病人のようには見えなかった)、死の直後に言われていたような公演のリハをほとんど行っていなかったという真らしきデマが嘘だったこともよく分かる。リハーサルの様子を観るかぎり、かなり完成形に近づいていたと思うし、公演への思いも本気だったと理解できるのだ。だとすれば、死因はやはり担当主治医の処方ミスということになるのだろうか。それは分からないが、ここではMJの死因について語ることが目的ではない。それはたぶん永遠の謎かもしれない。 今回「This Is It」を観て、改めてMJの晩年の容貌について思うのだが、今更ながらなんと年齢不詳であることかということ! とても50歳の人には見えないよね。確かに芸能人やエンターティナーを職業としている人たちが年齢不詳、アンチ・エイジングで、いわゆる普通の人の年域を超えて若く見えるのは当然だとしても、彼の場合は単にそれだけではなく筋金入りで、元々その根っこの思想としても年を取ることを拒んでいたように思えるのだ。どこか中性的な感じ、なにか少年合唱団の面影をひきずり(ジャクソン5)、合唱団を卒業した後も去勢したように声変わりせずに高音域の声を残したまま、華奢で未成熟な肢体のイメージを醸し、白でも黒でもない人種の枠を超えて、少年、児童、玩具、遊園地が大好きで・・・・・等々。スクリーンの彼はますます人間離れしていて、なにか手足の長い宇宙人のように見えたものだ。MJはその後半生において宇宙からの使者、伝道師ETのようなものになったのかもしれない。
今回「This Is It」を観て、改めてMJの晩年の容貌について思うのだが、今更ながらなんと年齢不詳であることかということ! とても50歳の人には見えないよね。確かに芸能人やエンターティナーを職業としている人たちが年齢不詳、アンチ・エイジングで、いわゆる普通の人の年域を超えて若く見えるのは当然だとしても、彼の場合は単にそれだけではなく筋金入りで、元々その根っこの思想としても年を取ることを拒んでいたように思えるのだ。どこか中性的な感じ、なにか少年合唱団の面影をひきずり(ジャクソン5)、合唱団を卒業した後も去勢したように声変わりせずに高音域の声を残したまま、華奢で未成熟な肢体のイメージを醸し、白でも黒でもない人種の枠を超えて、少年、児童、玩具、遊園地が大好きで・・・・・等々。スクリーンの彼はますます人間離れしていて、なにか手足の長い宇宙人のように見えたものだ。MJはその後半生において宇宙からの使者、伝道師ETのようなものになったのかもしれない。 そういうなかでMJの音楽ももともと深まることはなく、表層を表層のまま奏でていった。その後半に至って、ヒーリング(癒し)、地球環境へのメッセージや愛、WE ARE THE WORLDのボランタリーなどの色彩を強めて移動してゆくかのように見えても、それらは深さによったものではないし、なにか年輪の智慧によって生まれたものでもないし、どこまでも単に彼の嗜好、オタクの一環としてくらいの意味しかないだろうと思う、本当のところは。時代が下降してゆくなかにあっては音楽的には僕はむしろマドンナの方が戦略的にしたたかな感じがする。先ごろWOWOWで見たブエノスアイレスでの2008年のマドンナのツアーはよかった。ギター片手に歌うマドンナがいい。草原のなかの兵士みたいで、ジャンヌ・ダルクのようでもあり、フィジカルで、シンプルで、身体的で、・・・・、等々。
そういうなかでMJの音楽ももともと深まることはなく、表層を表層のまま奏でていった。その後半に至って、ヒーリング(癒し)、地球環境へのメッセージや愛、WE ARE THE WORLDのボランタリーなどの色彩を強めて移動してゆくかのように見えても、それらは深さによったものではないし、なにか年輪の智慧によって生まれたものでもないし、どこまでも単に彼の嗜好、オタクの一環としてくらいの意味しかないだろうと思う、本当のところは。時代が下降してゆくなかにあっては音楽的には僕はむしろマドンナの方が戦略的にしたたかな感じがする。先ごろWOWOWで見たブエノスアイレスでの2008年のマドンナのツアーはよかった。ギター片手に歌うマドンナがいい。草原のなかの兵士みたいで、ジャンヌ・ダルクのようでもあり、フィジカルで、シンプルで、身体的で、・・・・、等々。