以前のまさむねさんのエントリー記事「ノルウェイの森、小説と映画におけるテーマの違い」(2011年1月2日)のコメント欄で以下のような僕自身のムラカミ・ハルキ脱落体験について記した。
ぼくの村上春樹体験は「ノルウェイの森」の登場で終わりました。それ以前にはマイナー・ポエットの同時代作家として好きでずっとリアルタイムで読んでいたのです。「風の歌を聴け」もぼくは群像の本誌で読んでました。「ノルウェイの森」はたしか100%の恋愛小説という本人直伝のキャッチコピーで当時売り出されてましたよね。読後感はこれで村上さんもメジャーな作家になったと思いました。それと同時に、これからはもうあまり読まないだろうと思いました。実際その通りになってしまいましたが。
僕個人のムラカミ・ハルキ体験はあくまでも個人的なものである。その脱落体験に果たしてどれほどの意味があるか、そこに普遍的な何かがあるかは分からないが、図らずもまさむねさんも同じような体験を持たれていたということが分かった(偶然にも!)ので、自分なりに過去の体験について少し思い返してみたい。
ノルウェイの森で終わっているので、ぼくの村上春樹像も上記に要約した通りで、今もそこから一歩も抜け出ていないとも言える。その意味ではなんら深化しているわけではない。ハルキ・ムラカミはぼくにとっては依然としてマイナー・ポエットの作家であり、それ以上でも以下でもなく、ある時代・ある雰囲気の中でもっとも時代の風のようなものを代弁してくれていた作家であった、ということに尽きる。
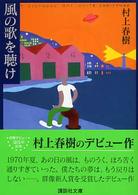 その時代とは特に80年代前半からバブル期の全盛前夜辺りまでとなる。「ノルウェイの森」が出版されたのは1987年で、「風の歌を聴け」が1979年に群像に掲載されたので、この間ほぼ10年近く、ぼくはずっと村上春樹の小説をリアルタイムで読んでいた。
その時代とは特に80年代前半からバブル期の全盛前夜辺りまでとなる。「ノルウェイの森」が出版されたのは1987年で、「風の歌を聴け」が1979年に群像に掲載されたので、この間ほぼ10年近く、ぼくはずっと村上春樹の小説をリアルタイムで読んでいた。
なぜ好きだったか? それは他の多くの作家が多かれ少なかれ自身の体験の重さや亀裂、あるいはその多寡によってどこか物語るような風潮がまだ残っていた中にあって(その代表が戦後の体験を小説にするような作家先生たちであった)、遅れてきた青年であるぼくらにとって、時代が透かして見せている何もないことの空虚さをそのまま代弁してくれていたからだったのではないかと思う。しかもストーリーテラーとしてはどこか未熟さが残り、どこか未完成の物語のにおいがして、そこが好きだったとも言える。
ぼくが高校生になったとき、すでに学生運動は終わっており、いわば宴の後だった。因みにぼくの出身高校はその当時某地方都市で最も学生運動が盛んな高校といわれていた高校だった。でもぼくが入学したとき、そんな運動は跡形もなく終わっており、それ以後もなにか社会全体の動きに巻き込まれていくような運動はいっさい起こらなかった。そういう時代である。
村上春樹さんはより正確にいえば、僕よりも上の、いわゆる全共闘や団塊の世代といわれる世代に属する。けれど、都市生活における消費することへのノスタルジーみたいなものや、全体として中流化・希薄化が進むなかでの空虚感のようなもの、そうしたオブラートのように纏わりついてくる些少なものへの目配せみたいなものをふくめて、村上さんの小説が持っている断片性がぼくを捉えていたのではないかと思う。その意味では村上春樹さんは徹頭徹尾、ぼくにとってはマイナーな作家であったのだ。
だが、「ノルウェイの森」の登場で、それは終わった。ぼくが変わったのか。村上春樹さんが変わったのか。どちらとも言えるし、どちらでもないかもしれない。ただ一つ言えるのは、ノルウェイの森はいかにも小説らしい小説の体裁になったということだ。大向こうの読者がたぶんより強く意識されるようになったとも言えるだろう。そして結末がどうあれ、小説は完成された物語の衣装に近づいたし、村上さん自身の小説家としての力量も成熟化したのだろう。
 けれど、そのことによって僕にとっては村上さんの小説がリアルなものではなくなったのだ。なによりも物語になりきれないその不全さを愛していたのだから、たぶん。「羊をめぐる冒険」も「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も然りだった。
けれど、そのことによって僕にとっては村上さんの小説がリアルなものではなくなったのだ。なによりも物語になりきれないその不全さを愛していたのだから、たぶん。「羊をめぐる冒険」も「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も然りだった。
またそれ以降の時代の流れということもおそらくあるだろう。やがて90年代を迎えてバブルがはじけ、現実がリアルに折り重なってくるなかで、その後僕自身も、仕事のことや自らの結婚や、人の死などにも直面し、いやおうなく自身のリアルに向き合わざるを得なくなったという現実的な理由もあるかもしれない。そうした中で僕個人の関心が完成された物語のようなもの、散文的なものから離れていったという嗜好の変化もあるだろう。
でも何も現実だけがリアルではないし、人はリアルさを感じるかぎりは付き合い続けるものだと思う。そういう意味でなら、ぼくにとっての90年代のリアルは、ハルキ・ムラカミの小説ではなく、「その男、凶暴につき」(89年)に始まり、「あの夏、いちばん静かな海」(91年)と「ソナチネ」(93年)を通って「菊次郎の夏」(99年)に至るまでの北野武の映画だったとも言える。
ぼくにとっての「ノルウェイの森」以降の村上春樹さんに対する雑駁な印象は、題材としてオウム真理教や阪神大震災や地下鉄サリン事件の擬似のようなものを選ぼうと、あるいは精神分析への興味・コミットのような形をとろうとも、彼の小説が醸し出すどこか書割的な事件性や物語性のイメージ臭に興味を失い(勝手な思いこみかもしれないが)、もう真に読みたい作家ではなくなったのだ。それは今日まで続いており、ぼくは「ねじまき鳥」も「海辺のカフカ」も「1Q84」も読んでいない。もちろんこの間にハルキ・ムラカミさんは世界的な作家になってゆくのだが。
 最後に、先のコメントで、ぼくは村上さんの小説には本当の意味で他者性がないかもしれないとも書いた。同じキャラクターの分身の物語ではないか、とも。じゃ、ぼくが感じる他者性のある小説とは何か。それはたとえば島尾敏雄さんが書いた「死の棘」という小説だ。ずっと昔に読んだのでもう細かいあらすじはすっかり忘れてしまっているけど、要は浮気をした主人公のおかげで気が変になってしまった(なりかかった)奥さんと、それにとことん付きあい付き添ってゆくしかない男の話。しまいには主人公の男も気が変になりかかるような、ふたりがふたりで病んでゆくような、どちらが快癒してゆくか分からないような、そんな決して切り分けることのできない現実のなかで生き延びてゆく日々を書き続けたもの。その不分明さ。そういうものこそ実は本当の他者性ではないかと最近のぼくは思っている。
最後に、先のコメントで、ぼくは村上さんの小説には本当の意味で他者性がないかもしれないとも書いた。同じキャラクターの分身の物語ではないか、とも。じゃ、ぼくが感じる他者性のある小説とは何か。それはたとえば島尾敏雄さんが書いた「死の棘」という小説だ。ずっと昔に読んだのでもう細かいあらすじはすっかり忘れてしまっているけど、要は浮気をした主人公のおかげで気が変になってしまった(なりかかった)奥さんと、それにとことん付きあい付き添ってゆくしかない男の話。しまいには主人公の男も気が変になりかかるような、ふたりがふたりで病んでゆくような、どちらが快癒してゆくか分からないような、そんな決して切り分けることのできない現実のなかで生き延びてゆく日々を書き続けたもの。その不分明さ。そういうものこそ実は本当の他者性ではないかと最近のぼくは思っている。
それに比べて村上さんの小説の登場人物たちはある種のスタイルとモードを守り、けっしてそこからはみ出すことがないようにも見える。でもこういうすべてのことは個人的な感想だ。冒頭に戻り繰り返しますが、僕個人のムラカミ・ハルキ体験はあくまでも個人的なものである。その脱落体験に果たしてどれほどの意味があるか、そこに普遍的な何かがあるかは分からない。当たり前だけど、人それぞれであり、人それぞれのハルキ・ムラカミさんがいるのだ。世界中に、今も。
よしむね
関連エントリー
2011.01.03 僕の妻が観たもう一つの「ノルウェイの森」
2011.01.02 「ノルウェイの森」、小説と映画におけるテーマの違い
2009.05.26 村上春樹とビートルズの「ノルウェイの森」における共通点
2010.07.15 原作を知る者なら、原盤を映画に起用するのは必然的ではない「ノルウェイの森」
よしむねさんへ
こんにちは。僕自身の小説体験と映画体験が、よしむねさんのそれと余りにも同じことに驚きます。
僕の90年代のリアルも北野武だったからです。そして僕は「ノルウェイの森」を最後に春樹を離れたのと全く同じく「菊次郎の夏」を最後に武を離れました。
春樹が何かをさらけだしているようで何かを隠しているのとは逆に、武は静かな画面に何かを剥き出しているように僕は感じました。
そして、自分の00年代のリアルは何だったのかと考えると、それは、その時のなんらかの作品というよりも、ビートルズ回帰と墓巡りという過去への憧憬とフィールドワークになったのかもしれません。
これに関しては、またいずれエントリー化したいと思います。
まさむねさんへ
ぼくにとっても同様に北野武は00年代のリアルではありません。北野武もHANA-BI以降、微妙に変質していったように思います。たぶん村上春樹さんと同様により制作に意識的になっていった(成熟化した)のでしょうか。そのことによってそれまで無意識に具現していた良かったものを失くしたのかもしれませんね。この辺は難しいですよね。人は変化してゆきますから。ぼくにとっての00年代のリアルについては答えはありませんが、その一つが「経済」だったかもしれません。月並みですが、その現場にいたという当たり前な切実さもありますが、それに翻弄されるようになったという意味でも。良い意味でも悪い意味でも。まさむねさんと同様に、もう何か特定の作家や作品ではなくなりました。時代が特定の何かを越えるようになってしまったのかもしれません。そんななかで大きい意味では何かへの「回帰」が自分にとってのリアルになってきたような気もします。まさむねさんの00年代のリアルをめぐるエントリー楽しみにしています。
よしむねさんへ
こんばんわ。よしむねさんがゼロ年代のリアルを現実社会の「経済」に感じられたというのは、ちょうど、もう一人のムラカミである龍の志向とも重なっていて面白いですね。
実は僕は春樹を「ノルウェイの森」で止めたのと同じ頃に「愛と幻想のファシズム」で龍も止めました。
また、話はかわりますが、「経済」という剥き出しの現実が、ゼロ年代に多くの人にとってリアルになったとしたら、その一方で自分にとってはプロレス→格闘技という断層にリアルを感じていたのかもしれません。
99年の馬場さんの死がファンタジーの終焉を意味していました。
そして、ゼロ年代前半はダラダラとプロレスと付き合っていましたが、後半は明らかに墓と家紋に深入りしたという感じでしたね。
今、振り返ってみると微妙に社会とシンクロしているようにも感じます。
それではまた。
まさむねさんへ
人がそれまで好きだったものと、どう別れていったかというのはとても興味深いテーマですね(好きだった女性と別れたというのとまったく同じように)。
村上龍さんはゼロ年代以降もJMMを立ち上げたり、「カンブリア宮殿」の司会をやったりして経済のリアルさに近いところにスタンディングされているかもしれませんが、ぼくにとってももうあまりリアルに感じられる人ではありませんね。「この国には希望だけがない」とか「半島を出よ」とか、あまりにもその時代の趨勢に合致するような上手い言葉を言い過ぎることにおいてリアリティーがないようにも思えてくるのです。言い方が失礼かもしれませんが、カッコ良過ぎるのです。何か時代に先んじる(?)オピニオンらしきものを言おう言おうというような意識が強すぎるような気がします。先んじる意識よりも「回帰」ということのほうが今は面白い気がします。