この間、知り合いのSさんにお会いした。Sさんは自ら情報戦略研究所を立ち上げて長くコンサルテーション等の仕事をされている、業界では著名な方だが、ここではSさんのイニシャル名に留めておきます。
お会いしたのはご相談したいことがあってだったのだが、いろんなご指摘を頂戴して「なるほどなぁ」と思うことしきりであった。さすが百戦錬磨、厳しい時代を自ら生き抜いてこられた方の言葉だけに重みがあります。そのいくつかをここで紹介してみたい。
「大事なのはRich Experience(豊かな経験)を与えることができるかどうか」
時代はもうソフトでもハードでもなく、あるメディアならそのメディアを提供することによってユーザーにどんな経験をしてもらいたいのか、どんな可能性(実現のイメージ)に誘いたいのか、いわゆるRich Experienceを経験してもらいたいのか、だということ。
アップルにあって日本企業にいま決定的に抜け落ちているもの、それが多分この視点だと思います、ということ。日本の多くの企業は、単なるハード屋かソフト屋に終わっている、あるいはそういう役割に甘んじてしまっている。人が求めているのは経験であって、単なるモノではないはず。
そして高邁なこころに高邁なものが宿るのです。スターバックスだって自分たちのことを単なるコーヒー屋だと思っているのではない。彼らの社員教育の徹底ぶりもすごいが、彼らはコーヒーを飲むことが世界の平和につながるという信念でビジネスをやっているのですよ。そこまで行かなきゃビジネスじゃありません。
「奪うのではなく、与えること」
いまの日本人の心性・心持はとても小さくなってしまった。みんな与えることをしないで、少ないパイから分捕ることばかり考えるようになっている。死亡老人の遺族による年金分捕りも然り。そしていま流行の中国頼みの姿勢も基本は同じで、みんな中国から分捕ることしか考えていないようだ。
でもこれは絶対にうまく行かない。中国人もしたたかだし、それよりもなによりも互いに与え合うことのなかで共に享受することを志向していかない限り、物事はぜったいにうまく行かない。いつか破綻する。だから単に中国からいかに分捕るかばかりを考えている現在のビジネスの多くはやがてうまく行かなくなるだろう。
「古いものや大きくなりすぎたものがやがて停滞して壊れるのはいい」
それは当然だから。問題は新しいものが生まれてこないこと。誰も正しいリスクをとらず新しいことにも挑戦しようとしないことのほうがはるかに損失なのです。
そして最後にSさんはこうおっしゃった。
「よしむねさん、ある程度の年齢になれば、どれだけ人に与えてきたといえるかでその人の価値は決まりますよ。いままでよしむねさんのおかげで育ててもらいましたといえる人をどれだけ持っているか、です。与えることが結果として相手から与えられることにつながるのです」
これにはぼくも答える術がなかった。グーの音もなかった。まったくおっしゃる通りだし、はたと自分の来し方を考えたときに、いままでぼくはどれだけの人になにかを与えることができただろうかと思ったからだ。「よしむねさんのおかげで育ちました」なんて言ってくださる殊勝な方がいるだろうか? だいいちぼくに与えられるものがあるだろうか?
疑問だ。だけどまだ遅くないか? これからぼくはもっと与えることを学んでいかなければならない、というよりもとにかく与えること、応援すること、そう強く思った。与えよ、さすれば与えられん、たとえ与えられなくても。
よしむね
 まさむねさんの「家紋主義宣言」についていろいろ咀嚼させていただきながら、ぼくなりにいろんな角度で考えさせて(バージョンアップさせて)もらっている昨今である。この週末プールに行ったのだが、そのプールサイドで山下達郎のベストを聴きながら、特に「夏への扉」を聞いていて思ったこと。これは家紋主義者の詞ではないか! との想い。
まさむねさんの「家紋主義宣言」についていろいろ咀嚼させていただきながら、ぼくなりにいろんな角度で考えさせて(バージョンアップさせて)もらっている昨今である。この週末プールに行ったのだが、そのプールサイドで山下達郎のベストを聴きながら、特に「夏への扉」を聞いていて思ったこと。これは家紋主義者の詞ではないか! との想い。
「夏への扉」はロバート・A・ハインラインの作品で、ぼくの学生時代に仲間たちはみんな読んでいたし、ご存知のとおりSF作品のなかでファン投票をすると必ずトップに近いランキングを得る、あまりにも有名な、有名すぎるというような作品だ。ここには未来、過去、タイム・トラベルなど、メジャーすぎるような動線や伏線、フィギュアやキッチュが沢山ある。
曲の「夏への扉」は同名の小説のモチーフをそのまま踏襲した、作詞吉田美奈子、作曲山下達郎の作品。リリースされたのは1980年。ぼく個人の好みだけど「夏への扉」は山下達郎の曲のなかでベスト3に入れたくなる好きな曲のひとつだ。青い空をバックにこの曲を聴いていると、ほんとうにこれは夏の家紋主義ではないのかなあと思ってしまう。「夏の家紋主義」とはまさむねさんに断りなくぼくが勝手に仮称したもの。以下にその歌詞の一部を引用する。
ひとつでも信じてる
事さえあれば
扉はきっと見つかるさ
もしか君今すぐに
連れて行けなくても
涙を流す事はない
僕は未来を創り出してる
過去へと向かいさかのぼる
そしてピートと連れ立って
君を迎えに戻るだろう
特に「僕は未来を創り出してる過去へと向かいさかのぼる」という歌詞。そして扉はたとえば家紋。ぼくらは過去へさかのぼることで、たぶんなにかと連れ立って現在に戻ってくるのだ。
夏の小道、せみの声、それぞれにとっての家紋、紋様。本当はそれはどのようなものであってもいい。その手がかり、物語の原型のようなもの、の一つ一つ。それらを携えてぼくらは過去から続いてきた道を知る(辿りなおす)ことができるのだ。
夏の、家紋主義。ふとそんなことを思った。
もうすぐ8月15日がまたやって来る。これもひとつの家紋、家の門にちがいない。
よしむね
まさむねさんに「Body主義は家紋主義と対極にあるのかもしれない」というご返事の文章をいただいた。その中でまさむねさんが引用していた山田先生の「自分の仕事と家庭が流動化している現在、自分の肉体のみが、自分が生きている間続く唯一の自分の「持ち物」となる。自分が自分であるところの拠り所」という箇所。これなどは個がむき出しになっていてもはや頼るべきものがない現在のなかで、良い悪いは別にしてかろうじて自分を確認するために身体や暴力しかなくなっていることにも通じているのかもしれない。
時代はデジタル放送とか3D元年とかハイビジョンとか、とかく映像的なものが持てはやされるようなキライがなくもないが、実はその一方で今後ますます身体的なもの(取り残された身体)が横溢するシーンが増えてゆくかもしれない。マッチョや健康志向の身体ということではなく、実は身体こそもっとも不自由なもの、意のままにならないものとして再認識される可能性もあるように思うのだ。そういうものとしての身体、Bodyの再確認の必要性があるようにも思う。これはアメリカ流のBodyの文脈とは違うものとして。
それからすでに20世紀の後半以降21世紀を迎え、時代は紛れもなくアーカイブ(記憶)の世紀に入ったのだとぼくは思っている。どちらかと言うと20世紀前半からその終わり近くまでは映像の世紀(特に大衆映画とTVの登場以降)と定義できるとするなら、20世紀の最後の10年間以降からはむしろ記憶の世紀に重きが移ってきていると思う。PCや携帯電話やデジカメ等の新しいパーソナル・メディアが登場してから、ぼくらは意識するしないにかかわらず日毎夜毎に膨大なデータの蓄積と個人の履歴にさらされるようになっている。そして自分たちではその一々についてもはやどうにも意味づけできないためにとりあえずすべてを保存(アーカイブ)しておく必要性が生じてきている。
もっと大げさにいうなら、人類全体がやっぱり「われわれはどこから来たのか、どこへ行くのか、われわれは何者なのか」をいろんな角度で知りたがるということ。今、世界遺産にかぎらずいろんな遺産がブームになってきているように思うのだ。仏像ブームにしろ平城京遷都1300年にせよ、環境や自然保護にせよ、いろんな履歴が横溢しているなかで、一度われわれの遺産が何だったのかを検証しておく必要性のようなもの。それが高まってきていると思う。膨大なデータ(記憶や遺産)が増えつつあるなかで間違いなくアーカイブの整理が主題になってきていると思えるのだ。もちろん個人単位を越えて、だ。
そしてそのひとつの寓話(整理整頓の手法の一つ)を汲み取るものとして、上記の風潮のなかに家紋主義が交差してくるポテンシャルがあるとも思えるのだ。まさむねさんが言うようにたしかに「日本人は代々続く家系という物語を失ったからBodyに関心を持つようになった」。また成長という神話ももはやその命脈は尽きかけている。それはそれで仕方ない。
だが、その一方でだからこそより多様なかたちで「われわれはどこから来たのか、どこへ行くのか、われわれは何者なのか」を知るための手がかりが再び求められてくるようになるとも思える。自らのクラシック(古典)や過去などの来歴を知ること。帰り道を確認するための作業として。そのすべてに答えられるわけではないけど、その一隅を照らすようなものとして家紋主義が時代に交差してくるひとつの意味がある、とぼくは思う。だからこそ、あらためて時代は家紋(家紋的なもの)を求めてきているのだ、と繰り返し言いたい気がするが、如何でしょうか。
よしむね
去年タバコを止めてから体重の増量が進んでいることもあって、夕飯を食べてから、時々ウォーキングをやるようになっている。コースはいつも決まっていて、家を出て、呑川の川べり近くまで行き、そこからターンして池上本門寺の正門へまわってけっこう急峻な参道を登り、寺の裏にまわって、その近辺を散策しつつ家にもどってくるコース。
正味だいたい40分くらいか。本門寺の近くなのでいわゆる周りは寺町でもあり、お墓もけっこう多い。山あり谷あり、アップダウンも充実しており(この辺りはまた坂が大変多い)、それこそ幼稚園からお墓、坂道まで人生の一式が何でも揃っているコースなので、ぼくは「人生の並木道」と勝手に呼んでウォーキングに励んでいる。ただし雨降りの日は行かず、飲み会等があったりすると当然行かないということであまり真面目でない部分もあり、とくに最近はW杯が始まってしまい、ご無沙汰傾向ではあるのだが。
コース途中の教会(大森めぐみ教会内の講堂、幼稚園と隣接)では、去年日野原重明先生の講演会があり聞きにいったことがあった。先生はその前日に韓国から帰ってきたばかりということだったが、なんとも元気な感じでとても98歳の人には見えなかった! さすがいろんな方がおられるものだ。
そういえば、知っているひとで100歳まで生きることを前提に生活設計を考えているとおっしゃっていた方もいたっけ。200歳の少女がヒロインのホラー映画も近々公開されるはず。それはさておき、梅雨の合間でもし今夜も晴れていたら、人生の並木道をまた歩こうかな。
よしむね
 たしかフランスの詩人ポール・ヴァレリーだったと思うが、「後ろ向きに未来に入る」という詩句があるそうだ。まさむねさんの「家紋主義宣言」がこの度めでたく発刊となったが、送っていただいた御本を拝読して、まさに上記ヴァレリーの言をまず思い出した。
たしかフランスの詩人ポール・ヴァレリーだったと思うが、「後ろ向きに未来に入る」という詩句があるそうだ。まさむねさんの「家紋主義宣言」がこの度めでたく発刊となったが、送っていただいた御本を拝読して、まさに上記ヴァレリーの言をまず思い出した。
やっぱりぼくら人間はゴーギャンの絵のタイトルじゃないけど「われわれは何者か、どこから来て、どこへ行くのか」を知りたがる生き物だ。そしていま過剰なまでに日本人が未来へ向かっての視線(眼差し)に晒されて痛めつけられているのだと思う。それは日本の将来性や未来のなさへ通じるような喪失感の予感でもあるだろう。グラウンド・ゼロの時代。
だが、未来ばかりを想い描こうとしても、未来からの視点だけでは多分たいしたアイディアは出てこないだろう、それよりもわれわれはどういう性(サガ)の人たちだったのか、何をしてきたのか、その来歴(後ろ向きに)を知ることがいまこそ必要なのかもしれない。
龍馬ブームにしろ、墓マイラー、歴女の興隆、アシュラーのブームにせよ、いわゆる「日本」が冠につく本の出版ラッシュにせよ、未来へ!未来へ!という視線の投げかけに疲れ、むしろ足元へ至る過去の道からもう一度見つめなおそうというある種の先祖がえりとけっして無縁な風潮ではないと思う。
そして今回「家紋主義宣言」を読んで、あらためてわれわれ日本人とは何者だったのかを強く感じさせられる契機ともなった気がする。家紋に託されたさまざまな物語、その紡ぎの数々。そこに何よりもまさむねさんの個人史も投影されている。
そして改めて確認させてもらったことは、家紋にまつわる意外なおおらかさや自由さということ。家紋が持つ広がりとは、かならずしも厳密な物語の公証性に基づくような類によるのではなく、あくまでもそこに自由な個人の思いがいつも許容されるスペースのようなものとして広がっているのだという事実。
それから家紋の種類の多さ、そのアイコン(イコン)としての面白さと秀逸さ。この家紋をめぐる象形性のひとつをとっても、以前ぼくも「デザイン立国・日本の自叙伝」の架空談義として書かせていただいたこととも相通じると思うのだが、日本人のデザイン感覚力(構想力)のDNAはやはりすごい!と思うのだ。そうしたことも本書を読んで気づかされたことだ。
ぼくは家紋主義宣言を読む前に、以下のような勝手な予感メールをまさむねさんに送らせてもらったことがある。それを原文のままここに引用してみる。
「日本人がいま自分のルーツ探しをしようとする時にあるいは{われわれはどこから来たのか}を知ろうとするときに家紋というのは有力なツールのひとつになりえるように思われます。
何でもありの時代だからこそ何も手がかりのない時代でもあるわけでそこに物語性としての家紋の意義があるようにも思われます。おっしゃられるように見えない制度としての抑圧性については注意しないといけないと思いますが。」
「みんな物語がすでに死滅したことは了解していてもやっぱり想像力としての任意の物語性は求めているように思います。それとやはり身体性ということの関連でも妙に家紋の象形チックな紋様がマッチするようにも感じます。」
この思いは本書を読んだ後のいまも変わらない。というよりも21世紀を迎えて、あらためてますます家紋の潮流が新しい、と言えるように思うのだ。ぼくもまさむねさんとは古い付き合いで、途中の音信途絶の時期もいれてもうかれこれ20数年になる。
昨年から骨折を機縁に(?)一本気新聞にも合流させてもらってこうして書かせていただいているわけだけど、年齢の近しい同時代人として、このような書物が同世代のひとりの書き手によって出現したことを誇りに思うし、もっと多くの人の目に触れてほしいと思う。
本の帯にもあるようにこの本は21世紀に出版が予定されていたもっとも危険な書物の一冊かもしれない。読まれていない方があったら、ぼくが言うのもなんですが、ぜひ読んでいただきたいと思います。そしてまず自分と自分の家の歴史(先祖の人たちのことも)についてしばし想いを馳せてみてください。そこからはじめてみましょう。
因みにぼくの家紋は「細輪に中柏」の柏紋である。まさむねさん曰く、ぼくの先祖はアート感覚にあふれたおしゃれな方だったのかもしれませんね、とのご診断。それからぼくの家(先祖)の出は姓から推察しても京都あたりだったのでしょう、ということ。ただし、実際のお墓に彫られた家紋は間違っているのだが。この間実家に帰ってそれを確かめてきた。まあ、いずれにしてもこれも家紋にまつわるおおらかな物語のひとつかもしれない。
最後に、まさむねさんの「家紋主義宣言」の一節でぼくがもっとも好きな語句は次のことばだ。
「今ならば、まだ、僕らの「帰り道」はかろうじてそこに在るに違いないのである。」
文字通り、最終章、結びのことば。ひとの帰り道。それはそのままこれから行く道でもある。もう日が暮れて、道は遠くなってきていても(お家がだんだん遠くなる)、まだ帰り道があると信じたい。
まさむねさん、出版おめでとう!
よしむね
宮沢賢治が晩年を営業サラリーマンとして生きたことは意外に知られていないのではないか。「宮沢賢治 あるサラリーマンの生と死」(佐藤竜一著、集英社新書)はそのサラリーマン時代に比較的照準を合わせて書かれた本だ。
宮沢賢治についてはこれまで農業学校の教師や自ら農民となって活動したりという、いわゆる聖人ぽい紹介が多くなされてきたように思うが、晩年のサラリーマンとしての賢治像を読むと、長くモラトリアム青年であることをひきずり理想と現実の違いに悩み、病弱で転職を繰り返すような、どちらかというと現代の若者像とも交差する等身大の像に触れるようで共感を覚えた。
いま賢治が生きていたら、間違いなくブログやツイッターにはまっていたかもしれない。それにiPhoneやiPADにも。宮沢賢治はどこまでも未完成で、探し続ける実業の人という一面があったのだと思う。今でこそ詩人・童話作家として有名だが、存命中はもちろん無名に近く、生涯において原稿料は一度だけしか手にしたことがなかったという。
ぼくがサラリーマンとしての宮沢賢治に興味を感じるのは、もちろん自分が現にサラリーマンを生業としているということもあるし、世の多くの人がその生涯の大半を過ごす形態である以上避けて通ることのできない関心事であることにもよるが、それよりも複数の生としてのあり方に関する示唆のようなものを賢治の生き方に感じるからというのが一番の理由かもしれない。
回りくどい言い方かもしれないが、ぼくらは今後ますます多数的に生きてゆくほかないように思う。ネットの普及によってプロとアマの垣根が曖昧になりつつあるとはよく言われる。誰でもが自分が書いた小説や記事のたぐいをネットで公開することが可能になった。極端にいえばプロの新聞社に伍して個人でも新聞記事を書き、毎日配信することができる。
いっぽうプロとアマの間には依然として深い溝があり、いわゆるプロとアマの作家の違いには歴然としたものがある、という議論も成り立つだろう。ここでどちらが正しいというのではない。ただひとつ言えるのは、これからはプロとアマの間のグレーな部分がますます大きくなり、従来の既得権益に乗ったようなただの権威づけではもはやプロの定義にはなりえなくなるだろうということだ。もっといえば従来の境界を越えて、自由に行き来できるような感性のあり方こそがますます必要になると思われる。境界(クロスオーバー)の動きに鈍感なひとは多分何にせよもはやプロにはなりえなくなるだろう。
宮沢賢治の詩や童話がいまでも新鮮だとしたら、それはサラリーマンのような視点をけっして否定せずにむしろそこから書かれているからだとも言えると思う。なにかを特権視しないこと。書くことが偉いわけでも絶対でもないし、食べること、生活すること、楽しむこと、書くことを同じ視線で並べること。みんないろんなキャラクターに基づく複数の生を生きているのだ。
あるときは童話作家であり、詩人であり、法華経の信者であり、サラリーマンであり、広告マンであり、農業の実践者であるような生。そうした複数性こそが宮沢賢治の新しさであり、今も未来的な詩人に見える理由ではないかとおもう。
よしむね
 この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。
この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。
電子書籍とは異なる、従来からある紙の本の可能性についてはいずれ別の機会にあらためて書いてみたいと思っているけど、ここではいわゆる3DやiPADによって代表されるある種の万能感の感覚のようなものについてぼくなりにいま思うところを書いておきたい。
3Dにせよ、iPhone やiPADにせよ、極端にいえばぼくらはその登場によって以前よりも何でもできるような気になりつつあるように思える。つまりぼくらの身体を引き延ばした形での万能感のようなもの。しょせん端末等の力を借りてなのだが、自分の見る能力がとても高くなり、読む能力や、探し出して調べる能力がとても高くなりつつあるような錯覚。良い意味では世界共通としてのイマジネーション力に変化を及ぼす可能性もあるかもしれない。
でも、これはひとつの予感だけれど、ぼくらはある種の万能感が高まるような感じになればなるほど、その一方でますます自分のなかの無能さや無能力さ加減を体感することに飢えるようになるのではないか。
 いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。
いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。
それは高校の地学だったかで習ったアイソスタシーの原理のようなものでもあるかもしれない。海のうえに浮かんでいる氷山は海面から出ている氷の量が多いだけ海面下の氷塊もまた比例して多くなっているという。だから世をあげての万能感が高まれば高まるほど海面下の無能感も高まる・・・。
やっぱり身体のセンシビリティーこそがますます大事になるように思える。理屈ではうまく言えないけど、いわば自分の無力さを肌実感できるような能力こそがとても大事になると思えるのだ。まさむねさんも以前恋々風塵の映画評のなかで述べていたけど、以下の文章にはぼくもまったく同感だ。
「おそらく、センシティブ(感度が高い)というのは自然に対して、こうした悠久の流れ、すなわち山の霊を感じ取れることだと思う。けっしてアップル社の新製品に飛びつく器用さではない」
 だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。
だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。
けっきょく読む、聞く、書く、走る、歩く人間の素の能力なんて2000年まえとたいして変わっていないかもしれないのだから。
よしむね
 まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。
まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。
もう細かいことやあらすじについては触れない。ただあのラストで、お爺さんと主人公が言葉を交わす(実はあまり交わさない)シーン。山の気に包まれたなかで、お爺さんは失恋した主人公に対して仔細はなにも尋ねず、ただ今年はさつまいもが不作だとか良くできたとか、そんな話をするだけだ。お爺さんは多分分かっているのだけど、なにも言わない。
 誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。
誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。
こんなシーンに出会えたことのなんという至福! 映画を観るとはまさにこういう瞬間に出会うことだと思わせてくれた、そういう作品。
人を好きになることはときに悲しい。ぼくももうあの少年少女たちからは遠く離れたところに来ているけど、今もときどきこの映画のいくつかのシーンを思い出す。切ないことや思いっきり楽しかったこと、ワルをしたり、そんなこんな誰にでもあったに違いない小さな出来事の数々。今も恋々風塵は走馬灯のようにそれらを浮かべて回っているのだと思う。
よしむね
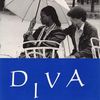 ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。
ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。
今回あらためてビデオで見なおしてみたのだが、ストーリ自体には少しも古い感じがしない。出てくるパリの風景や女性の服装や髪型にはさすがに80年代のものを感じる部分もある(メディアとしての録音テープ等もそうである)が、奇妙な味わいといい、スタイリッシュな映像や、妙な可笑しさといい、誤解を恐れずにいえば3Dという話題性があるにせよ画一的な作品であるアバターなんかよりもよほど飽きない。サスペンスフルで奇妙でスタイリッシュで恋愛的でと、なんでもある。主人公とディーバが連れ立ってデートする雨のなかの寡黙なシーンなんかとても良い。けっして平板ではない。こうした映画をみると、80年代の映画ってやっぱり面白かったなと思う。
 しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。
しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。
当時この映画をみて、東京でもまったく違和感のない、共振する時代感覚のようなシンパシーを感じたのを覚えている。それから余談だけど、ぼくはこの映画ではじめてカタラーニのオペラ「ワリー」を知って、なんて素晴らしい曲なんだと思ったものだった。今ではサラ・ブライトンなんかがさんざん歌っているので、とても有名になってしまったと思うけど。
いろんな意味で2010年になって時代はふたたびディーバに追いついたのかもしれない。
よしむね
 最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。
最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。
たしかに実体経済レベルでは一時の最悪期(去年の春前後)を過ぎつつあることは事実かもしれない。ぼくが身を置いているハイテク関連業界でもかなり忙しい状況になっている。自動車業界、半導体や電子部品業界、精密機器業界、工作機械業界然りだろう。いわゆる実体経済といわれる部分については製造業という観点からみればかなり忙しくなってきていると思う。それもまるでジェット・コースターのようにダウンしたと思ったら急にアップし始めて、猫も杓子もという感じだ。ここに来て急にみんな一斉に、という感じかもしれない。
でも、果たして、と思ってしまう。これが実体というものだろうか? ある意味で実需に根ざしていると思われる実体経済がこんな風に急激に萎んだり膨らんだりするものだろうか。結局実体経済もきわめて虚の経済(レバレッジの効いたバブルチックな経済)に似てきているということなのだろうか。これがグローバルの正体なのかもしれない。悪くなるときはみんな一斉に悪くなり、良くなるときも一斉に良くなるように映って見え、世界での自動車やパソコンや携帯電話や液晶TVの売れ行きにすぐに左右され、みたいな・・・・。
結局グローバル化が進んだことで、経済というものがますます薄っぺらになり、何処も彼処も似たようなトレンドを受けざるを得なくなったということ。その意味で経済そのものに厚みがなく、奥行きや深みがなくなったのだろう。リーマンショック以後、ほんとうは従来の虚の経済から脱却しようという(それを考える)良い機会だったのかもしれないのだけど、やっぱりみんなは喉元すぎれば熱さを忘れるで、バブルチックなものが恋しいのである。というよりも裏返せば今の経済原理そのものがなにかのバブルなしには成立しにくくなっているということでもあるのだろう。麻薬なしでいられない患者たちが増えているのだ。
 でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?
でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?
今騒がれているギリシャに端を発したヨーロッパの経済危機にしても、誰かにババを引かせようとしているゲーム漬けの人たちの策略としか思えない。ギリシャだけが極端に悪いわけではない。借金漬けという意味では実体はアメリカも英国も似たようなものだ、もっと悪いだろう。だいいちユーロよりも米ドルが安全なわけがないじゃないか。
でも、まあこれくらいにしておこう。世の中が変わるときはたぶん一直線ではなく、蛇行しながら変化してゆくのだ。これは以前まさむねさんが小沢一郎について書いていた記事(1月28日)でも述べていたことと同じだけれど、ぼくもまったく同感だ。
人間はホモ・エコノミクスでもあるとおもうけど、でもやっぱり「パンのみに生くるにあらず」もほんとうだ。お金なしでは生きられないが、いかにお金や経済の起伏と上手に別れていけるかも考えていきたい、そう思う。
よしむね
Just another WordPress site

 この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。
この週末の金曜日、日本でもiPADが発売になった。3D元年といい、すでに発売されていた電子書籍キンドルの登場とあわせて、グーテンベルグによる印刷の発明以来の、メディア文化の変容の可能性を指摘するような論調の取り上げかたもけっこう多いようだ。 いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。
いながらにして何でも手に入り、なんでも見れるような気になればなるほど、逆に自分で実際に歩いて、ものを触り、体感することへの渇望みたいなもの。そしていかに自分が無力であるかを実感すること。それを身体感覚で確認すること。その必要性がバランス感覚に促されるようにますます高まってくるように思える。 だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。
だから逆説的だけど、3DやiPhoneやiPADが出てもそれだけではなにも変わらないのだ。大事なのは最後はやっぱり身体のセンシビリティーで感じること(それはたとえば今日の風はとても気持ちがいいでもいい)、そしてマルクスやランボーの言葉じゃないけど、そのことを通じて「生活を変えよ、変革せよ」という日々の考え方みたいなものにつなげてゆくこと、それこそが今でも未だにもっともリアルであり続けていると思うのだが。 まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。
まさむねさんとなるべく重ならないように80年代の映画について取り上げる予定なのだが、この「恋々風塵」だけはちょっと例外ということで、ぼくも書かせていただくことにした。というのももし今まで見た青春(恋愛)映画でベスト3を上げろと言われたら、間違いなくそのひとつにこの映画を上げるだろうからだ。とても好きな映画だ。 誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。
誰もどうすることもできないからだ。ただみんなそうしてきたように、ひとりで黙って泣くしかないし耐えてゆくしかない。映像はどこまでも静かで凛としている。そしてもの悲しい。山の気の張り詰めたような美しさ。老人と青年のふたりだけがいて・・・。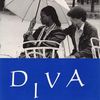 ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。
ジャン=ジャック=ベネックス監督の作品。この監督の作品では「ベティー・ブルー」も有名だが、ぼくは「ディーバ」のほうが好きだ。公開は1981年でたしか六本木シネ・ヴィヴァンで上映されたと思うが(この辺は記憶が曖昧)、公開時に観た。 しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。
しかも今回改めて気づいたのは、ベトナム人の女の子が出てきたり、ギリシャ人の謎の男や黒人であるディーバ(歌姫)が出てくるところなど、いわゆるパリの中の異邦性がすでに映画として取り上げられていたこと。今でこそというか90年代くらいからはヨーロッパに旅行してもパリやロンドンなどの大都市での黒人の多さが当たり前に目につくようにはなっていたと思うけど、80年当初からフランス映画の中でこんな風に都市のなかでの異邦性や無国籍性を取り上げたものはあまりなかったようにも思う。その意味でも先駆的。 最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。
最近、新聞紙上でけっこう経済が復調しつつあるような記事が目に付くようになった。前年比でやれ何%増益の企業が増加してきたとか街角景気の改善とか見通しの引き上げとか、等々。 でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?
でも、果たしてとまた思ってしまう。リーマンショック以後の今の金融業界のみかけ上の復活って、ほんとうは証券業界が作ったジャンク債(ボロ屑と消える運命にある債券の群れ)の借金を国が肩代わりして、いっとき誤魔化しているだけじゃないだろうか。依然何も解決していないわけで、いずれこのかりそめのバブルも弾けるときが近いのでは?