北京五輪の野球の結果は誠に残念だった。
敗因はいろんな解説者が出し尽くした感があるので、ここで素人の僕が付け加えることは特に無い。
ただ、気になったのは星野監督の、己のドラマに対するこだわりだ。
決勝戦、3位決定戦での采配ミスに関して、彼は、テレビインタビュー(ZERO 8.25)でこう述べている。
質問「選手起用ついてお伺いしたいんですが、調子が良くない、あるいはミスした選手、実名を挙げますとGG佐藤選手ですとかピッチャーで言うと岩瀬投手、準決勝であまりよくないパフォーマンスの中で3位決定戦でも使い続けました...」
星野「はい、言われますね。これが私のやり方なんです。挽回させてやろう。もう一回チャンスを与えてやろうという。一度や二度、失敗したからと言って、という...(後略)」
このやりとりを聞くにつけ、星野監督は、勝負にこだわる以上に「部下思いのいい上司でありたい」という自分と、期待を意気に感じて大活躍する選手との感動的なドラマに、取り付かれれて生きるタイプの人間と思わざるを得ない。
その直後、キャスター氏は当然のごとく以下の質問を続ける。
質問「それは、僕は長期決戦だったらわかる気もするんです。ただ短期決戦の場合には、そうも言ってられないじゃないかなと私なんかは思ってしまうんですが。」
星野「そうなんですけれども、代わる選手がいないんですよ。正直言って。体調面を考えるとか、台所事情が。その苦しさはありましたね。え~。」
だったら、最初から正直に、現実を言えばいいではないか。しかし彼は、上記の判断を己の美学として語ろうとするのだ。
しかし、五輪という場は残酷だった。
戦いの最中には、星野的ドラマが入り込む余地は無かった。
そこに必要なのは、勝利を得るためのリアリズムのみであった。
そして、ドラマは勝った者のみが許される特権である。
例えば、フェンシングの太田選手や体操の内村選手、柔道の石井選手を見るまでも無く、彼らは勝利したがゆえに、ドラマを手に入れることが出来た。そして、マラソンの土佐選手や柔道の鈴木選手はドラマを作ってもらえなかった。
一方、星野監督は上記のように、ドラマを己で演出するようなタイプの人間である。すなわち、ドラマ体質の人なのだ。
勿論、それはプロとしても稀有な才能だ。だから彼は成績は超一流ではなかったが、男・星野の反骨精神というドラマを武器に、全日本の監督にまでのし上がることが出来たのだ。
しかし、彼は五輪の監督しては、あまりにもファンタジックではなかったのか。
あの準決勝と3位決定戦の惨敗を目の前にして、かつて、プロレスラー達がリアルファイトのリングでボコボコにやられ続けた。あの風景を思い出してしまった。
まさむね

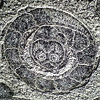 家の近所にあった何気ない共同墓地で、家紋の観察(採取)を行った。
家の近所にあった何気ない共同墓地で、家紋の観察(採取)を行った。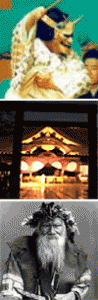 以前、書いた「悪い人なんていない。已むに已まれず暴力を振るってしまった人も本当はいい人に違いない。」という思想に関して考えた。
以前、書いた「悪い人なんていない。已むに已まれず暴力を振るってしまった人も本当はいい人に違いない。」という思想に関して考えた。