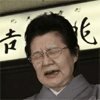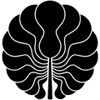内田けんじ監督、大泉洋、佐々木蔵之助、堺雅人出演の「アフタースクール」を見た。
はっきり言って、私の理解力では、1回見ただけだとよくわからないディテールが多かったが、この話がどういう価値観に基づいているのかということはおぼろげながら、解釈することが出来た。
ここでぶつかっているのは、佐々木蔵之助扮するチンピラが体現している実社会的・経済的価値と、大泉洋が体現している学校的価値だ。
話の途中で、小利口なチンピラ(佐々木蔵之助)が中学教師(大泉洋)を「この世間知らず!、早く中学、卒業しろ」と罵倒するが、最終的には、逆に「どこのクラスにもお前みたいな奴はいるよ。つまらんつまらんと言いながら他人のせいにばかりしている。」と反論される。
詳細の展開(この映画での一番の面白いストーリー)は省略するが、結局のところ、この映画は、中学時代的価値である初恋、友情、勤勉、正義といった価値が勝利する映画である。
最近、メディアでは学校で教える事や、教科書に書いてある事には価値が無い的な言説がはびこっているが、俺的は、今後は、個人的なレベルでは、スタンダードな人々の地味な価値観こそ再評価されるべきだと思うし、その意味で、この映画は、評価に値すると思う。
まさむね