コチラのページに移動しました。
タグ: 家紋
菱紋 -武家の正統としてのプライドと信玄の威光- 武田信玄、高杉晋作、森進一...
10秒後、新ページに自動移動します。移動しない場合は、コチラをクリックしてください。
梅紋 -菅原道真の怨霊を封じ込めた紋- 前田利家、岡本太郎、菅直人...
コチラのページに移動しました。
菊紋 -後鳥羽上天皇の意地が生み出した優美な紋- 西郷隆盛、夏目漱石、野口雨情...

天皇家が菊紋を使用し始めたのは、後鳥羽上皇の頃からだといわれている。
後鳥羽天皇(後の上皇)は、平氏が持ち去ったため、三種の神器が無い状態で即位せざるを得なかった。
後に、神器のうち、勾玉と鏡は戻ったが、本物の剣は壇ノ浦に沈み、戻ることは無かったのである。
しかし、剣の無い天皇は、刀を打つ事を好み、自分専用の鍛冶場を庭に創らせたという。
さらに、力で幕府を倒そうと承久の変を起こしたが、失敗し、隠岐に流され、その地で崩御。
おそらく、天皇の刀へのこだわりは、剣無しで即位した自分の正当性に対するコンプレックスへの補償行為だったのではないだろうか。
 そして、天皇は、自分の刀に優美な菊の紋章を入れた。
そして、天皇は、自分の刀に優美な菊の紋章を入れた。
台頭する武家文化に対抗べく王朝文化の最後の維持をこの紋章に込めたのである。
その後、この菊紋は天皇を象徴する紋となる。
江戸の時代こそ、一般庶民にも広まったこの紋であるが、明治になると国家主義とも結びつき、権威を持った。
比較的多い地域は東京都(24位)、宮崎県(25位)、愛知県(27位)、北海道(28位)。茨城県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、広島県、福岡県で29位。
さて、菊紋を用いた有名人であるが、以下の通りである。

 楠木正成 。1294年 – 1336年7月4日、 南北朝時代の河内の武将。
楠木正成 。1294年 – 1336年7月4日、 南北朝時代の河内の武将。 河内国石川郡出身。伊予橘氏の橘遠保の末裔。建武の新政の立役者として足利尊氏らと共に活躍するが湊川の戦で敗れ自害。明治以降大楠公と称される。後醍醐天皇から下賜された菊紋を菊水紋として使用。画像は楠木家の菩提寺・楠妣庵観音寺の菊水紋。

 由井正雪 。1605年 – 1651年9月10日、 軍学者。
由井正雪 。1605年 – 1651年9月10日、 軍学者。 静岡県清水区由比町の紺屋の子として生まれるが、江戸へ奉公に出て楠木正成の子孫の軍学者・楠木正辰の婿養子となる。神田連雀町に軍学塾「張孔堂」を開いた。「慶安の変(由井正雪の乱)」を起こし駿府にて自害。菊水紋は養子先の楠木家の家紋。

 江川英龍 。1801年6月23日 – 1855年3月4日、 幕臣。
江川英龍 。1801年6月23日 – 1855年3月4日、 幕臣。 伊豆国韮山出身。伊豆韮山代官・江川英毅の次男。通称は江川太郎左衛門。読みは、えがわひでたつ。洋学とりわけ近代的な沿岸防備の手法に強い関心を抱く。反射炉を築き、日本に西洋砲術を普及させた。家紋は井桁に十六葉菊紋。

 増田甲斎 。1820年 – 1885年5月31日、 ロシア外務省の役人。
増田甲斎 。1820年 – 1885年5月31日、 ロシア外務省の役人。 遠江国掛川出身。藩士・立花四郎右衛門の次男。読みは、ますだこうさい。ロシアに密航を企てる。ロシア正教会に改宗後、ロシア外務省の役人、ペテルブルク大学の日本語の講師となった。家紋は十六菊に三つ引両紋。画像は高輪源昌寺にて撮影。

 得能良介 。1825年12月18日 – 1883年12月27日、 武士、官僚。
得能良介 。1825年12月18日 – 1883年12月27日、 武士、官僚。 薩摩国鹿児島城下新屋敷出身。薩摩藩士・得能直助の長男。維新後、大久保利通の推挙によって大蔵大丞兼民部大丞に任じられる。その後、司法大丞、印刷局長、初代大蔵技監等を歴任。家紋は丸に三つ割菊に三の字紋。画像は青山霊園の墓所にて撮影。

 外島機兵衛 。1826年7月5日 – 1868年3月30日、 会津藩士。
外島機兵衛 。1826年7月5日 – 1868年3月30日、 会津藩士。 会津出身。藩士・堀藤左衛門の次男。外島家の養子となる。藩主・松平容保に従って上洛。鳥羽・伏見の戦いでは兵糧などの調達にあたる。家紋は菊水紋。画像は青山霊園の墓所にて撮影。顔画像は、テレビドラマ「白虎隊」で機兵衛を演じた大河内浩。

 那珂通高 。1827年 – 1879年5月1日、 折衷学派儒学者。
那珂通高 。1827年 – 1879年5月1日、 折衷学派儒学者。 盛岡藩藩医江幡道俊の次男。読みは、なかみちたか。戊辰戦争後は奥羽越列藩同盟参加藩の幹部として責任を問われるが、維新後は大蔵省・文部省に出仕して「古事類苑」「小学読本」編纂に携わる。家紋は十六菊に一の字紋。青山霊園の墓所にて撮影。

 西郷隆盛 。1828年1月23日 – 1877年9月24日、 藩士、政治家。
西郷隆盛 。1828年1月23日 – 1877年9月24日、 藩士、政治家。 薩摩藩の下級藩士・西郷吉兵衛隆盛の長子。薩長同盟の成立や王政復古に成功し戊辰戦争を巧みに主導した。大久保利通や長州藩の木戸孝允と並び維新の三傑と称される。家紋は天皇より下賜された抱き菊の葉に菊紋。元の家紋は鷹の羽とも言われる。

 木戸孝允 。1833年8月11日 – 1877年5月26日、 武士・政治家。
木戸孝允 。1833年8月11日 – 1877年5月26日、 武士・政治家。 長門国萩呉服町萩藩医 和田昌景の長男として出生。桂家の末期養子となる。尊王攘夷派の中心人物。西郷隆盛、大久保利通とともに維新の三傑として並び称せられる。桂小五郎時代は丸に三つ星紋。画像は多磨霊園にある類縁・木戸幸一の墓所にて撮影。

 松方正義 。1835年3月23日 – 1924年7月2日、 薩摩藩士、政治家。
松方正義 。1835年3月23日 – 1924年7月2日、 薩摩藩士、政治家。 薩摩国出身。第4代、6代内閣総理大臣。大蔵卿時、緊縮財政を行い深刻なデフレ(松方デフレ)を招いた。私生活では26子を儲け、長與專齋、岩崎家、山本権兵衛、森村市左衛門等と婚姻関係を結ぶ。家紋は抱き菊の葉に抱き茗荷紋。画像は青山霊園。

 永山武四郎 。1837年5月28日 – 1904年5月27日、 陸軍軍人。
永山武四郎 。1837年5月28日 – 1904年5月27日、 陸軍軍人。 薩摩国出身。藩士・永山盛広の四男。北海道庁長官となり、北海道の開拓と防衛に情熱を傾け、「屯田兵の父」と呼ばれた。軍人としての最終階級は陸軍中将。家紋は丸に抱き菊の葉に剣四つ星紋。画像は青山霊園の弟・永山盛輝の墓所にて撮影。

 西郷従道 。1843年6月1日 – 1902年7月18日、 海軍軍人。
西郷従道 。1843年6月1日 – 1902年7月18日、 海軍軍人。 薩摩藩鹿児島城下加治屋町出身。西郷隆盛の弟。伊藤博文内閣の海軍大臣、内務大臣などを歴任。妻、清子は得能良介の長女。四男は上村彦之丞、六男は小松家の嗣養子。最終階級は元帥海軍大将。家紋は三つ寄り菊葉紋。画像は多磨霊園の墓所にて撮影。

 高島鞆之助 。1844年12月18日 – 1916年1月11日、 陸軍軍人。
高島鞆之助 。1844年12月18日 – 1916年1月11日、 陸軍軍人。 薩摩国出身。藩士高島喜兵衛の四男。読みは、たかしまとものすけ。第1次松方内閣の陸軍大臣。最終階級は陸軍中将。大阪偕行社附属小学校(現在の追手門学院小学校)を創設。陸軍大将野津道貫は義弟。家紋は抱き鬼柏に剣菊紋。画像は青山霊園にて撮影。

 山田平左衛門 。1845年6月22日 – 1906年1月6日、 民権運動家。
山田平左衛門 。1845年6月22日 – 1906年1月6日、 民権運動家。 土佐国高知城下帯屋町出身。父は土佐藩(馬廻役・580石)山田清粛(八蔵)。戊辰戦争に従軍し軍功を上げる。征韓論に敗れて高知に帰り、板垣退助や植木枝盛らと立志社の設立に参加。第2代社長となり自由民権運動を主導した。家紋は菊水紋。

 日高壮之丞 。1848年4月26日 – 1932年7月24日、 海軍軍人。
日高壮之丞 。1848年4月26日 – 1932年7月24日、 海軍軍人。 薩摩国出身。薩摩藩士・宮内清之進の次男。日高籐左衛門の養子となり家督を相続。NHKドラマ「坂の上の雲」では中尾彬が演じた。最終階級は海軍大将。幾多の軍功によって男爵位を受勲。家紋は割り杏葉菊に違い鷹の羽紋。画像は青山霊園にて撮影。

 益田孝 。1848年11月12日 – 1938年12月28日、 実業家。
益田孝 。1848年11月12日 – 1938年12月28日、 実業家。 佐渡国出身。明治維新後、世界初の総合商社・三井物産の設立に関わる。草創期の日本経済を動かし三井財閥を支えた。更に日本経済新聞の前身・中外物価新報を創刊。実妹の繁子は瓜生外吉に嫁ぐ。家紋は三つ割り菊紋。画像は総持寺にて撮影。

 上村彦之丞 。1849年6月20日 – 1916年8月8日、 海軍軍人。
上村彦之丞 。1849年6月20日 – 1916年8月8日、 海軍軍人。 薩摩国出身。薩摩藩漢学師範・上村藤一郎の長男として生まれる。最終階級は海軍大将。渾名は船乗り将軍。日露戦争の日本海海戦では判断よくバルチック艦隊の進路を塞いだ。家紋は丸に橘紋と抱き菊の葉紋。画像は青山霊園にて撮影。

 栗野慎一郎 。1851年11月29日 – 11月15日、 外交官。
栗野慎一郎 。1851年11月29日 – 11月15日、 外交官。 筑前国出身。槍術師範・栗野小右衛門の長男。陸奥外務大臣から駐米公使兼駐メキシコ公使に任命され、日米改正新通商条約の調印を成し遂げる。また、パリ万国博覧会では、同郷の川上音二郎の公演を支援した。家紋の鬼菊菱紋は、鶴見総持寺にて撮影。

 東郷正路 。1852年4月19日 – 1906年1月4日、 海軍軍人。
東郷正路 。1852年4月19日 – 1906年1月4日、 海軍軍人。 越前国出身。父は福井藩士・東郷晴霞。日清戦争時は「鳥海」艦長、「西京丸」艦長を、日露戦争では第6戦隊司令官として出征し、黄海海戦、日本海海戦に参戦し、後に海軍中将となった。家紋は抱き菊の葉紋。画像は青山霊園の墓所にて撮影。

 菊池武夫 。1854年8月21日 – 1912年7月6日、 法学者。
菊池武夫 。1854年8月21日 – 1912年7月6日、 法学者。 陸奥国岩手郡出身。穂積陳重、江木衷、高橋健三、元田肇等と英吉利法律学校を創設し、中央大学初代学長に就任した。他に、司法省民事局長、東京弁護士会会長、貴族院勅選議員等も務めた。家紋は菊水紋。画像は染井霊園の墓所にて撮影。

 青山幸宜 。1854年12月9日 – 1930年2月5日、 郡上藩青山家11代。
青山幸宜 。1854年12月9日 – 1930年2月5日、 郡上藩青山家11代。 第6代藩主・青山幸哉の長男として生まれる。版籍奉還で郡上藩知事に任じられ、廃藩置県で免職された。その後は実業家、貴族院議員となって活躍した。市川米庵に書を学び、多くの名筆を残した。家紋は青山紋。菩提寺である梅窓院の墓所にて撮影。

 青山胤通 。1859年6月15日 – 1917年12月23日、 医学者。
青山胤通 。1859年6月15日 – 1917年12月23日、 医学者。 江戸に苗木藩藩士・青山景通の三男として生まれる。読みは、あおやまたねみち。東京帝国大医科大学校長、伝染病研究所所長を歴任。明治大帝の侍医、宮内庁御用掛を勤める。原田直次郎の治療や、樋口一葉の診察も行ったという。家紋は抱き菊の葉に菊紋。

 大橋新太郎 。1863年9月11日 – 1944年5月5日、 出版業者。
大橋新太郎 。1863年9月11日 – 1944年5月5日、 出版業者。 越後国長岡出身。博文館創業者大橋佐平の三男。父没後、博文館館主となり、博文館印刷所(現在の共同印刷)、日本書籍株式会社を設立。衆議院議員・貴族院議員もつとめる。家紋は杏葉菊菱紋。画像は護国寺の墓所にて撮影。

 山之内一次 。1866年12月12日 – 1932年12月21日、 政治家。
山之内一次 。1866年12月12日 – 1932年12月21日、 政治家。 薩摩国出身。藩士・山之内時習の長男。読みは、やまのうちかずじ。青森県知事、逓信省鉄道局長、第1次山本内閣内閣書記官長、貴族院勅撰議員、第2次山本内閣鉄道大臣などを歴任。家紋は丸に十六剣菊紋。画像は青山霊園の墓所にて撮影。

 夏目漱石 。1867年2月9日 – 1916年12月9日、 小説家。
夏目漱石 。1867年2月9日 – 1916年12月9日、 小説家。 江戸牛込馬場下出身。数代前から続く町方名主、夏目小兵衛直克の末子。千円札の図柄としても著名。代表作は『坊ちゃん』『我輩は猫である』『こころ』など。家紋は井桁に菊紋とも言われるが雑司が谷霊園には菊菱紋(画像)がある。

 血脇守之助 。1870年3月2日 – 1947年2月24日、 歯科医師。
血脇守之助 。1870年3月2日 – 1947年2月24日、 歯科医師。 下総国南相馬郡我孫子驛出身。加藤家に生まれるが、18歳の時に血脇家に入る。東京歯科大学の創立者の一人。日本の近代歯科医療制度の確立に尽力。また、野口英世のパトロンとして知られる。家紋の菊水紋は八柱霊園の墓所写真より。

 尾上梅幸(6代) 。1870年11月8日 – 1934年11月8日、 役者。
尾上梅幸(6代) 。1870年11月8日 – 1934年11月8日、 役者。 尾張国名古屋出身。父は尾上朝次郎本名は寺島榮之助。屋号は音羽屋。昭和初期を代表する名女形役者。十五代目市村羽左衛門の名相方とうたわれ墓も隣にある。役者としての家紋は重ね扇に抱き柏だが、雑司が谷墓地の墓所の家紋は杏葉菊紋。

 伏見宮博恭王 。1875年10月16日 – 1946年8月16日、 海軍軍人。
伏見宮博恭王 。1875年10月16日 – 1946年8月16日、 海軍軍人。 伏見宮貞愛親王王子。議定官、軍令部総長、元帥海軍大将。日露戦争では連合艦隊旗艦三笠分隊長として黄海海戦に参加。艦長や艦隊司令長官を務めるなど皇族出身の軍人の中では実戦経験が豊富。家紋は伏見宮裏菊紋。画像は息子・博英の墓所にて撮影。

 有島武郎 。1878年3月4日 – 1923年6月9日、 作家。
有島武郎 。1878年3月4日 – 1923年6月9日、 作家。 東京市小石川出身。旧薩摩藩士で大蔵官僚の有島武の長男。作家の里見とんは弟。長男は俳優の森雅之。同人「白樺」に参加。代表作は『カインの末裔』『迷路』。家紋は丸に雪持ち笹だが、多磨霊園の墓所には抱き菊の葉に雪持ち笹紋も見える。

 野口雨情 。1882年5月29日 – 1945年1月27日、 童謡作詞家。
野口雨情 。1882年5月29日 – 1945年1月27日、 童謡作詞家。 茨城県出身。生家は廻船問屋を営む名家。野口家は、楠木正成の弟、正季が先祖と伝えられているという。代表作は、『シャボン玉』『こがね虫』『雨降りお月さん』『証城寺の狸囃子』など多数。家紋は菊水紋。画像は小平霊園所に撮影。

 東久邇宮稔彦王 。1887年12月3日 – 1990年1月20日、 皇族。
東久邇宮稔彦王 。1887年12月3日 – 1990年1月20日、 皇族。 京都府出身。読みは、ひがしくにのみやなるひこおう。陸軍軍人としての最高階級は、陸軍大将。第二次世界大戦終結後、鈴木貫太郎の後を継いで内閣総理大臣、陸軍大臣に就任、憲政史上最初で最後の皇族内閣を組閣した。家紋は東久邇菊紋。

 小松輝久 。1888年8月12日 – 1970年11月5日、 華族、海軍軍人。
小松輝久 。1888年8月12日 – 1970年11月5日、 華族、海軍軍人。 東京府出身。北白川宮家。長兄・恒久王は特に竹田宮家を創設し自身は臣籍降下し小松侯爵家を創設。終戦間際まで帝国海軍の軍務に服し、最終階級は海軍中将。戦後は平安神宮宮司を務める。家紋は三つ割菊紋。画像は護国寺にて撮影。

 恩地孝四郎 。1891年7月2日 – 1955年6月3日、 写真家、詩人。
恩地孝四郎 。1891年7月2日 – 1955年6月3日、 写真家、詩人。 東京府出身。宮内省式部職・恩地轍の四男。読みは、おんちこうしろう。前衛的表現方法を用いた芸術家としてあらゆるジャンルで活躍。代表作は自身の詩や版画との組み合わせた写真集『飛行官能』『博物誌』。家紋は楠木氏家臣からの流れの菊水紋。

 甲斐庄楠音 。1894年12月23日 – 1978年6月16日、 日本画家。
甲斐庄楠音 。1894年12月23日 – 1978年6月16日、 日本画家。 京都出身。甲斐庄氏は楠木正成末裔を称した旗本の一族。読みは、かいのしょうただおと。大正末期の暗い風潮を象徴したデカダンス画家の代表。代表作『青衣の女』『横櫛』等。家紋は菊水紋。画像は文京区・吉祥寺にて撮影。

 笹川良一 。1899年5月4日 – 1995年7月18日、 政治運動家。
笹川良一 。1899年5月4日 – 1995年7月18日、 政治運動家。 大阪府三島郡豊川村の造り酒屋の長男。衆議院議員、財団法人日本船舶振興会会長、福岡工業大学理事長を務めた。戦後は政財界の黒幕として「日本の首領(ドン)」と呼ばれた。家紋は半菊に一の字紋。顔画像は高見山の引退興行での紋付姿。

 中村泰三郎 。1912年1月24日 – 2003年5月13日、 抜刀家。
中村泰三郎 。1912年1月24日 – 2003年5月13日、 抜刀家。 山形県上山市出身。実践剣術・戸山流抜刀術を修練し中村流抜刀道を創始。国際居合抜刀道連盟(国際抜刀道連盟の前身)を組織。国際武道院より抜刀道十段を授与される。橋本龍太郎に山岡鉄舟愛刀「左文字」の写しを献上した。家紋は丸に菊水紋。

 石井ふく子 。1926年9月1日 – 、 テレビプロデューサー。
石井ふく子 。1926年9月1日 – 、 テレビプロデューサー。 東京都出身。父(養父)は劇団新派の俳優・伊志井寛。TBSのプロデューサーとして「肝っ玉かあさん」「ありがとう」「女と味噌汁」「おんなの家」「渡る世間は鬼ばかり」等を手がける。家紋は菊杏葉紋。谷中・瑞輪寺の伊志井寛の墓にて撮影。

 綿貫民輔 。1927年4月30日 – 、 実業家、政治家。
綿貫民輔 。1927年4月30日 – 、 実業家、政治家。 富山県南砺市出身。父・南佐民は兵庫県淡路島の出身で楠木正成の系譜だが、井波八幡宮の宮司を務める綿貫家の婿養子に入る。自民党の重鎮であったが郵政民営化を巡る党内抗争の結果、離党し国民新党を結成。菊水紋は南家の家紋。

 恩地日出夫 。1933年1月23日 -、 映画監督。
恩地日出夫 。1933年1月23日 -、 映画監督。 東京市出身。堀川弘通監督の助監督を経て、27歳の若さで監督になる。『若い狼』で監督デビュー。代表映画監督作は『女体』『伊豆の踊子』『四万十川』など多数。一方テレビドラマでは『傷だらけの天使』の監督を手がけた。家紋は菊水紋。

 北白川道久 。1937年5月2日 – 、 元皇族。
北白川道久 。1937年5月2日 – 、 元皇族。 東京府出身。1947年10月14日に皇籍離脱し、以後は北白川道久となる。伊勢神宮の大宮司に就任。紀宮清子内親王(現・黒田清子)の結婚式において、斎主を務めた。現在は、神社本庁統理。家紋は北白川菊紋。画像は護国寺共葬墓地にて撮影。

 嵐山光三郎 。1942年1月10日 – 、 作家。
嵐山光三郎 。1942年1月10日 – 、 作家。 静岡県浜松市出身。本名は、祐乗坊英昭。2012年日本文藝家協会理事。独特の文体でのエッセイを多数の雑誌に発表。椎名誠らとともに「昭和軽薄体」と呼ばれた。家紋は三つ割菊紋。画像は高尾霊園にある祐乗坊家の墓所にて撮影。

 竹田恒泰 。1975年 – 、 法学者。
竹田恒泰 。1975年 – 、 法学者。 東京都出身。家系は伏見宮家より分かれた北白川宮家の分家にあたる竹田宮家。明治天皇の女系の玄孫に当たり、皇太子徳仁親王の三いとこにあたる。竹田恒和は父。家紋の横見菊は、「たかじんのそのまで言って委員会」出演時の紋付より。

 青山久蔵 。江戸時代後期、 北町奉行所与力。
青山久蔵 。江戸時代後期、 北町奉行所与力。 テレビ朝日系で放送された「八丁堀の七人」という時代劇の主人公の一人(もう一人の主人公は片岡鶴太郎演じる仏田八兵衛)。村上弘明が演じた。青山という姓より、徳川譜代の青山氏の庶流を想定していると推定される。家紋は丸に立ち葉菊紋。
有名人の家紋索引(あ行~さ行) (た行~わ行)
まさむね

引両紋 -無骨な武家紋の代表- 足利尊氏、近藤勇、オノ・ヨーコ...
コチラのページに移動しました。
蔦紋 -遊女が好んだ優美な紋- 藤堂高虎、谷崎潤一郎、いかりや長介...
コチラのページに移動しました。
花田家の家紋がいつの間にか替わった件に関して
 先日、Yahooの特集に「【大相撲豪傑列伝】(13)力道山の肉を食いちぎった『土俵の鬼』初代若乃花幹士」という記事が掲載されていた。
先日、Yahooの特集に「【大相撲豪傑列伝】(13)力道山の肉を食いちぎった『土俵の鬼』初代若乃花幹士」という記事が掲載されていた。
記事の内容は、「二所ノ関部屋の兄弟子である力道山のシゴキを受けて強くなったが、けいこの途中で力道山の脛にかみつき、肉を食いちぎったことがある。力道山がプロレス転向後に黒いロングタイツをはいたのは、その傷を隠すためだったともいわれる。」とあるような武勇伝であるが、僕が気になったのは、その記事と一緒に掲載されていた写真だ。
おそらく、若乃花が優勝したときのパーティの写真(写真一番上の段)だろうが、若乃花の紋付の家紋が「丸に三つ柏」なのである。
花田家の家紋と言えば、思い出す事がある。
二子山親方(元大関貴ノ花)が亡くなった時の葬儀で、離婚した憲子さんが花田家の家紋のついた帯をしてきて、貴乃花親方(元横綱貴乃花)が激怒したあの件である。
この時、葬儀の壇上に大きく飾られた紋所は、「隅立ての四つ目結い」であった。
そして、憲子さんの帯にも「丸に隅立ての四つ目結い」が入っていたのだ。
勿論、その後、貴乃花親方、兄の三代目若乃花の正装の紋付にはこの紋が入っている。
さて、それでは何故、先代若乃花の家紋と二子山親方、あるいは貴乃花親方の家紋が違うのだろうか。
勿論、僕はここで、巷に流布している花田家に関するくだらない噂(真実の親子関係など)を云々しようとしているわけではない。
家紋というものが得てして、このように替わってしまうものだという事を確認したかっただけである。
花田家の家紋がいつの間に「丸に三つ柏」から「丸に隅立ての四つ目結い」になったのか。
そんなコロコロ替わってしまうものに対して何故、貴乃花はあれほどこだわったのか。
謎と言えば謎ではある。
しかし、それでもいいのである。
誰も真実をもって貴乃花に詰め寄るようなことはしない。
日本人というのは、おおらかなものなのである。
◆
本人が、これがウチの家紋だと言い張れば、それはそのウチの家紋になる。
これが、ウチの伝統だと思えば、それがウチの伝統になる。
正確な経緯とか、歴史の真実などどうでもいいのである。
例えば、井の頭公園弁財天の神紋にしても境内各所にある対い波に三つ鱗の紋の波の形が少しづつ違うではないか。
本当はどの形が正しいのかなどは野暮な疑問なのである。
これは推測であるが、二子山親方(元大関貴ノ花)が、「四つ目結い」は家族の絆の象徴だからと誰か(霊友会関係者?)に言われて、花田家の家紋として、採用しただけかもしれない。
ちなみに、和泉元彌の和泉家も「雪輪に隅立て四つ目結い」を家紋としている。
花田家、和泉家、ともに現代日本を代表する伝統芸の一家であるが、家紋の意味とは裏腹に、家族内のゴタゴタが事あるごとに漏れ伝わってきてしまうのは皮肉である。
◆
さて、歴史の真実と言えば、戦後、日本では戦前の日本がどうであったのかという論争がずっと続いている。
最近も、自衛隊の田母神氏の論文が問題になった。
おそらく、彼の論文に対して、真実はどうかという歴史考証のレベルで話をしてもそれほど実りがあるとは思えない。
重要なのは、田母神氏が信念を持って論文を発表したということだ。
おそらく、田母神氏が日本は決して悪くなかったと信じている。それは貴乃花が四つ目結いを伝統的に花田家の家紋であると信じているのと同じことだ。
それゆえに、もし、彼がいずれかの討論会などで完全に論破されたとしても、その後で一言つぶやくだろう。
「それでも、日本は悪くない」と。
◆
人が信じていることを替えさせるというのは、本当に難しいことだと思う。
まさむね
聖子とヨーコ
 いまの私がいちばん好き
いまの私がいちばん好き
もっと自分を好きになる
最近、松田聖子が出演するDiosa(ヘアカラー)のCMのコピーである。
いまだに輝き続ける彼女に相応しいキャッチだ。
「自分らしく生きる」という誰でも出来そうで誰にも出来ないスタイルを貫く松田聖子。
彼女には、支持するファンが存在すると同時に、彼女に対して、嫌悪感を隠さない人々もいる。その人生は、その嫌悪感に対する闘いの歴史でもあった。
しかし、彼女が立派なのは、どんなに逆風が吹いても彼女は逃げなかった事だ。
ある芸能記者によると、「どんな状況でも松田聖子は取材に応じる」そうである。
そして、彼女はいつも”松田聖子”であり続けるそうだ。
闘い続けた女性だけが表現できる迫力、今回のCMにはそんなものを感じる。
来週22日(水)に発売予定のニューシングル「あの輝いた季節」は、またヒットチャートを賑わしてくれる事だろう。
—
世界中のすべての時計を二秒ずつ早めなさい。
誰にも気づかれないように。
これは、松田聖子がデビューする30年程前に、アメリカに渡り、前衛芸術家として活躍、後にビートルズのリーダー、ジョン=レノンと結婚、ビートルズ解散の元凶と言われ、世界中からバッシングを受けたオノ・ヨーコが、60年代初頭に著したインストラクションアート(命令文による詩集)「グレープフルーツジュース」の中の
一節だ。
彼女は一般的にはジョンの妻としてのみ有名であるが、ジョンと出会う前から芸術家として素晴らしかったのだ。
この2行を読んでもらえば、分かる人にはわかるよね。
ちなみに、彼女は今でも毎年、日本のアーティストを集めて武道館でチャリティコンサートを行っている。
今年も12月8日にあるらしい。奥田民生、斉藤和義、ボニピン達に加えて、今年は、Salyu、絢香や宮崎あおい達も出るらしい。
ヨーコもまた闘い続けた女のみが出せるオーラをいまだに持っている。今年のステージも今から楽しみだ。
さて、松田聖子とオノ・ヨーコは実はある共通点があるのだ。
知る人ぞ知る事実なのだが、二人とも九州の柳川・立花藩の家老の家の末裔なのだ。
ちなみに、松田聖子の蒲池家の家紋は左三つ巴(一番上)、オノヨーコの小野家の家紋(一番下)は一つ引両だ。
世が世なら、この二人の家老の姫達がそれぞれの立場で顔を合わせていたかと想像するのも一興か。
そんな城内ってもしかしたら、まわりは大変だったかも…
それにしても、柳川って僕も一度行った事があるんだけど、大林宣彦監督の「廃市」の舞台になった、美しい運河(写真中)の街だ。
この映画のタイトルでもイメージ出来るように、ある意味、消えゆく日本美の象徴みたいな街なんだよね。
ちなみに、この「廃市」には先ごろ亡くなられた峰岸徹さんも出演されておりました。合掌。
まさむね
「篤姫」の家紋に物申す
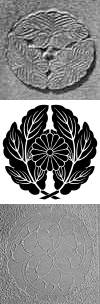 篤姫のような本格的な時代ドラマを見ていると、僕はどうしても(若干の悪意を含みながら)登場人物の家紋に目が言ってしまう。
篤姫のような本格的な時代ドラマを見ていると、僕はどうしても(若干の悪意を含みながら)登場人物の家紋に目が言ってしまう。
いつも気になるのが、徳川家茂と一橋慶喜の家紋が同じに見える事。
ものの本によると、三つ葉葵でも、徳川宗家の家紋は3つの葉が中心がくっついているが、一橋家では離れていたらしい。
まぁウチはまだアナログテレビなので、微妙な差異は見分けられないんだけどね。
そして、今日の「篤姫」で気になった事。
本日の放映回では、西郷隆盛が島津久光に許されて薩摩の軍役に復帰するのだが、その際、紋付を羽織っていたのだが、その家紋が「抱き菊葉に菊」(写真真中)だった。
確かに、西郷さんといえば、この「抱き菊葉に菊」と言われているのだが、この家紋は明治天皇から下賜されたもののはずだ。
という事は、禁門の変(1864年)の時点で西郷隆盛がこの紋付を着ているのはおかしいのではないだろうか。
それでは、西郷の元々の家紋は何だったのであろうか。
多磨霊園にある、西郷隆盛の弟の西郷従道の墓の家紋は写真一番上だ。
これが、梶の葉なのか、菊の葉なのか、僕にはちょっとわからない。
しかし、ここからは推測だが、元々、菊の葉の家紋だった西郷家の隆盛に対して、明治天皇が「私をずっと守ってほしい」という意味を込めて、その菊の葉が囲む菊の花の紋を与えたのではないか。
さて、西郷と言えば、大久保だが、青山墓地にある大久保利通の墓にある家紋は写真一番下。僕には藤巴紋に見える。
ちなみに、この藤巴紋は、寅さんで有名な渥美清の本名、田所康雄の家紋でもある。
家紋を調べていくと、全然別のキャラクタの人々が同じ紋を持ってたりするから面白い。
まさむね
秩父の街 紋所散歩1
 知らない街を歩いて、いろんなものを見て回る時、私はその街に点在する紋所(家紋)を意識的に見て回るようにしている。
知らない街を歩いて、いろんなものを見て回る時、私はその街に点在する紋所(家紋)を意識的に見て回るようにしている。
街の歴史がイメージされるからだ。
勿論、私は歴史の専門家ではないので、それは実証というものからは遠い。あくまでもイメージ(想像)して楽しもうというのだ。
最近は、C型肝炎のおかげで、出かける事はめっきりと減ってしまったが、以前はたまに、そんな街散策を楽しんだ。
例えば、今年の冬に妻と出かけた秩父日帰り旅行。楽しかった。
街のメインストリート(西武秩父駅~秩父神社)は700メートルくらい。左手に慈眼寺(写真-1)という秩父札所十三番の寺がある。
本堂の後ろに墓地があり、覗いてみた。墓石の紋所には九曜(写真-2)、七曜等の曜(星)紋系が多い。恐らく、ここは、平氏の流れをくんだ(くんだと思い込んだ?)人々が根付いている土地なのであろう。ものの本にも、この土地は平氏良文流・支流の秩父一族が支配していたとある。そして、彼らは自分達のシンボルに曜(星)を選んだのだ。
元来、農耕民族であった日本人は星への信仰はそれほど強くない。関東~南東北にかけて、星宿信仰があったようだが、これは星系紋の集中地域でもある。
日々、星の位置、動きに敏感にならざるを得ない海洋民族、狩猟民族あるいは渡来人の流れをくむ者が、この地方に居住していたのかもしれない。彼らにとっては、真夜中の移動の際に自分が現在どこにいるのかというのが最も重要な情報であり、そのため、天の星は神に近い存在=命綱だったのだ。
ちなみに、星野さん、星川さん、星さんというように、名字に星がつく家は、星宿信仰者の末裔である可能性が高いという。
「巨人の星」の主人公の星一徹・飛雄馬を輩出した星家もそうかもしれない。
原作漫画では星家の長屋の部屋には、折口信夫全集があった(竹熊健太郎さん談)そうであるが、一徹は自分のアイデンティティを定住民としてではなく、マレビト(異人)に求めていた可能性がある。
一徹の周囲に迎合しない生き方は、”星”という名が持つ宿命なのかもしれないのである。
なんか、最後は秩父とは全くかけ離れてしまったね。
秩父の街 紋所散歩2へつづく
まさむね